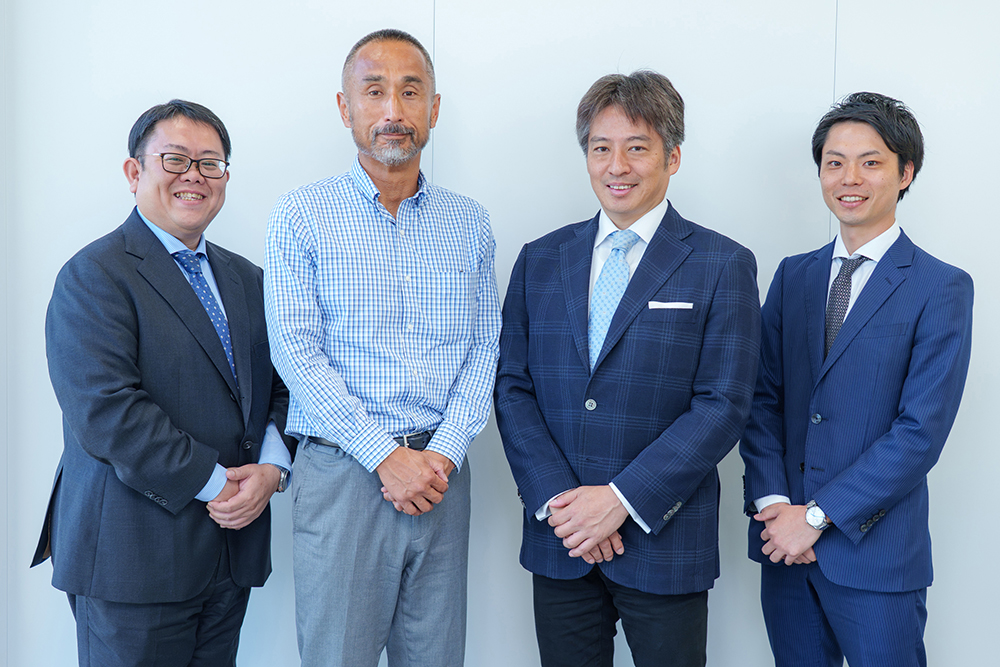平日9:00〜18:00

“泥臭さ”を信じ、“行間を読む力”に助けられたM&A。従業員とカルチャーを大切にする両社が結ばれた奇跡のパートナーシップ
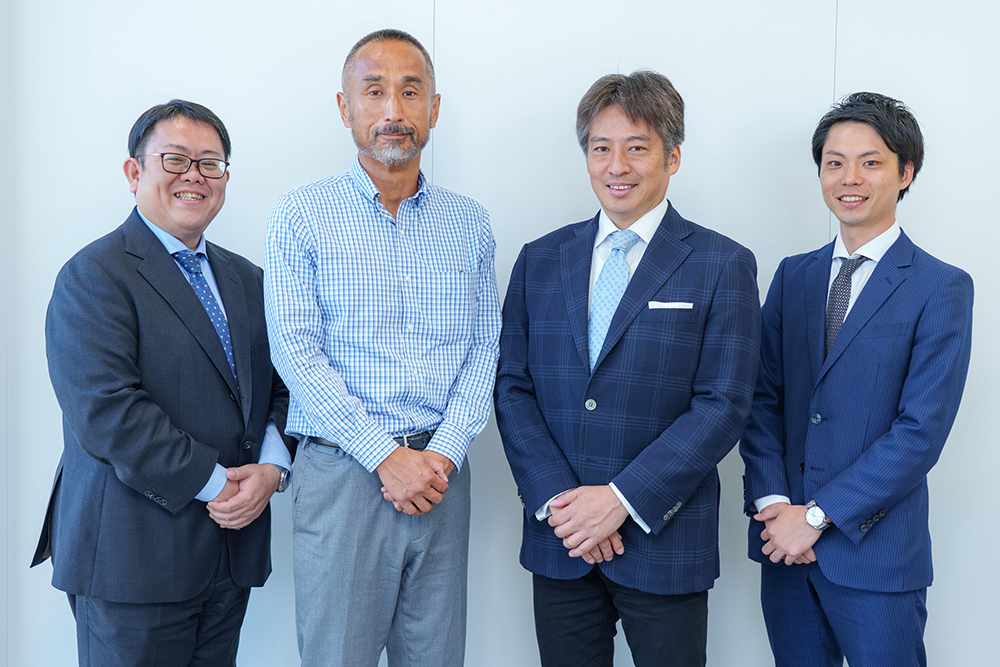
写真左より レコフ担当者生井、株式会社中本・アンド・アソシエイツ代表取締役桐島様、
丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社常務執行役員 グループCSO堀様、レコフ担当者佐藤
インタビュー概要
日本オラクル株式会社のERP製品の導入支援ベンダーとして、業務領域の広さやその実績から“国内屈指の専門家集団”として知られる株式会社中本・アンド・アソシエイツ。少数精鋭ながら安定した経営と顧客の信頼を30年以上積み重ねてきた優良企業が、なぜM&Aを選択することになったのか。どうして、パートナーとして丸紅I-DIGIOホールディングスを、アドバイザーとしてレコフを選んだのか。代表取締役社長の桐島良昌様と、譲受側である丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社の常務執行役員グループCSO兼コンサルティング&SI本部長 堀 佳介様に、これまでの経緯と現在、そして未来について伺った。
インタビュイーのご紹介

株式会社中本・アンド・アソシエイツ
前代表取締役
桐島 良昌様
中本氏が創業したオラクルERP事業へ1993年から参画されました。
その後30年にわたり同社を業異屈指の著名企業へ成長させた古参社員の一人として尽力し、2025年6月に丸紅I -DIGIOホールディングス株式会社に譲渡されました。
未知の市場に飛び込み
“ブリッジ役”を担いながら
唯一無二の存在へと成長した
まずは中本・アンド・アソシエイツという会社の成り立ちからお話しください。

桐島(譲渡企業)
1993年に創業者の中本がERP導入サービス事業をはじめたきっかけは、日本オラクル社と中本の偶然の出会いでした。当時、ERP事業を立ち上げようとしていた同社は、日本の複雑な会計業務に精通したパートナーを強く求めていました。そんな時期に、監査や翻訳業務で同社と取引のあった中本に白羽の矢が立ったのです。
しかし創業当時は、OracleやSAPといった外資系のソフトウェアは、「日本企業ならではの複雑な業務の進め方に合うはずがない」という懐疑的な見方が一般的でした。だからこそ、お客様の業務と製品の機能、その双方を深く理解し、両者の間に立って橋渡しをする“ブリッジ役”の存在が不可欠だったのです。昔も今も新システム導入で大きな壁になるのは、現場からの抵抗です。日々の業務フローが変わることを懸念する現場の方々の納得感を積み上げ、全体最適を理解されているトップとの整合を図り、より俯瞰的な視点を持つ経営層からは強力な方針を社内に打ち出していただく。組織内の力学を読み解き、会社全体の合意形成を醸成し、プロジェクトを成功に導く。それこそが創業者・中本の卓越したコンサルティング能力であり、その後の社員たちが継承してきた弊社の真の強みです。
また、当時この業界ではパッケージに追加開発をたくさん施して売上を上げるビジネスモデルが主流でしたが、私たちはあえて逆の道を選びました。お客様の業務を深く理解することを起点に、パッケージ標準機能でのソリューションを可能な限り提示。業務改善は当然のこととして、お客様のコストを抑えるようにもしていきました。今でこそFit to Standardという言葉がありますが、創業からしばらくは、特に日本のERPベンダーの中では異端なアプローチだったと思います。
創業当時の風景で思い出すのは、築年数の古い80平米のオフィスに、売上高数兆円規模の複数の会社から役員や幹部の方々が「中本さんにコンサルティングをお願いしたい」と、直々に足を運んで下さったことです。あの方々にとっては大手・準大手のSIerやコンサルティングファームに依頼する方が、社内手続きも含めて容易だったはずです。それでも選んで下さったのは、会社の規模以上に、中本やチーム中本を信用して下さったからだと思います。
そうした経験が、その後、見た目の規模だけを気にしすぎずに、強みやユニークさを追究しながら”足腰を鍛える”ことを優先してきた経営方針につながっています。創業当時の社員数は限られていましたが、下請け・孫請けではなく、あえて大手・準大手と同じ市場でプライムベンダーとして戦っていく道を選んだのも、中長期的な視野での強固な会社づくりのためでした。現場仕事において組織の庇護が薄く苦労をかける社員たちには、業界平均よりも高い給与を払い、きずな重視の社風を醸成し、安心して長く働いてもらえるよう努めてもきました。目先の売上や規模拡大よりも組織の足腰づくりこそが、数年までの中本・アンド・アソシエイツの経営の最優先事項だったのです。
買収、そして合併も検討し
あらゆる可能性を模索した末
M&Aという決断に至った
M&Aを意識するようになったきっかけを
教えてください。
桐島(譲渡企業)
経営環境の変化がもたらす問題は常にあるものですが、数年前からはほとんどの企業がそうであるように、弊社も「日本人の人材採用の難しさ」に直面していました。自力で組織を強くすることを優先してきた弊社にとって、今後協業パートナーを拡大していく中でも、採用難は成長を加速できるかどうかに関わる問題であると認識しはじめました。
そこで私たちは、この問題もまずは自力での解決を試みました。短期間に要員数を増やすことを戦略目標とし、その方策として弊社が小規模開発会社を買収することや、弊社と同規模・同業種の会社との合併を模索しました。市場全体の長期的な見通しは明るかったので、成長の加速も果たせると考えたからです。しかしながら約3年続けたものの、期待する成果には至らず諦めました。当社のような規模の会社に買われたり、一緒になることを前向きに検討する会社にたどり着く見通しと、今後それにかかるであろう時間について学習した結果です。
中本と私は約3年の学習を経て「株主・経営者自身から刷新することが、採用問題の解決と今後の成長の加速を短時間で成し遂げる最善・最後の方策」という考えに至り、M&A助言会社を通じた事業承継へと舵を切りました。「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」と、会社がより大きく飛躍できるのであれば、それこそが正しい決断だと確信したのです。
M&Aの実行を決めてから、アドバイザー選びは慎重に進めました。複数のM&A助言会社と面談をしましたが、その中で評価が最も高かったのがレコフです。その魅力は彼らの「いい意味での泥臭さ」に尽きました。見栄えの良さや口先の巧さではなく、実直にお客様と向き合うことが本質的な価値を生む、という弊社の仕事の哲学と、彼らの姿勢に通じるものを感じたのです。
ここからはレコフの担当者にも話を聞いていきます。
中本・アンド・アソシエイツにプレゼンした意図は
どのようなものだったのでしょう。
生井(レコフ担当者)
桐島様から最初にお話を伺った際、一度他のM&A助言会社とM&Aを試みてもうまくいかなかったという経緯をお聞きしました。そこで、過去にご検討された候補先を拝見したのですが、正直に申しますと、「これでは、うまくいかないのは当然だ」と感じました。銘柄を見ただけで、「この会社は合わないだろう」と判断できるほどだったのです。そのため、我々が培ってきたIT業界でのM&Aの経験を活かせば、もっといいご提案ができるだろうという自信がありました。
さらに幸運にも、ちょうど桐島様からご相談をいただく少し前、後に最終的なお相手となる企業グループのM&Aへの意欲と戦略を詳しくお聞きする機会がありました。そのため、今回桐島様のお話を伺った瞬間に、両社の組み合わせをひらめいたのです。
もちろん、あくまでも候補先は広くお考えになるべきなので、他の会社もお声がけはさせていただきましたが、この両社をお引き合わせすることこそが、我々の介在価値だと信じ、ご提案させていただきました。
桐島(譲渡企業)
株主・経営者にとって最も重要だったのは、残る社員たちの未来でした。経営の母体が変わっても、この会社を支えてきた社員たちが安心して、これまで以上にやりがいを持って働ける環境でなければ、M&Aをする意味がありません。その本質を理解した上でパートナーを探してくださったことに、大変感謝しています。
会社の独立性を尊重し、
今の形のまま成長してほしいという
理想的な提案をしてくれた
お相手
ここからは、譲受会社である丸紅I-DIGIOホールディングスの堀様にもご参加いただきます。まずは、事業概要からお聞かせいただけますか。

堀(譲受企業)
丸紅I-DIGIOホールディングスは、総合商社である丸紅グループのICT・デジタル領域を担う事業会社グループで、グループ全体の社員数は約1,450名、連結売上高は約700億円です。ITコンサルティングからシステムの開発・運用、セキュリティ、SaaS型のサービスまで、ICTに関する多様なソリューションを幅広く展開しています。
我々の強みは、ITコンサルティングから開発・運用までを網羅する、その幅広いソリューションにあります。しかし、私たちは単なるソリューションの提供者ではありません。お客様からのご要望にお応えするだけでなく、いかにそのビジネスに深く入り込み、課題を先回りして解決する能動的なご提案ができるか。ただ言われたものを作るのではなく、お客様とともに未来を創っていくパートナーとなること。
そうした“フロントに立つ力”こそが、今後の我々の成長には不可欠であり、何よりも大切にしている姿勢です。
貴社のM&Aに対する考え方についてお聞かせください。
堀(譲受企業)
我々の成長戦略において、M&Aは自社リソースだけでは実現できない非連続な成長を遂げるための、まさに主軸です。ただし、そのM&Aを進める上で何よりも重視しているのは、事業規模やスキルセットではありません。唯一絶対の基準は「カルチャーフィット」です。その企業が持つ独自の文化を心から尊重し、ともに成長していけると感じられるか。すべては、その一点にかかっています。
この考え方は採用活動においてもまったく同じです。以前、素晴らしい経歴を持つ専門職の方を50名近くご紹介いただいた際も、最終的にオファーを出したのは数名だけでした。スキル以上に、その人の持つマインドセットや空気感が我々のグループに合うかを何よりも優先するからです。 ただ、正直に申し上げますと、最初にご提案をいただいた時点では私自身の中にあった古い情報から、一度はその真価を正しく見抜けずにいました。しかし、その反応を見た生井さんから「本当にそれでいいのですか?」と念を押されたのです。その一言で我に返り、改めて深く調査した結果、自分の見方がいかに表層的であったかに気づかされました。あの的確な助言がなければ、この素晴らしいご縁を逃していたかもしれません。
中本・アンド・アソシエイツが貫いてこられたのは、会計制度・会計業務への深い理解と洞察からくる、お客様にとって真に最適な業務要件・システム要件をご提案してこられた姿勢であり、弊社はその点を高く評価させていただきました。その根底にあるお客様への誠実な姿勢。調べれば調べるほど、それらが我々のカルチャーと深く共鳴し、かつ我々が持っていない素晴らしい価値であると分かり、「ぜひとも我々の仲間にお迎えしたい」と強く感じたのです。
生井(レコフ担当者)
具体的なビジョンについては、M&Aのプロセスを通じてさらにすり合わせが必要だと考えていましたが、我々が事前に伺っていた戦略の根底には、相手にリスペクトを持って「お迎えする」という、丸紅I-DIGIOの明確な考え方があったのです。
その基本的な方向性が、桐島様や中本・アンド・アソシエイツにとって理想的なパートナーの姿だと感じられたため、「この組み合わせは必ずうまくいく」という強い確信を持つことができました。
丸紅I-DIGIOホールディングス様とご一緒になるまで、
どのようなご検討を進めたのですか。
桐島(譲渡企業)
複数の候補企業と具体的にお話を進めていきました。その中で、株主・経営者が評価の軸として最も重視していたのは、事業規模や条件面よりも、まず「社員たちとの相性」です。会社の未来、社員の未来のために、彼らが新しい環境で安心してやりがいを持って働けるかどうか。それがすべての判断の基準でした。
株主・経営者の評価が一通り終わった後はリーダークラスの一部にだけ本件を共有し、彼らの要望、疑問、不安をひとつひとつ解消していく作業を加えました。弊社の事業はヒトが全てです。去っていく株主・経営者だけがM&A検討の主役なのではなく、殘ってリーダーシップを発揮していく者たちも検討中の主役です。交渉事につきものの制約には我慢してもらいましたが、早い段階から彼らの納得感の醸成をはかりました。丸紅IDIGIOホールディング様とご一緒できた最大の立役者をあげるなら、中本や私ではなく、自分たちの納得感の醸成にとどまらず、弊社の将来を思って有用な指摘や配慮、根回しの労をとってくれた清瀬現副社長、執行役員および管理部長でしょう。
最終的に数社と面談させていただきましたが、その中でも丸紅I-DIGIOの堀様のご提案は、まさに飛び抜けていました。私たちが抱える採用という弱点を的確に理解し、具体的な解決の道筋を示してくださったのはもちろんですが、その社員を想う姿勢に感銘しました。初回の株主面談で、堀様は私たちが最も懸念していた人事制度について、詳細な資料とともに丁寧に説明してくださいました。そのお話から、中本・アンド・アソシエイツの独立性を尊重し、「今の形のまま、グループの一員として成長してほしい」という想いが、単なる言葉だけでなく本心であることが伝わってきたのです。
実は、お会いする前から丸紅グループという信用力に大きな魅力を感じていました。一方であくまで相性を重視し、フラットな視点で臨んでいましたが、堀様のそのお考えに触れたことで、「ここしかない」と確信に変わりました。最終的には、株主面会後の執行陣紹介の場でも、皆の意見が完全に一致し、すんなりと決まったのです。
社員の未来と自社の課題解決を重要視されたのですね。
桐島(譲渡企業)
その通りです。今回のM&Aにおける私の関心事は、突き詰めればただ一点、「長年の課題であった採用という弱点を、本質的に解決できるか」ということだけでした。今回のM&Aにおける中本と私の狙いは、「採用問題を短期間に解決する」、「当社事業の成長を加速させる」ということでした。もちろんその前に「社員にとって今よりもよい職場となっていただける会社と」という大前提がつきます。
アドバイザーとしてレコフはどのようにサポートしたのですか。
生井(レコフ担当者)
プロセスで我々が何よりも心がけていたのは、交渉の条件面だけでなく、お相手が「今、何に悩み、何を乗り越えようと苦慮されているのか」という、言葉にならない部分の解像度を最大限に上げることでした。M&Aの交渉は、当事者同士のさまざまな思惑が絡み合います。我々はその中心に立ち、双方のお考えを深く理解し、正確にお伝えすることに徹しました。
佐藤(レコフ担当者)
そのために、私たち担当者同士でも常に密に会話を重ねていました。面談が終わるたびに「今日のあのご発言は、きっとこういう考えの表れだろう」「今、こう感じているのではないか」という“すり合わせ”を常に行い、真意を理解するよう努めました。ご両社がどう思われているかを常に意識しながら、プロセスを進めることを心がけていました。
言葉にならない想いを汲み取り
「行間を読む力」で先回りし
常に安心感を与えてくれた
成約後の率直なお気持ちをお聞かせください。

桐島(譲渡企業)
丸紅IDIGIOホールディングス様という、これ以上ないお相手に継承できて一安心しています。と同時に中本も私も、これからの会社の発展と、新しい環境での社員のしあわせを陰ながら祈っている思いです。
堀様(譲受企業)
我々にとってクロージングは、あくまで通過点に過ぎません。ここからが本当のスタートです。その手応えを、先日行った1泊2日の役員合宿で早速感じることができました。中本・アンド・アソシエイツの役員の方々にもご参加いただいたのですが、良くも悪くも長年のやり方に染まっている我々の幹部に対し、彼らが一切空気を読まずに「それは違うのではないか」と率直に意見を述べてくれる。その光景は、文字通り「痺れるぐらい最高」でした。こういう新しい化学反応こそ我々が求めていたものであり、「だからこそ、お迎えした甲斐があった」と心の底から思いました。そして今後は、彼らがその個性を失わないように守っていくことこそが、私の仕事だと強く感じています。
今後は、中本・アンド・アソシエイツが持つ専門性を、存分に発揮してもらいます。彼らがお客様の業務の根幹に深く入り込むことで生まれる新たなビジネスチャンスを、グループ全体で捉えていきたい。もちろん、我々が持つ採用力やネットワークも最大限に活用し、彼らの更なる成長を全力でサポートしていきます。そしてそれは、会社組織のあり方についても同様です。私は常々「ライフの中にワークがある」と考えています。自分を犠牲にして会社に奉公するのではなく、社員一人ひとりの人生がまず充実して初めて、仕事でも良いパフォーマンスが発揮できる。これは新しく仲間になった皆さんだけでなく、1,400名を超えるグループ全社員にそうあってほしいと考えています。自分の力が一番発揮できるやり方を全員が見つけられる、そんな組織を目指していきたいですね。
レコフの担当者はどのようにお役に立てたでしょうか。

桐島(譲渡企業)
まず前提として、お二人はコンサルタントである以前に、一人のビジネスマンとして非常に信用できる方々でした。会社の看板は立派でも、担当者がともなわないケースは往々にしてありますが、彼らは違いましたね。その信頼感をベースに、フットワーク軽く動いてくださいました。
そして、まさにお二人がそうした姿勢でいてくださったおかげで、助かった場面は多々ありました。伝えなければいけないことを、その場ですべて伝えられなくても、状況を察して先回りして動いてくださる。その“行間を読む力”と安心感があったからこそ、最後まで信頼関係を崩さずにゴールまでたどり着けたのだと、心から感謝しています。
堀(譲受企業)
レコフでなかったら、このディールはクロージングできなかったと断言できます。
まず、多くのFA*は、論点だけを提示して「さあ、考えてください」というスタンスであることが多いです。しかし、レコフのお二方はまったく違いました。常に「落としどころは、おそらくこのあたりでしょう」という具体的な仮説とその背景にあるロジックまで示してくださるからこそ、我々も迅速な意思決定ができたのです。
そしてもう一つが、プロセス管理の的確さです。M&Aの交渉は、どうしても双方にストレスが溜まります。「まだこんな論点が出てきたか」と感じる局面でコミュニケーションがこじれると、ディールブレークになりかねません。レコフのお二方は、そのコミュニケーションにおけるルールを最後までぶらすことなく管理し、我々が常に本質的な議論に集中できる環境を整えてくださいました。
そして何より、彼らは常に「売り手にとって、本当の優先順位は何か」という本質を深く理解しようとアンテナを張っています。だからこそ、我々買い手側も、的外れな提案に時間を費やすことなく、安心して交渉に臨むことができました。そのおかげで、これ以上なくスムーズにプロセスを進めることができたと、心から感謝しています。
*Financial Advisor:仲介者と異なり、片側当事者(この場合は売手)のみに起用され、当該当事者の利益最大化を目指して案件を主導する役割。仲介者は双方に起用され、両者意向を調整のうえ案件を成約させることを目指すという点で役割に違いがある。一般に、中小M&Aでは友好的な関係の維持と円滑なプロセス推進が望まれることから、片側に就いて利益追求を図るFAではなく、両当時者の合意調整を第一義とする仲介者が起用されることが多い。
ありがとうございます。最後に、M&Aを検討している経営者に向けてメッセージをお願いいたします。
桐島(譲渡企業)
これからM&Aを検討される経営者の方に、私自身の経験からお伝えしたいのは、まず「情報をオープンにすること」の重要性です。アドバイザーに対して、何か駆け引きをするようなことは絶対にしない方がいい。オープンにできる段階があるかもしれませんが、自社の強みも弱みもすべて正直にさらけ出さないと、本当に信頼できる関係は築けません。もし、表面的に取り繕った情報で話を進めてしまうと、優秀なアドバイザーほど離れていってしまうでしょう。
その上で、特に私たちのような中小企業の経営者は、スマートさや見栄えの良さではなく、実直に、汗をかいてくれる“泥臭い”相手をアドバイザーとして選ぶべきです。自社の価値観と合う、心から信頼できるパートナーを見つけること。それが、M&Aの成功に向けた、何よりも重要な第一歩だと思います。
堀(譲受企業)
M&Aはゴールではなく、あくまで未来を創るための手段です。我々譲受側の目線で言えば、自社に明確なビジョンがあり、「この会社のこの力が必要だ」という確信がある場合にのみ、M&Aは大きな力を発揮します。
そして、その確信の根幹にあるべきなのは、「カルチャー」を見極めることです。私にとってM&Aは会社を買うという感覚ではなく、新しい家族を迎えるという感覚に近い。売り手であるオーナー経営者が、「自分の子供を渡すつもりです」とおっしゃる、その言葉の重みを深く受け止め、その大切な会社をお預かりする覚悟がなければ、一緒になるべきではありません。M&Aの成功は、結局のところ“人とカルチャーで決まる”と、私はそう考えています。
そして、この「家族」を、これからも増やしていきたいと考えています。今後、第2、第3の中本・アンド・アソシエイツのような素晴らしい会社をお迎えする際に、先に仲間になった彼らが「丸紅I-DIGIOグループに入って本当に良かった。ぜひ、おいでよ」と、新しい候補企業の背中を押してくれるような、誰もが入りたいと思えるグループを創り上げていくことが私のこれからの目標です。
佐藤(レコフ担当者)
振り返りますと、「非常に良いディールだったな」と、この一言に尽きます。何より、誰もが知る丸紅グループが強い熱意を持って仲間に迎え入れたいと願う中本・アンド・アソシエイツという、素晴らしい会社のM&Aに携われたことが嬉しいです。その最初の両社面談で、堀様のビジョンがあまりに素晴らしく、「これは、もう決まったのではないか」と直感したことを今でも覚えています。
もちろん、プロセスの中ではさまざまな論点がありました。しかし、両社のトップが互いに深い敬意を払い、熱い想いをぶつけ合う姿を間近で見ながら、「このディールは絶対にブレイクすることはないだろう」という不思議な安心感がありました。その想いの架け橋となれたことは、アドバイザーとしてただただありがたい経験であり、この素晴らしいご縁に心から感謝しています。
生井(レコフ担当者):
皆様からは「スムーズだった」とのお言葉をいただくこともありましたが、決して平坦な道のりばかりではなかったと思っています。M&Aのプロセスでは、両社が「ここでボタンを掛け違えたら間違いなくディール・ブレイクする」ような、調整が大変な局面も間違いなくありました。
その困難を皆様が真摯に向き合い、乗り越えてくださったこと。その事実に、私はアドバイザーとして本当に嬉しく感じていますし、最後までご協力いただけたことに、心から感謝しています。
もし我々が、その過程で皆様のお考えを引き出し、ご成約までのお手伝いができたとご評価いただけるのであれば、これに勝る喜びはありません。この度のディールに立ち会えたことを光栄に思います。今後とも個人的にも、皆様と良いお付き合いをさせていただけたらと願っております。


本件のアドバイザー
株式会社レコフ マネージング・ディレクター
生井 寛尚
2005年レコフ入社、ソーシングからエグゼキューションまで一連のM&A業務に従事。M&A戦略立案支援、事業戦略におけるM&A推進の位置付けや実行に関する助言、統合型・カーブアウト型などを含む組織再編や事業選択の助言などを経験。

本件のアドバイザー
株式会社レコフ ヴァイスプレジデント
佐藤 幹也
有限責任監査法人トーマツにて約10年間IFRS基準のグローバル企業含めた 上場/非上場企業の監査(法定監査・内部統制監査等)業務やアドバイザリー業務(会計、内部統制・経営体制、財務諸表分析等)に従事。 上場企業の監査主任も務め、2年間のDeloitte UK London officeへの出向(海外駐在)も経験。 2023年レコフ入社後、CFDにてエグゼキューション業務に従事。 公認会計士(CPA)
主な成約インタビュー
弊社でご成約されたM&A事例・実績をご紹介します。
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00