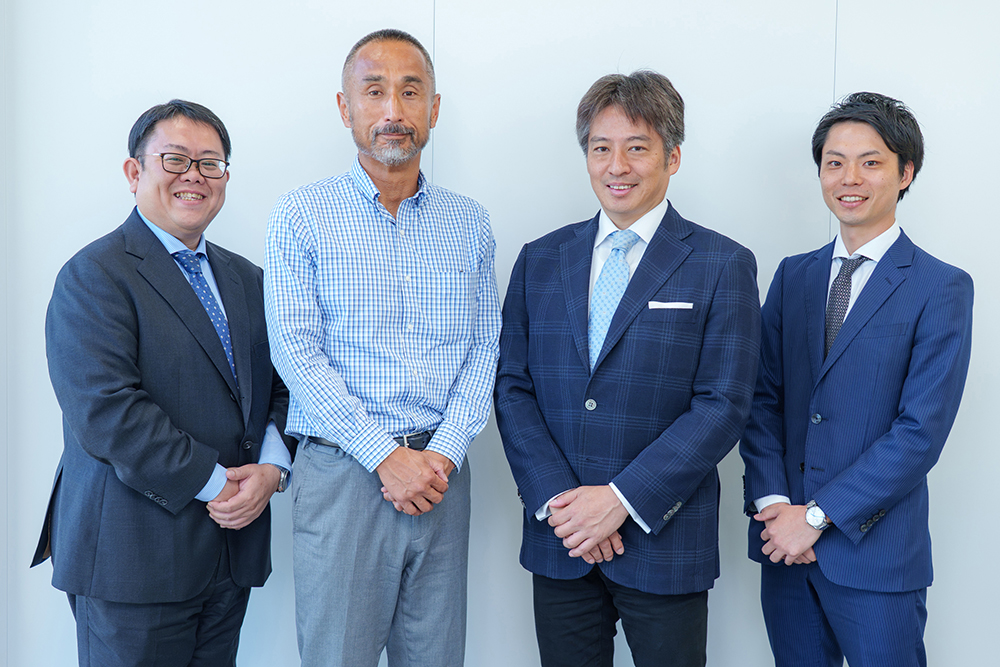平日9:00〜18:00

寄り添い、客観的な視点で選択肢を整理してくれるアドバイザーが果たした真の役割

写真左よりレコフ担当者岩田、株式会社ユカリア執行役員高橋様、株式会社メディステップ代表取締役中村様、レコフ担当者小寺
インタビュー概要
東京23区を中心に、訪問看護と居宅介護支援事業を展開する株式会社メディステップ。「住み慣れた場所でいつまでも自分らしく」という理念のもと、質の高いケアで地域社会の信頼を集め、着実な成長を遂げてきた。順調に事業を拡大してきた同社が、なぜM&Aという決断に至ったのか。パートナーとして株式会社ユカリアを、そしてアドバイザーとしてレコフを選んだ理由とは。代表取締役の中村 達也様と、譲受側である株式会社ユカリア執行役員 経営戦略本部副本部長 高橋 典久様に、これまでの経緯と現在、そして未来について伺った。
インタビュイーのご紹介

株式会社メディステップ
代表取締役
中村 達也様
IT・金融業界でキャリアを積んだ後、医師である友人から「仮想病院」構想を打ち明けられたことをきっかけに、ヘルスケア業界へ。2015年7月、株式会社メディステップを設立。異業種で培った知見を活かし、創業から約10年で組織を拡大させたのち、2025年6月に株式会社ユカリアとのM&Aを実行されました。
親友との約束から
生まれた「仮想病院」。
ヘルスケアの常識に挑んだ10年間
まずは、メディステップという会社の成り立ちからお話しください。

中村(譲渡企業)
2015年に設立したメディステップは、訪問看護と居宅介護支援を主な事業としています。すべての始まりは、医師である親友からの「中村、三軒茶屋で会社を作ろう」という突然の誘いでした。
三軒茶屋で糖尿病内科を開業している彼は、私たちの会社の原点となる“仮想病院”というビジョンを熱く語ってくれました。「都心ではもう新しい大規模病院は建てられない。それにもかかわらず、高齢化で亡くなる方は増え続ける。今でさえ8割が病院で最期を迎える中で、このままでは行き場を失う人が必ず出てくる。その人たちは、どこで最期を迎えるべきなのか」。
その問いから生まれたのが、メディステップの原点となる構想でした。「患者様のご自宅を、まずは“病室”だと想像してほしい。そして、街の道路はすべて、その“病室をつなぐ廊下”なのだ」と。
それは、地域全体を一つの病院とみなし、医療スタッフが街を巡回することで、自宅にいながら誰もが質の高いケアを受けられるというものでした。 彼がそこまで熱を込めるのには、医師として経験した痛切な理由がありました。彼のクリニックに通う患者様が、誰にも看取られずに孤独死されてしまったのです。地域医療に誇りを持っていた彼にとって、この出来事はあまりにも大きな衝撃でした。「もっと他にできることがあるはずだ」という深い苦悩と後悔が、この事業の着想につながったのです。
半泣きで語る親友の熱意に、私自身の価値観も大きく揺さぶられました。「これは社会のためにやるべき、すごい仕事だ。ぜひ挑戦したい」。そう確信した瞬間こそ、メディステップの真の原点です。
当時、まったくの異業種にいた私にとって、ヘルスケアは未知の世界でした。それでも40代半ばでこの挑戦に踏み出せたのは、信頼する相棒が専門家である医師だったからに他なりません。
未経験の業界に飛び込まれ、どのような10年間でしたか。
中村(譲渡企業)
会社を設立して以来、看護師や理学療法士といったヘルスケア専門職の方々が持つ、職業観や使命感の素晴らしさに感動し続けてきました。例えば、仕事中か否かにかかわらず、街中で体調が優れない様子のお年寄りを見かけると、ごく自然に駆け寄って声をかける。その姿を目の当たりにするたび、心から「すごい」と感じてきました。
しかし、その素晴らしい仕事の価値が、必ずしも正当な報酬に結びついていない現実に、私は強い悔しさを感じてきました。「これほど価値のある仕事をしている方々こそ、もっと報われるべきだ」というその想いは、10年間まったく変わっていません。
社員の待遇を改善するには企業として利益を上げなければならず、それは決して簡単なことではありません。この理想と現実の狭間で、どうすれば会社を成長させられるかを模索し続けたのが、この10年です。「これが正解だ」という道筋が見えていたわけではなく、むしろ、業界の課題に直面する中で「自分たちで新しい仕組みを作らなければならない」という想いを、より一層強くしていったのです。
成長を支える資金繰りの課題
理想実現のために選んだ
次なる一手
M&Aを意識するようになったきっかけを教えてください。
中村(譲渡企業)
素晴らしい使命感を持つ社員たちが、心から幸せだと感じられる会社を作ること。それが私たちの理念です。ただ、その理念を実現するには、会社の規模という現実的な基盤が不可欠でした。例えば、5人の訪問看護ステーションと500人では、経営上の選択肢がまったく異なります。理想を叶えるための絶対条件は、とにかく会社を「大きくすること」だったのです。
その成長の過程で、私たちは必然的に資金繰りの課題に直面します。訪問看護事業は、先に人件費などの支出が発生し、その売上にあたる報酬が約2ヶ月遅れて国から入金されるビジネスモデルです。会社が成長して売上が増えるほど、この先行する支出と遅れて入る収入の差額、つまり運転資金の不足額が雪だるま式に膨らんでいくのです。
その課題は、年々厳しくなっていきました。創業当初は、共同創業者である医師の親友と200万円ずつ私財を出し合っていましたが、わずか3年で800万円の追加資金が必要となり、さすがに親友の顔にも緊張が走ります。そして5〜6年目、経理担当者から「次の資金調達ノルマは1,000万円以上です」と告げられたとき、個人で支える限界を感じました。そしてついに、「外部から資本を入れなければ、これ以上の成長はできない」と、決断する日が来たのです。
その課題に対し、最初からM&Aを検討されていたのでしょうか。
中村(譲渡企業)
いえ、当初はM&Aという発想はまったくなく、とにかく資金を集めることだけを考えていました。信託銀行や証券会社に相談し、ファンドや事業会社から出資を募る活動を始めたのが、創業6年目の頃です。幸いにも、私たちのビジョンに共感してくださる方々から少しずつ増資を受けることができ、会社は安定的に成長を続け、社員数も150名規模にまでなりました。
しかし、会社の成長は新たな責任も生み出しました。出資してくださった株主の方々は、当然ながら寄付をしているわけではありません。私と創業者の医師にとってはライフワークですが、会社としては株主の期待に応え、もう一段階上の成長を成し遂げる必要がありました。そのためには、もはや単なる資金調達では不十分でした。訪問看護の可能性を、異業種とのシナジーによってさらに広げ、ともに未来を創っていける強力なパートナーが必要だと痛感したのです。そうした中で、取引のあった証券会社からご紹介いただいたのが、今回のお相手であるユカリアでした。
ビジョンが共鳴した瞬間
未来を変える
パートナーとの出会い
ここからは、譲受会社であるユカリアの高橋様にもご参加いただきます。まずは、事業概要からお聞かせいただけますか。
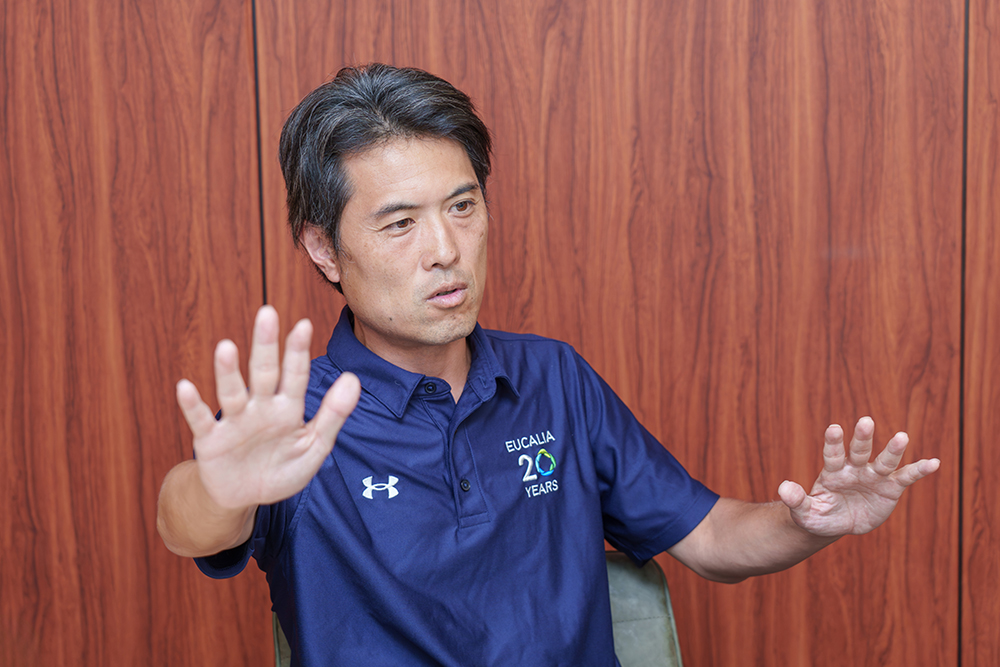
高橋(譲受企業)
私たちの事業の中核は、「医療経営総合支援事業」と「シニア関連事業」の2つです。医療経営総合支援事業では、病院の経営コンサルティングから資金繰りの支援、人事採用のサポートまで、病院経営全般を包括的に支援しています。一方、シニア関連事業では高齢者施設の運営に加え、施設への入居を検討されている方々のご相談に応じ、最適な施設探しをサポートしています。
我々の根幹には「医経分離」という考え方があります。医師をはじめとする医療従事者の方々は、高い専門性と倫理観を持って日々素晴らしい仕事に取り組まれています。しかし、その多大な貢献に見合った正当な対価が支払われていない現実があるのです。その原因には、医療のプロである医師が“必ずしも経営のプロではない”ことにもあります。例えば、日本ではMRIのような高額な医療機器の導入率の高さは世界トップクラスですが、稼働率は非常に低い。これは経営的な視点での投資判断が難しい現状の表れです。そこで、先生方には医療行為に専念していただき、経営の部分は我々のような、その道のプロフェッショナルが全面的にバックアップする。この「医経分離」を“二人三脚”の体制で実現し、医療現場の持続可能性を高めたいのです。
医経分離などの施策を通じて、私たちが実現を目指しているのが、ビジョンに掲げる「ヘルスケアの産業化」であり、「三方良し」という世界観です。まず医療機関の経営が健全化すれば、働く医療従事者のやりがいや報酬が向上し、その結果、最終的に患者様・利用者様へのサービス品質も高まる。この好循環を生み出し「医療・介護のあるべき姿を実現する」ことが私たちのミッションです。
貴社のM&Aに対する考え方をお聞かせください。
高橋(譲受企業)
我々にとってM&Aは、「仲間作り」そのものです。巨大で歴史あるヘルスケア産業を変えていくことは、ユカリア単独では到底できません。さまざまな専門性を持つ会社とパートナーシップを組み、皆で肩を組んで挑むのが我々の基本姿勢です。そのため、出資比率も1%から100%までと、形式にはこだわりません。
また、パートナーを決める上で最も重要な基準は、我々が掲げる「三方良し」の世界観や、“この世界を一緒に作りたい”という想いに共感いただけるかどうか。それがすべてです。
中村様は、どのようにパートナー選定を進め、ユカリア様とご一緒になることを決断されたのでしょうか。
中村(譲渡企業)
ユカリアと出会った当初、私はM&Aではなく、あくまで事業拡大のための資金調達が目的でした。しかし、その初対面で大きな衝撃を受けたのです。高橋様が語る世界観は、私たちが目指しているものとまったく同じでした。
さらに、ユカリアのビジョンに掲げられていた「ヘルスケアの産業化」という言葉には心が震えました。これは裏を返せば、「ヘルスケアはまだ産業として未熟だ」というようなもので、非常に挑戦的な言葉です。しかし、それを公言し、本気で業界を変えようと立ち向かっているチームがいることに驚きました。
ただ、M&Aとなると、正直なところ葛藤もありました。これまでの資金調達とはまったく感覚が違います。「会社を売る」という事実を前に、これまで支えてくれた仲間や従業員たちの、会社に対する想いや私への見方が変わってしまうのではないかと思ったのです。ユカリアとご一緒したいという気持ちと、仲間に対する責任の重さ。その両方を抱えながら、どう進むべきかを真剣に考え始めたのが、最初の面談の後でした。
高橋様は、メディステップ様とパートナーになることを決断されるまで、どのようなお考えを重ねられたのでしょうか。
高橋(譲受企業)
在宅介護マーケットへの参入は、我々にとって長年の悲願でした。「介護の悩みのない社会へ」というビジョンを掲げる上で、絶対に欠かせない部分だったからです。そうした中でメディステップと出会い、最初の面談で「この会社しかない」と直感しました。
決め手は複数ありますが、まず中村様のご説明のスタイルに驚きました。多くの会社が事業の「ファクト」を並べる中で、「こういうことをやりたい」というビジョンから語り始めたのです。実は、それは我々のスタイルとまったく同じだったのです。後から分かったことですが、お互いに業界の外から来た人間だからこそ、現状を俯瞰し、「こうあるべきだ」という未来から逆算して事業を考えていた。そこに根本的な思想の一致がありました。
高齢化が進み、病院や施設だけでは受け皿が限界に達する中で、在宅を含めた地域全体でどう支えていくかは喫緊の課題です。我々も病院・施設・在宅が分断されている現状に強い問題意識を持っていたため、仮想病院構想は、まさに我々が目指す世界観と同じものでした。
さらに、これまでのメディステップの歩みを拝見し、その成長の仕方が本当に美しいと感じました。新興企業にありがちな急拡大ではなく、一つひとつの事業を着実に固めてから次へ進む、という堅実なステップを10年間続けてこられた。その素晴らしい経営手腕も、大きな魅力でした。そのため単なる出資という希薄な関係ではなく、経営から深く関与し、「ともに未来を創る強固なパートナーシップを結びたい」と、その場で強く思ったのです。
「君たちは素人だ」
信頼する方の助言から始まった
アドバイザーとの出会い
M&Aのプロセスにおいて、レコフはどのような役割を果たしたのでしょうか。

中村(譲渡企業)
ユカリアと出会った後、株主の一人にM&Aの可能性を相談したところ、「今のメディステップの体制では、そんな判断はできない。君たちはM&Aの素人なのだから、専門家を入れた方がいい」と的確な助言をいただきました。その方が紹介してくださったのが、レコフだったのです。
ユカリア以外の候補企業をレコフに紹介いただき、最終的に5社ほどと面談をしましたが、レコフは本当に重要な役割を果たしてくれました。私の思考を整理し、決断の軸を明確にしてくれたのです。M&Aは初めての経験で本当に悩みましたが、レコフは「M&Aをすべきです」とは一度も言わず、ただひたすら「中村様にとって、本当に大事なことは何ですか」と問い続けてくれました。
その問いを通じて、私の中に残った軸は「仮想病院の実現にプラスになるか」と「お客様と従業員が幸せになれるか」の2つだけでした。そして、その軸が定まった上で、「他の大手企業は、中村様の構想を事業の中心には据えないでしょう。しかし、ユカリア様は在宅領域をまだ持っていません。これはメディステップ様にとって、絶好の機会です」と、非常に的確な分析と助言をくれたのです。
実務面でも、レコフがいなければもっと時間がかかったはずです。M&Aのプロセスで発生する膨大な量のやり取りをすべて一旦引き受けて交通整理をしてくれたおかげで、私たちは本質的な意思決定に集中でき、スピーディーに事を進められました。最終的に「M&Aをするならユカリアさんの一択だと思います」と率直な意見で背中を押していただき、迷いなく決断できました。
ユカリア様はM&Aのご経験も豊富です。そのお立場から、レコフの価値をどのように感じられましたか。
高橋(譲受企業)
レコフの存在は、お互いが良い決断をする上で極めて重要でした。M&Aは契約がゴールではなく、そこから一緒に事業を始めることが真の目的です。そのためには心から納得していただく、つまり腹落ちしてもらうことが何よりも重要でした。特に中村様にとっては初めての経験ですから、何かモヤモヤした気持ちを抱えたまま場の雰囲気に押されてサインし、後になって後悔されることだけは、絶対に避けなければなりませんでした。
しかし、我々がどれだけ歩み寄ろうとしても、交渉のテーブルではどうしても“相手方”になってしまいます。そのモヤモヤを解消する、本当の意味での相談相手にはなれないのです。ですから、客観的な専門家であるレコフのサポートは不可欠でした。そもそも、M&Aは売却される側の経営者にとって本当に大きな決断で、膨大な準備をお一人でこなすのは精神的にも大変です。その負担を支えるだけでも、大きな価値があります。
もう一つは、交渉の“緩衝材”としての役割です。交渉の過程ではどうしてもお互いの主張が出てきますが、当事者同士で直接ぶつかると後々の関係に遺恨を残しかねません。そのようなときに、レコフが間に入り、ときに“嫌われ役”を引き受けてくれたことで、私たちは常に良好な関係を保ったまま、本質的な議論に集中できました。 もし私が売り手の立場になったとしたら、間違いなく専門家にサポートを依頼します。なぜなら、自分と同じ想いで寄り添い、客観的な視点で選択肢を整理してくれるアドバイザーがいることが、“悔いを残さない意思決定”のために何よりも重要だからです。
仲間への想いを
貫いたM&A
加速する未来へ
成約が決まった後、特に力を入れたことは何でしたか。
中村(譲渡企業)
決断してから成約までの期間、私が何よりも心を砕いたのは、株主や従業員といった仲間たちへのケアでした。今回のM&Aは、私が引退するための事業承継ではなく、会社をさらに大きくするための成長戦略です。そのポジティブな意図が誤解なく伝わるよう、丁寧なコミュニケーションを重ねました。
グループインした途端に社員が辞め、売上が下がる。それだけは、双方にとって不幸ですから、絶対に避けなければなりませんでした。
そのために最も心を砕いたのが、社員への伝え方です。従業員がプレスリリースで初めて事実を知るような形は絶対に避けたいため、発表と同日にオンラインで全社員集会を開きました。そこにはユカリアの役員の方にもご参加いただき、「今回の決断が未来のための成長戦略なのだ」と、想いを込めて伝えたのです。
おかげさまで、誰一人欠けることなく、皆が前向きに受け入れてくれ、最高のスタートが切れたと感じています。
高橋(譲受企業)
我々が最初から中村様に惹かれたのは、そのお人柄に尽きます。M&Aの交渉というと、どうしても経済条件の話が中心になりがちですが、常に第一に口にされていたのは、これまで支えてくれた仲間や従業員のことでした。「この決断を、彼らにきちんと説明できるだろうか」「彼らは納得してくれるだろうか」と。利益や私欲ではなく、仲間を想うその姿勢に、この方とぜひご一緒させていただきたいと強く思いました。
今回のM&Aを経て、ご両社様はどのような未来を描いていらっしゃいますか。
中村(譲渡企業)
私たちのやるべきことは、ユカリアのグループに入っても何一つ変わりません。創業以来の夢である仮想病院を構築する、ただそれだけです。しかし、その実現に向けた環境は劇的に変わりました。これまでは外部の病院や高齢者施設と協業する必要がありましたが、これからは、その仲間がグループ内にいます。これはとてつもなく心強い。
そして何より、この提携によって、これまで不足していた人材と資金という強力なリソースを得ることができました。これだけ強力なサポートを得られるのですから、私の役割は明確です。事業の量とスピードを、これまで以上に底上げするべく力を注いでいきます。今は、未来に対するワクワクしかありません。
高橋(譲受企業)
我々は、現在のヘルスケア業界を、個人商店が立ち並ぶ“昭和の商店街”のようなものだと捉えています。それぞれが素晴らしいお店ですが、産業全体としては非効率な部分が多い。私たちが目指すのは、これを「ショッピングモール」のような総合プラットフォームに変えることです。そこに行けばワンストップであらゆるサービスが受けられ、相互連携によって利用者のメリットも生まれます。
今回の提携で、我々のプラットフォームに「在宅」という非常に重要な要素が加わりました。今後はメディステップを中核として、在宅マーケットの課題解決ができる総合的なサービスを構築していきたい。その世界観が実現できたとき、ようやく私たちのビジョンである「ヘルスケアの産業化」に近づけると考えています。重要なのはスピードです。速度を重視し、この変革を進めていきます。
もし今、会社の未来について悩んでいる経営者の方がいらっしゃれば、ぜひお伝えしたいことがあります。日本では、スタートアップの出口戦略としてIPO(新規株式公開)が美徳とされがちです。しかし、アメリカでは9割がM&Aを選択します。それは、M&Aを「自分たちの事業を、より大きな企業のプラットフォームに乗せてさらに成長させる」ための、ポジティブな成長戦略と捉える考え方が、社会に浸透しているからです。
M&Aは、決して事業の終わりや売却といったネガティブなものではありません。それは、会社の可能性を飛躍させるための、極めて有効な「戦略的オプションの一つ」なのです。
最初から選択肢を狭めることなく、「どこかに良いパートナーはいないか」と常にアンテナを張り続けることで、素晴らしい出会いが訪れ、会社の未来が大きく開けるはずだと考えています。


本件のアドバイザー
株式会社レコフ 代表取締役
小寺 智也
同志社大学経済学部卒業後、野村證券にて、リテール営業に従事したのち、「ホールセールのような大きな仕事を手掛けたい」「顧客に対し、より本質的な価値を届けたい」という想いから2012年にレコフへ入社。レコフでは入社以来一貫してヘルスケア業界を担当。
2021年10月 ディレクター就任
2023年4月 マネージングディレクター就任
2024年4月 執行役員就任
2024年12月 代表取締役就任
主な成約インタビュー
弊社でご成約されたM&A事例・実績をご紹介します。
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00