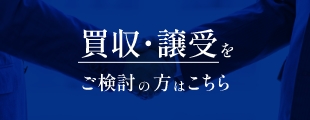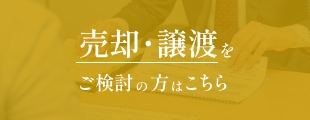平日9:00〜18:00

印刷業界のM&A動向
業界別M&A
印刷会社の事業は技術進歩による影響を大きく受けており、業界ではM&Aによる再編が進んでいます。
印刷会社のM&Aを行う際は、業界の特徴や市場規模を把握することが大切です。印刷会社が抱える課題も理解し、譲渡側は課題解決、譲受側はシナジー効果などを生み出せるM&Aを実現する必要があるでしょう。
印刷会社のM&Aを検討している方に向けて、印刷業界の市場規模・現状と課題、M&Aの動向とメリット・デメリットや取引事例などを解説します。
-
印刷業界とは?
-
印刷業界の市場規模と現状
-
印刷会社の主な課題
-
印刷会社におけるM&A動向
-
【印刷会社】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット
-
【印刷会社】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット
-
印刷会社のM&Aにおける主な取引手法
-
印刷会社における主なM&A事例2選
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
印刷業界とは?

印刷業界とは、印刷物の印刷・加工や製本などを事業とする印刷会社で構成される業界です。印刷会社は業態によって、印刷関連業務を行う「印刷業」、印刷物から本を作る「製本業」、印刷物の裁断や各種加工を行う「印刷物加工業」などの種類があります。
また、幅広い事業を行う印刷業は、業態がさらに出版印刷・商業印刷・事務用印刷・包装印刷の4つに分けられます。
| 出版印刷 | 出版社や新聞社から発注を受けて、書籍・雑誌・教科書・地図などの印刷物を作成する。 |
|---|---|
| 商業印刷 | 一般企業の事業で使用するチラシなどの宣伝用印刷や、カタログなどの業務用印刷を行う。 |
| 事務用印刷 | 企業の事務作業で使用する事務用伝票や事務用品、ビジネスフォームといった事務用印刷物を作成する。 |
| 包装印刷 | 包装紙・ダンボールなどの包装資材への印刷を行う。 |
業態によって製作物の種類や取引先が異なるため、印刷会社のM&Aでは自社・M&A先の会社がどのような業態であるかを確認することが重要です。
印刷業界の市場規模と現状

近年、印刷業界の市場規模は減少傾向にあります。
一般社団法人 日本印刷産業連合会が2024年に公表したデータによると、2010年以降の印刷産業の売上高は下記の通りに推移しています。
| 印刷産業の売上高 | |
| 2010年 | 約10兆3,835億円 |
| 2015年 | 約9兆1,468億円 |
| 2020年 | 約7兆6,305億円 |
| 2024年見込 | 約6兆3,914億円 |
(出典:一般社団法人 日本印刷産業連合会「印刷産業 Annually Report Vol.4 2025年」https://www.jfpi.or.jp/files/user/pdf/Annually_Report_Vol4.pdf )
2010年比にすると、2024年は市場規模が約6割となっていました。特に直近2年は7兆円を下回っており、市場規模の回復が難しい状況です。
小規模事業者が大半を占めている
出版業界の特徴として、従業員数が20人以下の小規模事業者が大半を占めていることが挙げられます。 特に従業員数10人未満の事業所は全体の約60%であり、対して従業員数が100人を超える事業所は3%未満という現況です。
(出典:一般社団法人 日本印刷産業連合会「印刷産業 Annually Report Vol.4 2025年」https://www.jfpi.or.jp/files/user/pdf/Annually_Report_Vol4.pdf )
印刷業界では大手の印刷会社が出版社・新聞社などから仕事を受注して、中規模・小規模事業者へと下請け発注するという構造になっています。 小規模事業者は事業資金が少ないため抜本的な設備投資が難しく、印刷業界全体における生産性向上の難しさに繋がっていると言えるでしょう。
出版印刷市場が減少傾向にある
出版印刷市場が減少傾向にある大きな要因が、近年のデジタル化による電子媒体の普及です。書籍・雑誌などのデジタル化が進むことで印刷会社に発注される仕事が少なくなり、印刷物の出荷額減少に影響しています。
また、近年はインターネット通販の形式で印刷物の受注生産を行う事業者が登場しています。大手印刷会社の下請けを行っている印刷会社は、印刷事業の価格競争に巻き込まれることにも警戒が必要です。
印刷会社の主な課題

印刷業界の現状は厳しいだけでなく、印刷会社自体にもいくつかの課題が存在します。印刷会社のM&Aを行う際は自社の課題を把握し、その解決ができるM&A手法を検討することが大切です。
印刷会社の主な課題を3つ挙げ、それぞれ経営にどのような影響を与えているかを解説します。
相場変動リスクへの対応
印刷事業では印刷用紙をはじめ、インク・フィルム・溶剤といった原材料を使用します。これらの原材料はいずれも原油価格相場の影響を受ける資材であり、原油価格が高騰すると原材料費も上昇することがリスクです。
また、原材料費の大部分を占める印刷用紙は、製紙メーカーの生産量による影響も受けます。 製紙業界は大資本による寡占化が進んでおり、小規模事業者が多い印刷会社は相対的に交渉力が弱くなります。<?原材料費を抑えられず、販売価格にも転嫁しにくい場合は、経営が逼迫するおそれがあるでしょう。
周辺環境への配慮
小規模な印刷会社の多くは、大手からの受注によって事業が成り立つ下請けであり、納期に間に合わせるため夜間も印刷工場を稼働させます。結果として、工場周辺地域との間で騒音問題を抱えるケースが少なくありません。
また、印刷工場ではインクや溶剤などの化学薬品を大量に使用することにより、土壌汚染のリスクもあります。印刷工場の閉鎖・売却の際は土壌汚染調査が実施されるため、普段から廃液・廃棄物などを適切に管理することが重要です。
紙媒体以外への事業展開
印刷業界は紙媒体での出版・印刷が主要事業であるものの、近年はデジタル化などの影響から業界全体の市場規模が減少しています。
業界で生き残る方法として、紙媒体以外への事業展開を模索する印刷会社が増えている傾向です。 ただし、小規模な印刷会社では新たな事業展開を目指すための資金力が不足しています。紙媒体以外への事業展開を実現するためにどのような手法を取るかが、印刷会社にとっての課題となります。
印刷会社におけるM&A動向

印刷会社は、紙媒体の印刷サービス提供だけでは事業成長が困難となっており、紙媒体以外への事業展開も視野に入れる必要があります。資金力確保や業務提携の手法として、M&Aを実施する印刷会社は多い状況です。
以下では、印刷会社における主なM&A動向を3つご紹介します。
既存事業の強化を目的としたM&A
主に印刷会社同士のM&Aで、紙媒体の印刷サービスなど既存事業の強化を目的としたM&Aが実施されています。大手印刷会社が小規模な印刷会社を買収して技術集約をする、顧客基盤や販路などの共有を行うなど、既存事業の強化が可能です。 特に小規模な印刷会社は特定分野の強みを持っていることが多く、既存事業の強化を図りたい大手印刷会社にとって魅力的な買収先となります。
事業領域の拡大を目的としたM&A
紙媒体以外の事業展開を目指す印刷会社の多くは、事業領域の拡大を目的としたM&Aを実行します。大手印刷会社が小規模な印刷会社を買収するケースや、異業種企業とのM&Aが代表的です。
特に電子媒体領域の拡大を目指す印刷会社では、デジタルマーケティングやIT関連企業とのM&Aが目立っています。
また、日本国外の市場開拓を目的として、アジア圏などの海外企業とのM&Aを行うケースも少なくありません。事業拠点を海外に設置することで、国内における原材料の価格競争を回避し、人件費削減も期待できます。
事業の多角化を目的とした異業種M&A
異業種企業とのM&Aでは、事業の多角化を目的としているケースもあります。 異業種M&Aで特にニーズが高いのは、パッケージ印刷や特殊印刷の高い技術を持つ印刷会社です。買い手となる譲受企業はパッケージメーカーや高機能素材メーカーが多く、印刷会社とのM&Aによってパッケージ印刷の内製化や、新製品の開発促進などを目指します。
事業の多角化を目指す異業種企業とのM&Aは、売り手の印刷会社にとっても印刷技術に新たなニーズが生まれるなどのメリットがあります。
【印刷会社】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット

印刷会社のM&Aを実行する際は、自社にどのようなメリットがあるかを理解する必要があります。 特に売り手側となる譲渡企業は、自社が抱えている課題をM&Aで解決できるか確認しましょう。
印刷会社のM&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリットを3つご紹介します。
譲受企業の資本力を活用できる
M&Aは基本的に相互に協力し合う関係になることが多く、譲渡側の印刷会社は譲受企業の資本力を活用できます。自社のみでは難しい紙媒体以外への事業展開も、譲受企業の資本力を背景として達成しやすくなります。
また、大手印刷会社の傘下に入ると印刷用原材料の大規模仕入れができるようになり、スケールメリットによって原材料費を抑えることも可能です。大手印刷会社が抱える高単価の案件を優先受注できるようにもなり、経営の安定化が図れるでしょう。
従業員の雇用を維持したままリタイアできる
M&Aを実行した場合、基本的に譲渡企業が雇用している従業員は譲受企業へと引き継がれます。譲渡企業の経営者は従業員の雇用を維持したままリタイアできます。
仮にM&Aではなく事業を廃業する場合、従業員を解雇しなければなりません。解雇に伴う退職金の支払いなどが発生し、少ない手元資金をさらに圧迫する可能性があります。
しかし、M&Aであれば従業員の雇用を維持できるため、退職金の支払いも不要です。
また、印刷会社で働く従業員は高い技術力やノウハウを持っています。印刷会社を買収する譲受企業にとって必要な人材であり、今よりも良い待遇で働ける可能性もあるでしょう。
経営者利益(譲渡益)を確保できる
印刷会社の売却をした経営者は、経営者利益(譲渡益)を確保できます。経営者利益は会社や事業の売却によって得られる対価です。
M&Aで一般的に行われる株式譲渡では、経営者利益は経営者が自由に使用できます。リタイア後の老後資金に充てたり、新しい事業を展開するための準備資金としたりといった使い方も可能です。
なお、M&Aスキームで事業譲渡を選択した場合は、会社が譲渡益を獲得することになります。事業譲渡の譲渡益は、経営者が自由に使えるわけではない点に注意してください。
個人保証や借入金を譲受企業に引き継げる
印刷会社の経営では、事務所・工場の建設や操業資金として金融機関からの借入金があるケースが珍しくありません。 特に小規模な印刷会社の経営者は、借入金の申し込みをする際に個人保証を選択していることが多いでしょう。個人保証は会社の信用力を補完できるものの、返済が滞ったときには経営者の生活に多大な影響が出る、リスクの高い方法です。
M&Aを行えば、個人保証や借入金を譲受企業に引き継ぐことができます。経営者は個人保証や借入金の支払いに悩まされなくなり、経営者利益を活用した新しいビジネスや老後の生活を実現できるでしょう。
【印刷会社】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット

印刷会社のM&Aでは、譲受側は印刷会社が保有していた経営資源を獲得できる、企業の価値・ブランドが向上するといったメリットを得られます。
譲受側の企業は、得られるメリットが自社の目的達成に繋がるかを考えた上で、印刷会社のM&Aを進めると良いでしょう。
あらゆる経営資源をまとめて獲得できる
譲受企業は、従業員・技術・取引先・工場など、譲渡側が保有していたあらゆる経営資源をまとめて獲得できます。
それぞれの経営資源の獲得には、下記のようなメリットがあります。
| 従業員 | M&Aで獲得した従業員は教育が基本的に必要なく、すばやく事業をスタートできます。 |
|---|---|
| 技術 | 自社で1から開発する場合と比べて、技術の獲得は時間・費用を大幅に削減できます。 |
| 取引先 | 販路拡大や売上向上に繋がります。 |
| 工場 | 印刷事業に必要な建物や機械・設備を取得でき、設備投資のコストを抑えられます。 |
獲得できる経営資源の内容や質は譲渡企業によって異なります。交渉段階でしっかりとM&A先のチェックやデューデリジェンスを行うことが重要です。
企業の価値・ブランドが向上する
M&Aで印刷会社を傘下に収めることにより、グループ規模が大きくなって事業規模も拡大し、企業の価値やブランドが向上します。事業進出や新商品開発、新規顧客の獲得などが実現し、企業のさらなる成長が見込める点がメリットです。
特に印刷会社同士のM&Aでは、電子媒体などの新しい分野への進出が事業成長に必要であるため、企業の価値・ブランド向上が重要となります。
自社とは異なる強みを持つ印刷会社を買収や提携することにより、従来とは異なる事業展開ができるようになって、印刷業界で生き残る可能性を高められるでしょう。
印刷会社のM&Aにおける主な取引手法

M&Aには株式譲渡や事業譲渡など、様々なスキーム(枠組み・手法)があります。 選択するM&Aスキームによっては、M&Aで得られるメリットや譲渡・譲受後の関係性が異なるため、選択するスキームを事前に考えておきましょう。
以下では、印刷会社のM&Aで用いられる主な取引手法を3つ挙げて、それぞれの概要と特徴を解説します。
株式譲渡
株式譲渡は、譲渡企業の株主が保有している株式を譲受企業に渡し、引き換えに対価を受け取るスキームです。特に譲受企業が譲渡企業を子会社化するときに用いる手法であり、M&Aで最も多く利用されています。
譲渡企業の株式の50%以上が譲受企業へと渡されると、譲渡企業は譲受企業の子会社になります。株式譲渡の完了後は譲渡企業が株主総会や取締役会を開催し、続いて譲受企業内で新役員や代表取締役の選任を行う流れが一般的です。
株式譲渡では、譲渡企業の債務や契約などの権利義務は包括的に承継されます。
事業譲渡
事業譲渡は、譲渡企業が保有する一部の事業や資産を譲受企業へと渡して、対価を受け取るスキームです。譲渡企業が不採算事業を切り離したり、譲受企業にとって必要な事業・資産を買収したりすることを目的として行われます。
事業譲渡は事業や資産の移動をするだけの取引であり、M&A後に譲渡企業と譲受企業が子会社・親会社の関係性にはならない点が特徴です。
また、譲渡・譲受する事業や資産は個別に選択できるため、交渉や手続きの手間が大きくなる傾向があります。株式譲渡とは違って権利義務の包括的な承継はされないため、債務や契約などをどうするかも話し合わなければなりません。
資本提携
資本提携は、出資企業が出資先企業の株式を取得して資本を提供し、協力関係を築くという手法です。2社以上が提携して、1社のみでは実現できない目標の達成を目指すことを目的としています。
資本提携では、一般的に出資企業が取得する株式の比率は全株式の1/3を超えないことが特徴です。株式比率が1/3未満であれば、株主総会の特別決議で単独での否決ができなくなり、出資先企業の経営に大きな影響を与えるおそれがありません。
印刷会社における主なM&A事例2選

印刷会社におけるM&Aを成功させるためには、M&Aの事例を参考にすることも有効です。
事例では譲渡企業・譲受企業のそれぞれの業態や、M&Aの目的とスキームが何であるかを確認して、自社のケースでの参考にしましょう。
印刷会社における2つのM&A事例を解説します。
大日本印刷株式会社×株式会社ハコスコ
大日本印刷株式会社は2023年7月、株式会社ハコスコの株式の51%を取得してグループ会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社ハコスコ |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 大日本印刷株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
大日本印刷株式会社は、独自の印刷・情報技術を強みとして多彩な分野に進出し、XRコミュニケーション事業も手がける大手印刷会社です。
一方の株式会社ハコスコは、メタバースやXR事業、ブレインテック事業などを展開するスタートアップ企業です。
大日本印刷株式会社は、株式会社ハコスコの柔軟な事業開発力やネットワーク力をグループ会社として活用することにより、新しい価値の創出を目指しています。
株式会社日本創発グループ×飯島製本株式会社
株式会社日本創発グループは2023年9月、連結子会社の飯島製本株式会社と株式交換を実施して完全子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 飯島製本株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社日本創発グループ |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式交換(完全子会社化) |
株式会社日本創発グループは、印刷事業やデジタルコンテンツなどのクリエイティブサービスを提供する大手印刷会社です。
一方の飯島製本株式会社は、中京圏をはじめ関東圏・関西圏にも工場を保有する大手製本企業です。
株式会社日本創発グループは飯島製本株式会社を完全子会社化することで、シナジー効果の最大化を図っています。
まとめ
印刷業界は市場規模が減少しており、小規模事業者が多いことによるさまざまな経営難のリスクがあります。既存事業の強化や事業領域の拡大・多角化を目的としたM&Aが活発に行われている状況です。
印刷会社のM&Aは、M&A先やM&Aスキームなど決めることがいくつもあります。M&Aを成功させるためには、印刷会社のM&Aに詳しい専門家に支援を求めましょう。
印刷会社のM&Aや異業種M&Aを検討している方は、株式会社レコフにご相談ください。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00