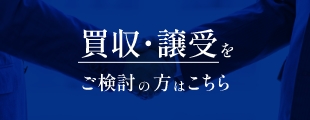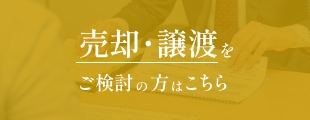平日9:00〜18:00

新聞業界のM&A動向
業界別M&A
新聞業界は、かつて世間の主要な情報源として絶大な影響力を誇っていました。しかし現在では、インターネットやSNSの普及によって紙媒体の需要は急速に縮小しており、業界全体が大きな変革を迫られる状況となっています。
多くの新聞社にとってM&Aは、収益構造の見直しや新たな事業展開による業界再編だけでなく、生き残りをかけた戦略的手段でもあるでしょう。
そこで今回は、新聞業界の基本的な構造や現状・課題から、具体的なM&Aの動向や事例、成功のポイントまでを分かりやすく解説します。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
新聞業界とは?

新聞業界とは、「新聞」と呼ばれる定期刊行物を通じて、国内外の出来事やニュースを収集・編集・印刷・発行し、多くの読者に提供する事業を営む業界<?です。社会の動きをいち早く伝える情報源として、古くから大きな影響力を持ち続けてきました。
新聞と一口に言っても、その内容や目的、発行対象に応じていくつかの種類に分類されます。主に「一般紙」「スポーツ紙」「専門紙」の3種類があり、それぞれで取り扱う情報の範囲や読者層が異なります。ここからは、各紙の特徴や分類について詳しく解説します。
新聞の種類(1)一般紙
一般紙とは、政治・経済・社会・国際・文化・スポーツなど、幅広い分野のニュースを網羅的に扱う新聞です。一般家庭や企業など、最も多くの読者に読まれているタイプの新聞で、日々の生活に関わる基本的な情報を提供することを目的としています。
また、一般紙はさらに「全国紙」と「地方紙」に分けられます。
全国紙は日本全国に向けて発行される新聞を指し、全国的な話題や国際ニュースなどを中心に取り扱います。一方、地方紙は特定の地域に根差した新聞で、地域のニュースや生活情報、地元企業の動向など、読者の生活圏に密着した内容が主です。
新聞の種類(2)スポーツ紙
スポーツ紙は、プロ野球やサッカー、大相撲などのスポーツに関する情報を中心に扱う新聞です。その他、芸能ニュースや娯楽情報、話題の人物や出来事に関する特集記事なども多く掲載されており、「エンタメ要素の強さ」や「速報性・独自取材に重きを置いた紙面構成」が特徴です。
読者層は、一般紙とは違ってスポーツファンや芸能情報を積極的に求める人々が中心で、駅売店やコンビニなどで手軽に購入できる形式が多く見られます。
新聞の種類(3)専門紙
専門紙(または業界紙)は、特定の業界や分野に特化したニュースや解説を提供する新聞です。対象となる業界は多岐にわたり、経済・金融・建設・医療・農業・ITなど、読者が業界関係者や専門家に限定される傾向があります。
専門紙で掲載される内容は、業界の動向や新製品情報、法改正、業界内の人事異動など、極めて専門性の高いもので、一般紙では得られない深い情報が得られる点が大きな強みです。読者の多くは法人や団体、個人事業主などであり、ビジネス上の意思決定や情報収集に役立てられています。
新聞業界の主な収益構造

新聞業界の主な収益源は、大きく分けて「販売収益」と「広告収益」の2つに分類されます。
●販売収益
販売収益とは、新聞そのものの販売によって得られる収益を指します。具体的には、定期購読料や駅・コンビニなどでの単体販売による売上がこれに該当します。読者から直接得られる収益であり、継続的な購読者を確保することが安定した経営につながります。 特に近年は、デジタル版の有料購読にも力を入れる新聞社が増えており、紙媒体とデジタル両面での販売戦略が重要となっています。
●広告収益
広告収益は、新聞紙面や新聞社の運営するウェブメディアなどに他社広告を掲載することによって得られる収益です。企業や自治体などの広告主が、商品・サービスの宣伝や告知のために新聞に広告を出稿する際に支払う掲載料が、新聞社にとっての収益となります。 広告収益は販売収益よりも変動が大きく、景気の動向や発行部数に左右されやすいのが特徴です。
新聞業界の現状
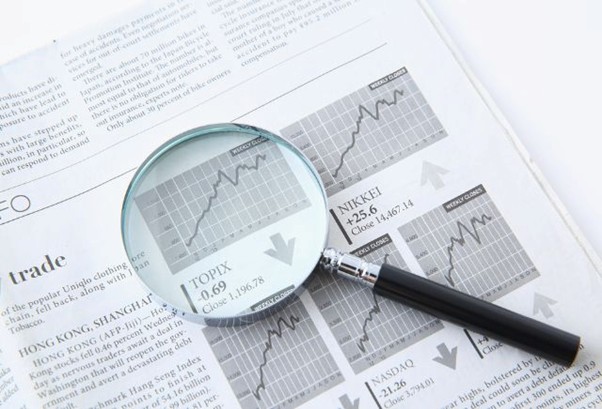
新聞業界では「読者からの購読料」と「広告主からの掲載料」という2本柱で収益を確保していますが、いずれも時代の変化にともなう影響を大きく受けています。
下記は、一般社団法人 日本新聞協会が公表した「新聞社における総売上高の推移(2019年度~2023年度)」です。
| 社数 | 総売上高 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 91 | 16,524億円 |
| 2020年 | 89 | 14,827億円 |
| 2021年 | 86 | 14,695億円 |
| 2022年 | 86 | 13,265億円 |
| 2023年 | 85 | 13,087億円 |
(出典:一般社団法人 日本新聞協会「新聞社の総売上高の推移」https://www.pressnet.or.jp/data/finance/finance01.php )
新聞社の総売上高は、2019年度から2023年度にかけて減少し続けています。これは主に「購読者数の減少」と「広告収入の落ち込み」によるものであり、新聞業界全体に構造的な変革を迫る動きが顕著になっています。
ここからは、総売上高の減少の背景にある主な要因を4つの視点から整理します。
新規顧客獲得の難化
新聞業界では、購読者数の減少が長年にわたって続いており、新規顧客の獲得が大きな課題となっています。その主な要因として挙げられるのが、インターネットの普及です。 便利なスマホの所有やネット環境が当たり前となりつつある近年、ニュースサイトやSNSなどで手軽に情報を得られる環境が整ったことで、紙媒体の新聞を定期的に購読する層は非常に減少しています。
実際に毎日新聞が公表した読者データによると、全国紙を購読する人の50%以上が40代以上であり、特に単身世帯や30代以下の若年層において顕著な新聞離れが見られます。こうした状況により、新聞業界では新規顧客の獲得が難しくなっているのが現状です。
(出典:毎日新聞「読者データ」https://macs.mainichi.co.jp/ad/profile.html )
発行部数の減少
日本新聞協会の公開データによると、新聞の発行部数は2000年の約5,371万部から2024年には約2,662万部まで減少し、およそ53%に縮小しています。
また、1世帯あたりの購読部数は2023年に初めて0.5部を下回る0.49部にまで落ち込み、新聞を定期的に購読する世帯がますます少なくなっていることを示しています。
特にスポーツ紙の減少率は深刻で、2000年の約631万部から2024年には約168万部へ激減し、およそ3割にまで落ち込んでいる状況です。こうした発行部数の減少も、インターネットの普及が大きな要因と考えられています。
(出典:一般社団法人 日本新聞協会「新聞の発行部数と世帯数の推移」https://www.pressnet.or.jp/data/circulation/circulation01.php )
広告収入の減少
新聞の購読者数と発行部数の減少により、業界全体における広告収入も大幅に減少しています。2004年には広告収入が約7,550億円あったのに対し、2023年には約2,420億円まで落ち込み、およそ20年で約70%の減少となりました。
広告収入の減少には、インターネット広告の急速な台頭が大きく影響しています。企業の広告予算がデジタル媒体へとシフトしている近年、紙媒体の広告価値は相対的に低下しており、新聞広告が従来のような主要な収益源としての役割を十分に果たせなくなっているのが実情です。
(出典:一般社団法人 日本新聞協会「新聞社の総売上高の推移」https://www.pressnet.or.jp/data/finance/finance01.php )
業界内における人員削減の進行
新聞業界は新規顧客獲得の難化や発行部数の減少、さらにそれに伴う広告収入の減少という複合的な要因により、深刻な経営環境に直面していると言っても過言ではありません。
このような苦境を背景に、各大手新聞社では100名から200名以上の規模で希望退職者募集を実施するなど、大規模な人員削減が加速しています。
しかし、人員削減によってサービスの質の低下を招くおそれもあり、結果として新聞業界の縮小を加速させる要因になりかねません。
新聞業界の主な課題

新聞業界は、新規顧客獲得の難化や発行部数・広告収入の減少に直面しており、苦境から抜け出すための対策が急務となっています。特に注目されている課題が、「新たな収益構造の確立」と「デジタル新聞の強化・拡大」です。
(1)新たな収益構造の確立
従来の紙媒体中心の収益モデルが限界に達していることから、多様な収益源の模索が求められています。 具体的には、デジタル広告の拡充、有料会員サービスの導入やイベント開催、さらにはコンテンツの多角化など、紙面に依存しないビジネスモデルの確立が課題です。これにより、収益の安定化と持続可能な経営基盤の構築を目指しています。
(2)デジタル新聞の強化・拡大
スマートフォンやタブレット端末を活用したデジタル配信の普及により、リアルタイムでの情報提供や多様なメディアとの連携が可能となりました。
しかし、無料で閲覧できる情報が多い中、有料デジタル新聞の価値をいかに高め、読者の支持を得るかが大きな課題です。特に、若年層の新聞離れを食い止めるうえで重要視されています。
新聞業界のM&A動向

新聞業界は経営環境の変化に対応するため、M&Aを通じた業界再編や経営強化の動きが加速しています。特に、デジタル化への対応や事業基盤の多様化を目的としたM&Aが増えており、業界の競争力再構築と収益構造の転換が模索されています。
ここからは、新聞業界でよく実施される主なM&Aの類型を紹介します。
新たな経営資源の獲得を目的としたM&A
新聞各社では、従来の紙媒体中心のビジネスモデルから脱却し、デジタル領域での収益確保が急務とされています。特に、若年層の新聞離れが進む中で、スマートフォンやニュースアプリを通じた情報収集が主流となっており、デジタル分野での競争力が企業の将来を左右する時代です。
しかし、新聞社にとってデジタル事業は専門性が高く、自前での展開には限界があります。そこで、ITやWebメディア運営に強みを持つ企業とのM&Aによって、ノウハウや顧客基盤を獲得し、デジタル化への対応を加速させる動きが広がっています。
新たな経営資源の獲得を目的とした戦略的提携により、新しいサービスの創出やデジタル市場へのスムーズな参入が図られています。
業界再編を目的としたM&A
新聞発行部数の減少や広告収益の低下により、業界全体が構造的な縮小を余儀なくされる中、業界内での再編の必要性が高まっています。
少子高齢化による読者層の先細りを背景に、従来の紙媒体中心の収益モデルを維持するのはますます困難になってきており、持続可能な経営を目指す上での選択肢として、M&Aが注目されています。
こうした状況の中、中堅・地方紙を中心とした連携・統合の動きに加え、大手新聞社を含めた広範な業界再編が進行する可能性も指摘されています。今後は、新聞業界全体が一体となって再構築を進める動きがさらに顕著になると見られています。
新聞業界の主なM&A事例3選
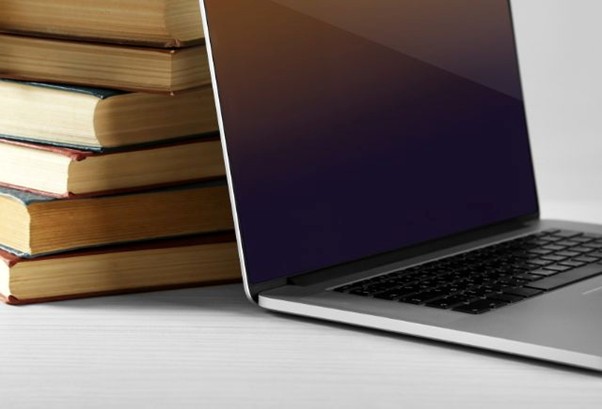
新聞業界のM&Aを成功させるためには、他社の取り組みや実例を参考にするのも非常に有効です。実際の事例を知ることで、どのような手法があるのかといった点や自社の目的に応じたM&Aの方向性を具体的にイメージしやすくなるでしょう。
ここからは、新聞業界における主なM&A事例を3つ紹介します。
株式会社朝日新聞社×株式会社ディーイーシー・マネージメントオフィス
株式会社朝日新聞社は、2019年8月に株式会社ディーイーシー・マネージメントオフィスの全株式を取得し、同社をグループ会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社ディーイーシー・マネージメントオフィス |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社朝日新聞社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式取得(子会社化) |
朝日新聞社は、全国紙『朝日新聞』の発行を中心に、報道・出版・メディア事業を展開する大手新聞社です。近年はデジタル領域の強化にも注力しています。
一方、ディーイーシー・マネージメントオフィスは、販促支援やプロモーション施策の企画・運営を手がける企業で、特にマーケティング領域におけるノウハウと実績を有しています。
朝日新聞社は、広告・販促に強みをもつディーイーシー・マネージメントオフィスを傘下に迎えることで、グループ全体のマーケティング支援体制を強化するとともに、新聞広告とデジタル施策を融合させた新たな収益モデルの構築を図っています。
株式会社朝日新聞社×グループ企業5社
2025年10月、株式会社朝日新聞社は株式会社ディーイーシー・マネージメントオフィスを含むグループ傘下の5社を吸収合併し、2社に再編しました。
| 譲渡(売り手)側 |
|
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社朝日新聞社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 吸収合併 |
朝日新聞社は、全国紙の発行に加え、広告やデジタルメディアなど多様なメディア関連事業を展開する大手新聞社です。
吸収合併の対象となった5社は、広告、オリコミ(折込チラシ)、地域密着型の販促、海外メディア展開など、それぞれ異なる領域で事業を展開していたグループ会社です。
今回の吸収合併により、朝日新聞社はこれらの事業を「株式会社4X(フォーエックス)」と「アルファサード株式会社」の2社に統合しました。 グループ全体の経営効率を高めると同時に、急速に変化する市場環境に柔軟に対応できる体制づくりを推進しています。
株式会社日本経済新聞社×ディールストリートアジア
株式会社日本経済新聞社は、2019年4月にシンガポールのスタートアップメディア「DealStreetAsia(ディールストリートアジア)」の株式を過半を取得し、買収しました。
| 譲渡(売り手)側 | DealStreetAsia |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社日本経済新聞社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
日本経済新聞社は、経済・ビジネス分野に特化した報道を強みとする国内有数の経済新聞社で、グローバル展開にも力を入れています。
一方、DealStreetAsiaは東南アジアのスタートアップ、ベンチャー投資、M&A情報に特化したオンラインメディアで、現地の独自ネットワークと速報性の高い報道力を有しています。
本M&Aにより、日経新聞社は東南アジアにおける情報収集体制を強化するとともに、国際的な報道ネットワークを拡充させ、海外ビジネス読者層へのリーチ拡大を図っています。
新聞業界のM&Aを成功させるポイント

新聞業界におけるM&Aを成功させるには、単なる資本提携にとどまらず、事業の持続性や成長戦略を見据えた取り組みが求められます。特に重要なのが、「市場動向を見極めたタイミング選定」と「M&Aの専門家への相談によるリスク軽減」です。
最後に、新聞業界におけるM&Aの成功に欠かせない上記2点のポイントについて詳しく説明します。
市場動向を見極めたタイミング選定の重要性
新聞業界は現在、読者離れや広告収入の減少により、再編の波が加速しています。そのため、適切なタイミングでM&Aを実施することが成功を大きく左右するカギとなります。
買い手側にとっては、先んじて優良企業を確保することで競争優位に立てる一方、売り手側も市場が過度に冷え込む前に交渉を進めることが望ましいと言えます。再編が進んだ後では、買い手が限定され、希望条件でのM&Aが難しくなる恐れがあります。
自社の事情だけにとらわれず、業界全体の動きや広告市場の変化、デジタル分野の成長性などを総合的に判断し、客観的かつ戦略的に最適なタイミングを見極めることが成功への第一歩です。
M&Aの専門家への相談によるリスク軽減
新聞業界のM&Aでは、事業の継続性や雇用維持、地域社会への影響など、様々なステークホルダーが関与します。こうした背景から、M&Aの各プロセスには高い専門性と慎重な判断が求められます。
そのため、仲介会社やファイナンシャルアドバイザー、弁護士、会計士といった専門家の支援を受けることが極めて重要です。これにより、リスクの洗い出しや契約内容の精査、最適なスキームの設計など、各ステップでの判断ミスを防ぎやすくなります。
特にM&A経験が乏しい中小新聞社にとっては、新聞業界におけるサポート実績を有した専門家の知見を活用することが、M&A成功への近道となるでしょう。
まとめ
新聞業界は、購読者数や広告収入の減少により厳しい経営環境が続いています。こうした中、経営改善や事業継続を目的としたM&Aの動きが活発化しており、新たな技術や経営資源の獲得、業界再編を見据えた案件が増加しています。
M&Aを成功させるには、市場動向を正確に捉えたタイミング選定と、専門家によるサポートが不可欠です。新聞業界でのM&Aを検討されている方は、ぜひM&A助言会社の株式会社レコフにご相談ください。豊富な実績と専門知識を活かし、最適な提案とサポートを提供いたします。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00