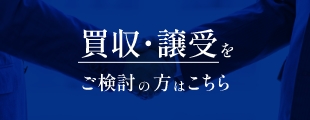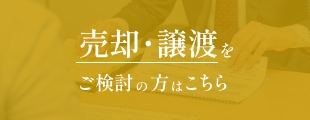平日9:00〜18:00

住宅設備機器業界のM&A動向
業界別M&A
住宅設備機器業界は住宅に欠かせない住宅設備機器を扱っており、住宅建設に伴う一定の需要が見込まれる業界です。一方で業界には課題も多く、事業継続が難しい住宅設備機器業者も多いと考えられます。
住宅設備機器業界で経営にかかわる課題の解決や事業拡大を目指す方は、M&Aを検討するとよいでしょう。
今回は住宅設備機器業界の市場規模やM&A動向を説明した上で、M&Aの立場別のメリットとM&Aの事例、住宅設備機器業界のM&Aを成功させるポイントを解説します。
-
住宅設備機器業界とは?
-
住宅設備機器業界の市場規模|現状から見える課題
-
住宅設備機器業界のM&A動向
-
【住宅設備機器業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット
-
【住宅設備機器業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット
-
住宅設備機器業界における主なM&A事例3選
-
住宅設備機器業界のM&Aを成功させるポイント
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
住宅設備機器業界とは?

住宅設備機器業界とは、住宅に導入される住宅設備機器の製造・開発や販売に携わる「住宅設備機器業者」で構成される業界です。代表的なメーカーとしては「LIXIL」「TOTO」「Panasonic」が挙げられます。
そもそも住宅設備機器とは、下記のような設備を指します。
| 住宅設備機器の種類 | 主な例 |
|---|---|
| 水まわり |
|
| 建具 |
|
| 空調設備 |
|
| 照明器具 |
|
| 創エネ設備 |
|
いずれも生活を便利・快適にするための設備であり、現代の住宅では住宅設備機器の導入が欠かせません。
住宅設備機器業者は大きく分けて、メーカー・卸会社・販売会社の3つがあります。
メーカーは各種住宅設備機器を製造し、卸会社に納品します。卸会社は住宅設備機器を販売会社に届け、販売会社が顧客(建設会社・一般消費者)に販売するという業界構造です。
住宅設備機器業界と建材卸売業界の違い
住宅設備機器業界と混同されがちな業界に「建材卸売業界」があります。住宅設備機器業界と建材卸売業界はどちらも住宅設備を扱うものの、厳密には異なる業界です。
建材卸売業界とは、メーカーから建築資材や住宅設備機器を仕入れて、建設会社などの顧客に販売する「建材卸売業」の会社で構成される業界です。取り扱う商品には住宅設備の他に住宅建材や住宅サッシなどがあります。
一方、住宅設備機器業界で取り扱う商品は住宅設備機器のみです。住宅の主要な材料である建材は、大手住宅設備機器業者を除いて基本的に取り扱いません。
また、建設卸売業界は住宅設備機器メーカー・木材建材メーカーのどちらからも仕入れを行うものの、建材や住宅設備機器を製造するメーカーを業界内には含みません。あくまでもメーカーから業者への流通を担う「卸売」の業界となっています。
住宅設備機器業界の市場規模|現状から見える課題

矢野経済研究所が公表するデータによると、住宅設備機器業界の市場規模は下記のように推移しています。
| 2022年度 | 1兆9,430億円 |
|---|---|
| 2023年度 | 1兆9,868億円 |
| 2024年度 | 2兆433億円 |
| 2025年度(予測) | 2兆553億円 |
(出典:市場調査とマーケティングの矢野経済研究所「住宅設備機器市場に関する調査を実施(2025年)」
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3884)
2020年からのコロナ禍により、2021年度の住宅設備機器業界の市場規模は減少していました。その後はコロナ禍からの経済回復と建設需要の増加により、市場規模も回復基調が見られています。
しかし、住宅設備機器の市場規模は現状では堅調であるものの、将来的にはいくつかの課題もある点に注意してください。
以下では住宅設備機器業界の現状と課題を、3つのポイントに分けて解説します。
新築住宅の需要は減少傾向にある
住宅設備機器は住宅建築やリフォーム時に多く使われるため、住宅設備機器業界は住宅業界の影響を受けやすい業界です。
野村総合研究所のデータによると、2023年度における新設住宅着工戸数は約82万戸でした。
しかし、近年は工事原価高騰の影響を受けて新設住宅着工戸数が減少しています。将来的には人口減少の影響もあり、新設住宅着工戸数はさらなる減少が見込まれている状況です。
(出典:NRI 野村総合研究所「2040年度の新設住宅着工戸数は61万戸に減少」
https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/20250612_1.html)
新築住宅の需要が減少すると住宅設備機器の需要も減少し、住宅設備機器業界の市場規模が縮小に転じる可能性も大きいと言えます。
リフォーム市場はわずかに成長している
新設住宅着工戸数が減少する一方で、リフォーム市場はわずかに成長しています。
野村総合研究所のデータでは、2023年における広義のリフォーム市場規模は約8.3兆円であり、2018年度から継続して成長傾向が見られます。将来的な予測も緩やかな上昇ペースとなる見込みです。
(出典:NRI 野村総合研究所「2040年度の新設住宅着工戸数は61万戸に減少」
https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/20250612_1.html)
しかし、近年は工事原価高騰やそれに伴うメーカー値上げが増えているほか、建築基準法の改正による影響もあり、今後の住宅業界の動きは見えにくくなっています。
住宅設備機器業界に属する会社は経営を安定化させるために、住宅業界の動向に依存しにくいビジネスモデルの確立が重要となるでしょう。
経済的課題が市場拡大を阻んでいる
リフォーム市場はわずかながらに成長しているものの、住宅設備機器の需要が大きく伸びる可能性は低いと言えます。住宅業界の需要には、日本を取り巻く経済的課題も影響しているためです。
特に関連性が深い経済的課題としては、建築資材の価格高騰が挙げられます。新型コロナウイルス感染症による物流停滞とウッドショックの表面化から始まり、ロシア・ウクライナ紛争の勃発でさらなる建築資材の不足と輸入価格の高騰が起こりました。
資材価格の高騰を販売価格に転嫁できればよいものの、近年は消費者も物価高に苦しんでおり、高額なリフォームや新築を検討する顧客自体が減少傾向にあります。価格転嫁による値上げは、さらなる顧客離れを招くリスクが高いでしょう。
また、資材価格の高騰をすぐに販売価格へと転嫁するのは簡単ではなく、実際に価格に反映させるまでにはタイムラグが発生します。しばらくの期間は価格高騰分を自社で背負わなければならず、大きな資金負担を強いられる住宅設備機器メーカーも多い状況です。
住宅設備機器業界のM&A動向

住宅設備機器業界では、ビジネス課題の解決を目指してM&Aを選択する企業・メーカーが増えています。ビジネス課題に悩まされている住宅設備機器業者の方は、M&Aでどのような課題が解決できるかを把握しておきましょう。
住宅設備機器業界のM&Aでよく見られる3つのパターンを説明します。
事業承継を目的としたM&A
経営者の高齢化による後継者問題は主に中小企業で問題となっており、住宅設備機器業界も例外ではありません。後継者問題の解決のために、事業承継を目的としたM&Aがよく行われています。
M&Aで自社の事業や株式を売却すれば、住宅設備機器事業を売却先の経営者に引き継いでもらうことが可能です。自社の従業員や顧客もそのまま引き継がれるため、従業員の雇用や顧客へのサービス提供を維持できます。
事業拡大を目的とした同業M&A
住宅設備機器業界では事業拡大を目的とした、住宅設備機器業者同士の同業M&Aも目立っています。同業M&Aは両社が互いの強みやサービスを活用できるようになり、住宅設備機器業界での存在感を高められる方法です。
特に同業M&Aでは、大手メーカー・卸による中小企業の買収がよく行われています。経営が厳しい中小の住宅設備機器業者は、大手傘下に加わることで経営の安定化につながります。
シナジー効果の創出を目的とした隣接業種のM&A
隣接業種とのM&Aも、住宅設備機器業界でよく見られるM&Aのパターンです。住宅設備機器業界の隣接業種には住宅業界・建材業界などがあり、事業領域が異なる2社の提携によって新商品開発などのシナジー効果を期待できます。
隣接業種のM&Aは、住宅設備に関するサプライチェーンの構築・拡大を図れる利点もあります。商品原材料を安く仕入れたり、流通コストを抑えたりができるようになり、競合との差別化や価格競争への余力確保を実現できるでしょう。
【住宅設備機器業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット

住宅設備機器業界のM&Aを進める際は、M&Aの実施によって自社にどのようなメリットがあるかを知ることが大切です。
M&Aの立場は売り手の譲渡側と、買い手の譲受側があり、それぞれの立場で得られるメリットは異なります。
以下では住宅設備機器業界のM&Aによる譲渡側のメリットを3つ紹介します。
後継者問題を解決できる
M&Aで会社を譲渡することにより、外部の人材を自社の後継者にすることができます。後継者の育成や指名ができていない住宅設備機器業者にとって、M&Aは後継者問題を解決させられる方法です。
M&Aで後継者問題を解決すれば、後継者の不足によって自社の倒産・廃業に追い込まれることがなくなります。自身がこれまで築き上げてきたビジネスを消滅させずに済むだけでなく、新しい経営者のもとで一層発展することも期待できるでしょう。
従業員の雇用を継続できる
経営難や後継者問題といった課題を解決できずに会社を廃業すると、従業員を解雇しなければなりません。従業員の解雇時には退職金の支払いが発生するだけでなく、経営者には解雇を通達することの心理的な負担もかかります。
M&Aで住宅設備機器会社や事業を譲渡すれば、譲受側の会社のもとで従業員の雇用を継続させられます。解雇に伴う問題を防げるだけでなく、従業員がより良い環境で働ける可能性があることもメリットです。
売却益を獲得できる
M&Aで会社や事業を売却すると売却益を獲得できます。売却益は売却対象となる株式や事業の対価であり、創業者や経営者(株主)が自由に使えるお金です。
また、会社を売却する場合は負債が譲受側に引き継がれます。経営者の個人保証や担保といった債務の負担から解放されることがメリットです。
売却益の獲得と債務からの解放により、経営者のリタイアや新規事業の展開を実現できます。
大手傘下に入ることで経営の安定化を図ることができる
M&Aの譲受側が大手企業の場合、譲渡側の住宅設備機器業者は大手傘下に入ることで経営の安定化を図れるメリットがあります。大手が保有する多額の資本で経営基盤が強化されて、大手のブランド力も使えるようになるでしょう。
また、多くの大手企業は仕入れルートや販路といった流通部分に力を入れており、傘下に入れば事業コストの削減や顧客拡大も期待できます。住宅設備機器業者が抱える課題を一度に解決したい方は、大手企業とのM&Aを検討すると良いでしょう。
【住宅設備機器業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット

M&Aの譲受側は、達成したい目標をM&Aで実現できることが重要です。たとえば事業拡大や新規顧客の獲得など、具体的な目標につながるメリットがあるかを確認しましょう。
住宅設備機器業界のM&Aによる譲受側のメリットを3つ挙げて、どのような目標の達成が見込まれるかを説明します。
新たな顧客層と営業拠点を開拓できる
M&Aによって譲受側が引き継ぐ資産には、譲渡側の顧客や営業拠点が含まれます。既存顧客とは異なる新たな顧客層や、未進出エリアの営業拠点を開拓できる点がメリットです。
中小の住宅設備機器業者は多くが地域密着型であり、特定の地域・地方でのサービス提供に強みを持っています。自社が事業展開できていないエリアを得意とする住宅設備機器業者とM&Aを行えば、商圏の拡大による事業成長に繋げることが可能となります。
取り扱い商材を増やせる
M&Aの譲受側には、自社の取り扱い商材を増やせるメリットもあります。中小の住宅設備機器業者は特定の住宅設備機器に強みを持っていることが多く、提案できるサービス領域と顧客数の増加によって売上向上を目指せるでしょう。
また、住宅設備機器の販売会社や住宅会社は、住宅を購入する方に同一メーカーの設備を顧客に提案することが多い傾向があります。取り扱い商材を増やせばセットで購入してもらえる商品数も増えて、売上を高められる点もメリットです。
事業拡大によるスケールメリットを得られる
住宅設備機器業者の買収を進めることで、譲受側は事業拡大によるスケールメリットを得られます。原材料費の削減や商品運搬コストの低下、商品ラインナップの充実による顧客満足度の向上・知名度向上などが、住宅設備機器業界における主なスケールメリットです。
住宅設備機器は生活の便利さ・快適さに結び付く商品であり、商品のライフサイクルも数年~十数年と比較的長いため、顧客満足度や知名度の向上は特に大切な要素です。顧客に良いブランドイメージを持ってもらえたほうが商品を選ばれやすくなり、売上向上につながります。
住宅設備機器業界における主なM&A事例3選

住宅設備機器業界のM&Aを成功させるためには、M&A事例を参考にすることも有効です。
以下では住宅設備機器業界のM&A事例を3つ紹介します。事例で説明する2社の事業内容や採用されたスキームを参考に、自社でどのようにM&Aを行うべきかを検討してみましょう。
株式会社NEXTAGE GROUP×レカム株式会社
レカム株式会社は2023年9月、連結子会社の株式会社産電テクノの全株式を株式会社NEXTAGE GROUPに譲渡しました。同時に、株式会社産電テクノの親会社である株式会社産電の事業についても、株式会社NEXTAGE GROUPの子会社に譲渡しています。
| 譲渡(売り手)側 | レカム株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社NEXTAGE GROUP |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡+事業譲渡 |
レカム株式会社は情報通信機器関連事業や住宅設備機器事業などを展開する会社です。2018年12月に太陽光発電等の住宅設備機器事業を行う株式会社産電・産電テクノの株式を取得したものの、コロナ禍により不採算事業となっていました。
株式会社NEXTAGE GROUPも住宅設備機器事業をはじめ、住宅全般領域で事業を展開する会社です。2社は株式会社産電と産電テクノの株式譲渡・事業譲渡を行ったほうが事業拡大につながると判断し、本M&Aを実施しています。
ブルケン関東×日新電機
ブルケン関東は2023年2月、日新電機の電設資材販売事業を事業譲渡により取得しました。
| 譲渡(売り手)側 | 日新電機 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | ブルケン関東 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 事業譲渡 |
ブルケン関東はJKホールディングスの連結子会社で、内装・外装建材などの木質建材販売事業を中核事業としています。
一方の日新電機は、電力・環境システム事業や装備部品ソリューション事業を手がける会社です。
ブルケン関東は本M&Aによって事業領域を広げ、グループ全体の企業価値向上も目指しています。
ダイキアクシス×アルミ工房萩尾
ダイキアクシスは2021年10月、アルミ工房萩尾の全株式を取得して子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | アルミ工房萩尾 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | ダイキアクシス |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
ダイキアクシスは水まわりの設備を中心に、住宅設備機器の製造・施工・販売などを行う会社です。
一方のアルミ工房萩尾は、住宅サッシやエクステリア建材の施工・販売を事業領域としています。
ダイキアクシスは本M&Aによって住宅サッシ・エクステリア建材を顧客に提案できるようになり、シナジー効果も見込めるとしています。
住宅設備機器業界のM&Aを成功させるポイント

最後に、住宅設備機器業界のM&Aを成功させるポイントを2つ紹介します。
●M&Aの目的を明確にする
自社の経営状況や事業のビジョンなどを整理・分析した上で、M&Aの目的を明確にしましょう。
M&Aの目的が明確化されていれば、M&AスキームやM&A先の選定を「目的達成ができるか」という基準で判断できます。
●M&Aに詳しい専門家に相談する
M&AにはM&A先の候補選定や交渉、各種契約書の作成など、いくつもの手続きがあります。M&Aの手順を漏れなく行うために、M&Aに詳しい専門家に相談しましょう。
M&Aに詳しい専門家にはM&Aアドバイザーや税理士、公的機関・金融機関などの種類があります。中でもM&AアドバイザーはM&Aの事前相談からM&A先との交渉や書類作成、クロージングまでを一貫してサポートしてくれるおすすめの専門家です。
まとめ
住宅設備機器業界は住宅業界と関係が深く、新築住宅の需要減少や資材価格の高騰といった影響を受けやすい課題があります。後継者問題を抱える会社も多く、事業承継や事業拡大を目的としたM&A、隣接業種とのM&Aなどが盛んです。
住宅設備機器業界のM&Aは、紹介したように譲渡側・譲受側の双方に多くのメリットがあります。自社の目的に合うメリットがある場合は、まずはM&A助言会社に相談して、どのようにM&Aを進めれば良いかを検討しましょう。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00