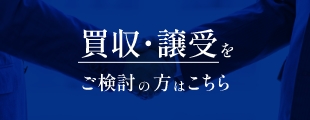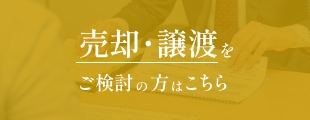平日9:00〜18:00

ドラッグストア業界のM&A動向
業界別M&A
近年、様々な業界でM&Aが実施されています。M&Aには多くのメリットがあり、ドラッグストア業界においても経営課題の改善や事業継承などを目的としてM&Aを検討する企業が増えています。
M&Aを成功させるには、まずドラッグストア業界の市場動向や課題を深く理解することが重要です。業界内でどのようなM&Aが行われているのか把握した上で、メリットが大きいM&Aを目指しましょう。
今回は、ドラッグストア業界のM&A動向と立場別のメリット・デメリットを詳しく解説します。
-
ドラッグストア業界の定義・特色
-
ドラッグストア業界の市場規模
-
ドラッグストア業界の現況と今後の課題
-
ドラッグストア業界のM&A動向
-
【調剤薬局業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット・デメリット
-
【調剤薬局業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット・デメリット
-
ドラッグストア業界のM&Aを成功させるためのポイント
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
ドラッグストア業界の定義・特色

ドラッグストア業界とは、医薬品や化粧品、家庭用品・日用雑貨・食品などを幅広く取り扱う小売店です。風邪薬や頭痛薬などの医薬品はもちろん、洗剤やトイレットペーパー、卵や牛乳など多岐にわたる商品を販売しています。
取り扱う商品は店舗によって異なるものの、多様な商品を販売することから人々の生活にはなくてはならない存在となっています。さらに、調剤薬局の併設や健康相談の実施など、地域医療にも深く関わる業界です。
ここからは、ドラッグストア業界の特色を詳しく解説します。
政策による影響を受けやすい
ドラッグストア業界は、法改正の影響を受けやすいことが特徴です。 過去にドラッグストア業界が影響を受けた主な法改正は、下記の通りです。
| 薬事法改正 | コンビニエンスストアでの処方箋のいらない一般用医薬品販売が解禁(2009年) |
|---|---|
| 薬事法改正 | インターネットでの第一類医薬品・第二類医薬品の販売が解禁(2013年) |
| セルフメディケーション税制導入 | 特定の医薬品購入額に対して所得控除制度を適用(2017年) |
法改正により、医薬品の需要が拡大することもあれば利益確保が難しくなることもあります。
立地や商圏に依存しやすい
ドラッグストアは人々の暮らしに密接に関わる業界であるため、立地や商圏に依存しやすいことも特徴です。
ドラッグストアの売上には、出店する立地や商圏が大きく影響します。地域の人口や住人の年齢層、活動時間帯などからドラッグストアの需要を把握し、季節や天候に左右されずに集客できるエリアに出店することが重要です。
調剤薬局を併設するドラッグストアの場合は、周辺に医療機関があるエリアを狙う必要があります。
規模によるメリットを得られやすい
ドラッグストア業界は、店舗数が多くて販売額が多い企業ほど仕入れ面のメリットを得やすくなります。
大規模企業は、規模が小さい企業に比べて仕入れの条件や価格の交渉が有利です。安く仕入れた商品を各店舗で販売することは、利益の向上につながります。
また、プライベート商品の開発に使える資金が潤沢であるほど、自社の強みを生かした商品の提供が実現しやすくなります。プライベート商品の開発と提供は、競合との差別化にも効果的です。
ドラッグストア業界の市場規模
ドラッグストア業界の市場規模は、年々大きくなっています。
ドラッグストアの店舗数の推移は、下記の通りです。
| 店舗数 | 前年比 | |
| 2022年 | 18,429店 | 4.6%増 |
| 2023年 | 17,622店 | 3.7%増 |
| 2024年 | 19,664店 | 3.3%増 |
(出典:経済産業省「2022年 小売業販売を振り返る」
https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/pdf/h2amini161j.pdf)
(出典:経済産業省「2023年 小売業販売を振り返る」
https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/pdf/h2amini166j.pdf)
(出典:経済産業省「2024年 小売業販売を振り返る」
https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/pdf/h2amini170j.pdf)
店舗数は2014年以降増加を続けており、今後もさらなる拡大が予想されます。
市場規模が拡大している主な理由は、下記の通りです。
- 消費者の健康意識の変化
- 高齢化の進行
- セルフメディケーション税制の導入
- 地域との密着性の向上
健康志向の消費者や高齢者が増えたことで、医薬品やヘルスケア商品を豊富に取り扱うドラッグストアへの需要が高まっています。
近年では、調剤薬局併設型のドラッグストアも増えています。セルフメディケーション税制の促進により、医師の処方箋がなくても購入できるOCT医薬品への注目度が高まったことも理由の1つです。
また、利用しやすい立地にあり必要な商品をコンビニより安く買えることも、市場規模の拡大に大きく影響していると言えます。ドラッグストアは医薬品や日用品の売上がメインだったものの、近年は食品の売上が最も大きくなっています。
ドラッグストア業界の現況と今後の課題

ドラッグストア業界は、市場拡大が続く一方で課題を抱えているのが実態です。ドラッグストア業界の経営を成功させるには、課題を明確にして必要な対策を講じなければなりません。
以下では、ドラッグストア業界の現状と今後の課題を4つ解説します。
薬剤師をはじめとした人材不足の深刻化
人材不足の深刻化は、ドラッグストア業界における大きな課題です。薬剤師をはじめとした従業員の不足により、サービスの品質維持や新規出店が難しくなるケースも増えています。
少子高齢化による働き手の減少に加えて、医薬品を販売する企業の増加や薬学部が6年制になり薬剤師国家資格の取得難易度が上がったことも、人材不足の理由の1つです。
慢性的な人材不足は、生産効率や企業の競争力の低下に繋がります。
大手の寡占化
ドラッグストア業界では、大手企業による寡占化が進んでいます。
最大手企業の売上高は1兆円を超え、上位10社の売上高は市場シェアの約7割を占めていることが特徴です。上位10社が占める市場シェアは年々増加傾向にあり、小規模企業との売上格差が広がっています。
大手企業は積極的に新規出店を進める傾向にあり、小規模企業は生き残るために競合との差別化や経営統合などの対策が必要です。
出店余地の減少による店舗拡大の難化
出店余地の減少により、ドラッグストアの店舗拡大は難化しています。
各ドラッグストアが積極的な新規出店を繰り返した結果、出店余地の減少が目立つようになりました。特に都心部では既に多くのドラッグストアが存在しており、新規出店をできるエリアはごく僅かです。
少子高齢化により人口減少が続く中、ドラッグストアの店舗は過剰傾向にあります。ドラッグストア業界では、市場の頭打ちに備えて競合他社との差別化に取り組む必要があります。
諸問題の解決や事業拡大を目指したM&Aの活性化
M&Aは、ドラッグストア業界が抱える問題や課題を解決する手段の1つです。薬剤師をはじめとした人材不足や出店余地の減少による店舗拡大の難化など、課題解決のためにM&Aを選択する企業が増えています。
ドラッグストア業界のM&Aでは、同業同士だけでなく他業種間での資本提携や子会社化も多く見られます。事業拡大を目指す企業にとっても大きなメリットと言えるでしょう。
ドラッグストア業界のM&A動向

ドラッグストア業界におけるM&Aの目的は多岐にわたります。今後の経営戦略を立てるために、まずはドラッグストア業界ではどのような目的でM&Aが行われているのか知っておくことが大切です。
ここからは、ドラッグストア業界のM&A動向を詳しく解説します。
事業承継や大手の傘下入りを目的としたM&A
事業継承や大手の傘下入りを目的とするM&Aは、小規模なドラッグストアに多く見られます。売り手側は、後継者不足や人材不足などの課題を抱えているケースがほとんどです。
大手の傘下に入ることで、売り手側は事業継承の不安を解消し、人材確保により経営の安定化を目指せます。M&Aが成功すれば、廃業せずに済むため顧客のライフスタイルや従業員の労働環境にマイナスな影響を与えずに済みます。
また、 経営資源が豊富な大手の傘下に入ることで、新規販売エリアへの新規出店も可能です。
商圏の開拓・拡大を目的としたM&A
ドラッグストア業界では、商圏の開拓や拡大を目的としたM&Aも多く見られます。商圏の開拓や拡大は、企業成長に欠かせない取り組みです。
主に、ドミナント戦略を積極的に行う大手企業が買い手となります。ドミナント戦略とは、 同じエリア内に複数の店舗を構える経営戦略です。経営の優位性をアピールしたり顧客の囲い込みを効率良く進めたりできます。
大手企業の未進出エリアにある小中規模のドラッグストアは、企業成長を目指す大手企業とのM&Aに有利です。
大手同士の業務提携を目的としたM&A
業界シェアの確保や業界順位の上昇を狙う目的で、M&Aを実施するケースも珍しくありません。
大手同士の業務提携は、同業他社より優位な立場を目指せる点が大きな魅力です。優位な立場になることで、ドミナント戦略も進めやすくなります。
また、ブランド力がある大手企業と手を組むことで、それぞれのブランド力を生かして経営にプラスの影響を与えられます。 株価が上がったり優秀な人材の確保につながったりすることは、双方にとって大きなメリットです。
シナジー効果を目的とした異業種M&A
ドラッグストア業界では、シナジー効果を目的とした異業種M&Aも活発です。
EC事業やIT事業に特化した企業とのM&Aにより、顧客の拡大や販売システムの構築を目指すドラッグストアも多く見られます。すでにシステムが構築されている企業を買収すれば、コストを抑えて生産性を上げることが可能です。
コンビニやスーパーなどドラッグストア業界への進出を考えている異業種企業も多く見られます。
【調剤薬局業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット・デメリット

ここからは、ドラッグストア業界のM&Aによる譲渡(売り手)側のメリット・デメリットを解説します。 株式や事業の譲渡を検討している経営者は、どのような影響が考えられるか把握しておきましょう。
メリット
M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリットは、下記の通りです。
- 大手傘下に入ることで経営が安定する
- 人材不足を解消できる
- 後継者問題を解消できる
- 個人保証を解消できる
経営資源が豊富な大手企業の傘下に入ることで、経営の安定化や事業の効率化を目指せます。大手企業の技術やノウハウを吸収できることはもちろん、ブランド力を得られる点も大きなメリットです。
また、今後の経営を任せられる人材がいない場合は、M&Aによって事業を引き継ぐことができます。M&Aにより個人保証は譲受(買い手)側に引き継がれるため、負債への不安や負担を解消できます。
ただし、個人保証の引継ぎには、譲受(買い手)側との話し合いと解除手続きが必要です。自動的に個人保証が引き継がれるわけではないため注意しましょう。
デメリット
M&Aによる「譲渡(売り手)側」のデメリットは、下記の通りです。
- 労働条件が悪化する可能性がある
- 経営上の権限や裁量が制限される可能性がある
- 競業避止義務により事業展開を制限される場合がある
株式譲渡の場合は、譲渡(売り手)側の従業員の雇用関係は守られます。事業譲渡の場合も雇用契約を継続する前提でM&Aが実施されますが、契約は新たに締結されるため給与や勤務地などが変更となる可能性もあるでしょう。 さらに、譲渡(売り手)側の経営者や役員は、競業避止義務により事業展開を制限される場合があります。競業避止義務違反にならないように、期間や範囲などをしっかり協議しておきましょう。
【調剤薬局業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット・デメリット
ドラッグストア業界のM&Aは、譲渡(売り手)側だけでなく譲受(買い手)側にもメリット・デメリットがあります。M&Aを成功させるためには、考えられる影響を把握しておくことが大切です。
以下では、ドラッグストア業界のM&Aによる譲受(買い手)側のメリット・デメリットを解説します。
メリット
M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリットは、下記の通りです。
- ドミナント戦略を展開できる
- 優れた人材やノウハウを獲得できる
- 企業の弱点を強化できる
- 新事業への参入リスクを軽減できる
ドミナント戦略の展開には、狙っているエリア内での店舗の確保が必要不可欠です。既存店舗を活用して系列店舗を増やすことができれば、効率良くドミナント戦略を進められます。
経験やスキルがある薬剤師をはじめとする人材を獲得できるため、サービスの品質向上も期待できます。開発やEC事業など自社の弱点を補える企業と手を組むことで、売上アップや競合との差別化も目指せるでしょう。
新規事業への参入は立ち上げリスクが伴いますが、異業種とのM&Aによりノウハウや人材を確保できれば様々なリスクを軽減できます。
デメリット
M&Aによる「譲受(買い手)側」のデメリットは、下記の通りです。
- 簿外債務を引き継ぐリスクがある
- 期待していた人材が離職・流出する可能性がある
- 経営統合が成功するとは限らない
譲受(買い手)側は、M&Aにより譲渡(売り手)側が抱える債務を引き継ぐことになります。貸借対照表に記載されていない簿外債務が存在する企業を買収した場合、想定外の不利益を被るリスクがあります。
また、労働条件や経営方針に不満が生じた場合、期待していた人材の離職や流出につながりやすくなるため注意が必要です。M&Aによるデメリットが大きくなれば、経営統合が上手くいかず大損失につながる可能性もあるでしょう。
専門家の力を借りて簿外債務がないかどうかしっかり調べたり、従業員が安心して働けるように説明会を開いたり、事前に対策を講じておく必要があります。
ドラッグストア業界のM&Aを成功させるためのポイント
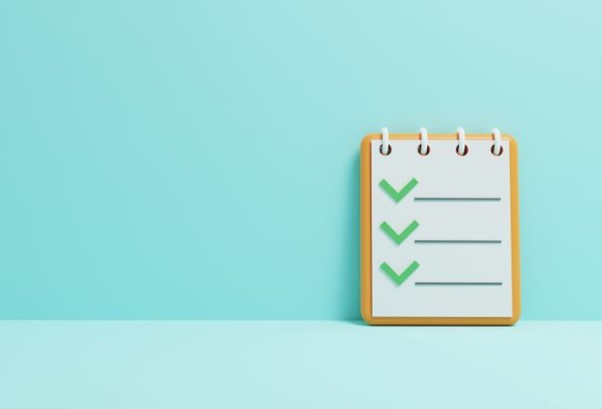
ドラッグストア業界のM&Aを成功させるためには、相手企業の情報をしっかりリサーチしておくことがポイントです。
下記は、M&Aを成功させるためにおさえておくべきポイントとなります。
●立地や地域の優位性
ドラッグストア業界のM&Aは、立地や地域の優位性が成功の鍵を握ります。「集客を見込める立地にある」「地域住民から必要とされている」などの優位性があるほど、好条件でのM&Aが実現しやすくなるでしょう。
●人材の豊富さ
人材不足の解消やサービスの品質向上を目指す上で、人材の豊富さは重要なポイントです。特に薬剤師や登録販売者などの有資格者が多く在籍する企業は、M&Aにおいて高く評価されます。有資格者が多いほど、好条件でのM&Aを実現しやすくなります。
●サービスの充実性
ドラッグストア業界のM&Aでは、サービスの充実性にも注目しましょう。競合との差別化につながる専門性やサービスがある企業は、付加価値をアピールしやすくなります。調剤薬局の併設や店舗アプリの導入など、顧客満足度向上につながる取り組みを行う企業ほどM&Aに有利です。
自社にとってプラスの影響が大きいM&Aを実施するには、3つのポイントを考慮した上で、将来を見据えつつ適切なM&A先を選定する必要があります。
ドラッグストア業界のM&Aは、M&Aに関する知識だけでなく業界内の動向にも詳しい専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。最適な企業とのM&Aを実現するために、知識と実績のあるM&Aアドバイザーに相談しましょう。
まとめ
ドラッグストア業界は、政策による影響を受けやすく立地や商圏に依存しやすいという特色があります。ドラッグストア業界の市場規模は年々拡大している一方で、人材不足や出店余地の減少などの課題を抱えています。
ドラッグストア業界のM&Aは、大手の傘下入りや事業拡大など企業によって目的はさまざまです。譲渡(売り手)側・譲受(買い手)側のそれぞれにメリット・デメリットがあるため、考えられる影響をしっかり理解しておくことが大切です。
ドラッグストア業界のM&Aを検討している方は、まずはM&Aアドバイザーに相談してみましょう。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00