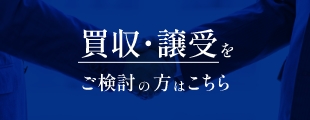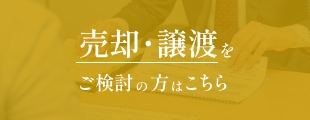平日9:00〜18:00

家具業界のM&A動向
業界別M&A
家具業界は大きな市場規模があるものの、価格帯の二極化や住宅業界の動向による影響など、さまざまな課題も存在する業界です。業界が抱える課題に対応する手段として、家具業界では同業種や異業種によるM&Aが活発化しています。
今回は家具業界の市場規模と現状を説明した上で、家具業界のM&Aや立場別のメリットなどを解説します。おすすめのM&A相談先も解説しますので、家具業界のM&Aを検討している方はぜひ参考にしてください。
-
家具業界とは?
-
家具業界の市場規模
-
家具業界の現状|現状から見える今後の課題も
-
家具業界のM&A動向
-
家具業界のM&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット
-
【家具業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット
-
家具業界における主なM&A事例3選
-
家具業界のM&A検討時におすすめの相談先
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
家具業界とは?

家具業界とは、日常生活やオフィス業務で使われる家具を製造・販売する事業者の業界です。家具は机・椅子・ソファ・キャビネット・照明器具など数多くの種類があり、用途や価格帯によっても分類できます。
家具業界はオーダーメイドの高級家具を手がけるメーカーから、リーズナブルな量産型家具を製造するメーカーまで、複数のメーカーが存在していることが特徴です。 また、オフィス家具の開発・製造を行うメーカーや、顧客ニーズに応じたインテリアの空間デザインを提案する企業も家具業界に含まれます。
このように企業ごとにビジネスモデルは大きく異なるものの、メーカーの規模によってある程度共通する傾向はあります。大手メーカーは家具の開発から販売、空間デザインまで幅広く行い、高い利益率につなげることが可能です。
一方で中小企業は家具の販売のみを行うのが基本であるものの、デザイン面やサービス面などで独自の強みを持つ傾向にあります。
家具業界の市場規模
矢野経済研究所による調査では、家具業界全体の市場規模は安定した状態であることが分かっています。
下記の表は、直近5年間における家庭用・オフィス用家具のメーカー出荷金額ベースでの市場規模です。
| 年度 | 市場規模 |
|---|---|
| 2019年 | 10,507億円 |
| 2020年 | 10,911億円 |
| 2021年 | 10,920億円 |
| 2022年 | 11,330億円 |
| 2023年(予測) | 11,330億円 |
(出典:市場調査とマーケティングの矢野経済研究所「家庭用・オフィス用家具市場に関する調査を実施(2023年)」https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3353 )
直近5年間の市場規模は継続して微増しており、家具の需要が高い状態にあることが分かります。コロナ禍での自宅時間の増加により家庭用家具を見直す動きが作られたり、アフターコロナに対応したオフィス用家具の需要が高まったりしたことが主な要因でしょう。
なお、家庭用家具の市場規模は平均して6,000億~7,000億円程度であり、家具業界では家庭用家具の占める売上が大きいと言えます。
家具業界の現状|現状から見える今後の課題も

家具業界は市場規模が微増傾向にある一方で、業界全体の状況は変化を続けており、さまざまな課題も存在します。家具業界に関わる企業は、家具業界の現状と課題を把握しておくとよいでしょう。
ここからは、家具業界の現状と、現状から見える今後の課題を3つ解説します。
高級家具・低価格家具の二極化が進んでいる
家具業界では、職人が無垢材などから製作する高級家具と、工場で大量生産される低価格家具の二極化が進んでいます。特に近年は個人消費の落ち込みが目立っており、低価格家具ブランドを展開する大手メーカーが家具業界を牽引している状況です。
高級家具・低価格家具の二極化によって、どちらの価格帯でもないミドルプライスの家具メーカーや、大きな知名度を持たない家具店は苦境に陥っています。製品の魅力を高める付加価値や、顧客のニーズに対応できるサービスを提供できないメーカーは市場から淘汰される可能性があるでしょう。
住宅業界の動向に影響を受けやすい
家具業界では家庭用家具の売上規模が大きく、家庭用家具の売上に関係する住宅業界の動向に影響を受けやすくなっています。
野村総合研究所のデータによると、新設住宅着工戸数は近年減少傾向にあり、将来的にさらなる減少が見込まれている状況です。新設住宅着工戸数が減少すると家具需要も減少するため、家具業界にも影響が出る可能性は大きいと考えられます。
また、リフォーム市場規模はわずかながらも成長を続けるとされているものの、近年は工事原価高騰による値上げが増えているほか、建築基準法の改正による影響もあります。
今後の住宅業界の動きは予測しにくいため、家具メーカーは住宅業界の動向に依存しにくいビジネスモデルの確立も重要となるでしょう。
(出典:NRI 野村総合研究所「2040年度の新設住宅着工戸数は58万戸に減少、2043年の空き家率は約25%まで上昇する見通し」https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2024/cc/0613_1 )
生活雑貨・ホームオフィス家具需要が拡大している
ECサイトの登場で消費者の購買行動は多様化しており、住宅業界では生活雑貨の需要が拡大しています。キッチン用品・インテリア用品・バス用品といった生活雑貨を取り揃えて、家具需要以外の顧客ニーズも満たすビジネスモデルが大手家具メーカーを中心に増えています。
また、リモートワークの普及によるホームオフィス家具需要の拡大も注目すべきポイントです。家庭用家具・インテリアと調和するホームオフィス家具の需要は将来的にさらに高まると考えられます。
家具業界のM&A動向

業界が抱える課題の解決手段として、家具業界ではM&Aが活発化しつつあります。 M&Aは会社や事業の一部または全部を売買する取引であり、家具業界ではさまざまな目的のM&Aが見られることが特徴です。
家具業界のM&Aにおける主な動向を3つ紹介します。
家具業界への参入を目的とした異業種M&Aが増えている
家具業界では、新規参入を目的とした異業種によるM&Aが増えています。異業種M&Aが増えている理由としては、既存事業とのシナジー効果を生み出せる点や、国外の市場に開拓の余地がある点が挙げられます。
家具業界とのM&Aを進める異業種は、家電業界や建築業界といった家具・インテリアとの関係性が深い隣接業種が多い傾向です。経営が厳しい中小の家具メーカーは、異業種M&Aが選択肢の1つとなるでしょう。
家具業界による異業種への参入も増加傾向にある
家具業界による、アパレル業界・設備機器業界・物流業界などの異業種への参入も増加傾向にあります。
アパレル業界は家具業界と並んで「衣食住」に関わりがあり、設備機器業界・物流業界は家具業界のデザイン力や物流機能を活かせる領域であると考えられます。
家具業界が異業種に参入することで、家具製造や販売事業のビジネス縮小リスクを分散でき、企業の安定的な成長・発展を目指せます。自社が持つ強みを他の業界でも発揮できる場合は、M&Aを通して異業種への参入を検討すると良いでしょう。
後継者問題の解決を目的とした同業種・隣接業種M&Aも見られる
家具業界では、後継者問題の解決を目的とした同業種・隣接業種M&Aも見られます。
家具業界には創業者が一代で築いたメーカーが多く、創業者の高齢化に伴って後継者問題が持ち上がることが少なくありません。「親族内に後継者がいない」などで事業の引き継ぎができず、廃業を選択せざるを得ないこともあります。
M&Aによって同業種・隣接業種に事業を引き継いでもらうことは、後継者問題の1つの解決方法です。築き上げた会社を存続させるために、家具の製造・販売に関するノウハウを有した同業種・隣接業種に買収してもらいたいと考える経営者は多くなっています。
【家具業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット

M&Aで得られるメリットは、事業や会社を売却する譲渡(売り手)側と、買収する譲受(買い手)側で違いがあります。家具業界のM&Aを検討する際は、自社の立場を決めた上でM&Aのメリットを考えることが大切です。
ここからは、譲渡側のメリットを4つ挙げて、具体的にどのような魅力があるのか・どのような課題を解決できるのかを説明します。
従業員の雇用を確保したまま経営から退けられる
譲渡側の経営者は、従業員の雇用を確保したまま経営から退くことができます。
もしも家具メーカーを廃業する場合であれば、経営者は廃業にあたって従業員を解雇しなければなりません。解雇する従業員の生活を思って気が重くなったり、従業員に支払う退職金が多額になったりして、廃業時の負担が大きくなることもあるでしょう。
M&Aでは従業員は譲受側の会社でそのまま雇用されるため、経営者の負担が大きくならない点がメリットです。
個人保証や担保から解放される
家具メーカーのM&Aには、譲渡側の経営者が個人保証や担保から解放されるメリットもあります。
中小の家具メーカーでは、金融機関からの融資を受ける際に経営者の個人保証や担保を設定しているケースが少なくありません。個人保証・担保は金融機関からの債務返済を保証する仕組みであり、廃業などで事業継続ができなくなった場合は経営者個人に返済負担がのしかかる可能性があります。
株式譲渡などのM&Aスキームでは、譲渡側が設定した個人保証や担保は譲受側へと引き継がれるため、経営者は返済負担などの悩みからも解放されるでしょう。
売却益(創業者利益)を獲得できる
M&Aを実施すると、譲渡側は売却対象事業や株式の価値に応じた売却益(創業者利益)を獲得できます。中小の家具メーカーは経営者自身が株主であることが多く、オーナー経営者は獲得した売却益を自由に使えます。
売却益は基本的に数百万~数千万円という大きな金額です。オーナー経営者は売却益を自分の老後資金として貯蓄したり、新規事業の準備金にしたりと、M&A後の自分の人生を豊かにするために活用できます。
大手企業の傘下入りによって安定化・競争力強化に繋がる
M&Aによって大手企業の傘下に入った家具メーカーは、大手の資本を活用して経営基盤の安定化や市場競争力の強化を目指せます。
中小の家具メーカーは人材や財務などの経営基盤が弱く、事業戦略の実現や資金調達が難しいことも多い傾向です。結果として継続的な事業成長ができず、市場競争力も失いやすくなっています。
大手企業とのM&Aを実施すれば、大手の人材や資金などを活用して経営基盤を強化でき、安定的な事業成長と競争力強化に繋がります。
【家具業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット

家具業界のM&Aは、もちろん譲受側にもさまざまなメリットがあります。譲受側の主なメリットは、買収した家具メーカーの経営資源を活用し、新たな価値創出や事業展開・進出ができることです。
次に、M&Aによる譲受側のメリットを4つのポイントに分けて解説します。
経営資源をまとめて確保できる
M&Aを実施する譲受側は、譲渡側の家具メーカーが保有している人材・顧客・ノウハウなどの経営資源をまとめて確保できます。
譲受側が異業種の場合、家具事業領域に参入するには家具製造を行う人材や設備、販売のための物流やネットワークが必要です。M&Aによって経営資源をまとめて獲得すれば、スムーズな事業展開を行えます。
譲受側が同業種の家具メーカーである場合も、譲渡側の経営資源を確保することは事業拡大に繋がるメリットです。
事業規模や販路・ネットワークの拡大に繋がる
譲受側は家具事業を買収することで、自社の事業規模や販路・ネットワークの拡大に繋がります。特に中小の家具メーカーは地域の販路や独自の物流ネットワークを保有しているケースが多く、譲渡側が持っている強みを譲受側はそのまま引き継げます。
また、譲受側が今まで家具製造を外注していた場合は、家具メーカーを買収することで家具製造の内製化ができる点もメリットです。外注による仕入れコストがかからなくなり、他社との価格競争に強くなります。
買収した企業・事業のブランドを活用できる
家具業界で市場競争力を確保するには、製品の付加価値を高めることも重要です。M&Aの譲受側は買収した企業・事業のブランドを活用して、付加価値の高い製品を販売できます。
家具はデザイン性だけでなく機能性・耐久性も求められるため、短期間でブランドイメージを高めることが難しい商品です。もともとブランド力が高い企業・事業を買収することにより、短期間でブランドによる恩恵を受けられます。
新規事業の参入によって新たな収益源を確保できる
異業種M&Aの譲受側は、新規事業の参入によって新たな収益源を確保できるメリットもあります。
近年はどの業界も変革や整理淘汰が進んでおり、1つの事業のみでは安定的な収益を得ることは難しくなっています。収益の安定化を図るには、既存事業の強化を図るとともに、新たな収益源となる事業への進出も重要です。
家具事業は他業種とのシナジーを見込みやすい業界であり、譲受側は新規事業として参入することで収益性の向上を目指せます。
家具業界における主なM&A事例3選

家具業界のM&Aを成功させるためには、M&Aの事例を参考にすることも有効です。
ここからは、家具業界の同業種M&A1つと異業種M&A2つを紹介します。家具業界のM&Aに興味がある方は各事例の内容を参考に、自社のM&A戦略を組み立てるとよいでしょう。
株式会社サンゲツ×D’Perception Pte.Ltd.
株式会社サンゲツは2024年5月、D’Perception Pte.Ltd.の株式の過半数を取得することを発表しました。
| 譲渡(売り手)側 | D’Perception Pte.Ltd. |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社サンゲツ |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
D’Perception Pte.Ltd.は、空間デザインや総合施工を事業として展開するシンガポールの企業です。
譲受側の株式会社サンゲツはインテリア商品やエクステリア商品などを取り扱う企業です。
本M&Aは、2社の協業によってアジア全域への事業拡大を見据え、市場競争力や収益力の強化を目指しています。
コクヨ株式会社×オリジン株式会社・株式会社エステイツク
コクヨ株式会社は2023年1月、オリジン株式会社と株式会社エステイツクの全株式を取得しました。
| 譲渡(売り手)側 | オリジン株式会社・株式会社エステイツク |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | コクヨ株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
オリジン株式会社はオフィス家具などの製造を行う家具メーカーであり、もう1つの株式会社エステイツクは独創性の高い製品を製造・販売する家具販売業者です。
国内の大手家具メーカーであるコクヨは2社を子会社化することで、家具事業領域の強化を図っています。
株式会社ヤマダホールディングス×株式会社大塚家具
株式会社ヤマダホールディングスは2022年5月、子会社の株式会社ヤマダデンキを存続会社として、株式会社大塚家具の吸収合併を行いました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社大塚家具 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社ヤマダホールディングス |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 吸収合併 |
株式会社大塚家具は家庭用家具・オフィス家具の大手メーカーであり、株式会社ヤマダデンキは家電商品を販売する家電量販店です。
株式会社大塚家具は2019年に株式会社ヤマダホールディングスの子会社となり、2021年には完全子会社化しました。本M&Aは吸収合併により2社の連携を深め、企業価値の向上を目指すものとなっています。
家具業界のM&A検討時におすすめの相談先

最後に、家具業界のM&A検討時におすすめの相談先を3つ紹介します。
●M&Aアドバイザー
M&Aアドバイザーは譲渡側と譲受側の間に立ち、M&Aを総合的に支援する専門会社です。家具メーカーにとって最適な候補の選定・紹介から、2社の交渉仲介やM&Aスケジュールの管理、最終契約とPMIまでをサポートしてくれます。
●金融機関
金融機関によっては、取引する会社のM&Aをサポートできる体制が整っています。金融機関は融資先の財務状況に詳しく、独自の企業ネットワークも保有していることが強みです。
●公的機関
事業承継・引継ぎ支援センターや商工会議所などの公的機関においても、M&Aの相談に対応してくれます。支援のスピードや範囲は十分ではないものの、重要なM&Aの相談を任せられる高い信頼性があります。
特におすすめの相談先は「M&Aアドバイザー」です。M&AアドバイザーはM&Aの専門知識やノウハウを有しており、家具メーカーの課題や目的に合う提案をしてくれます。譲渡側・譲受側の仲介をしてくれるため、M&Aの流れがスムーズに進みやすい点も魅力です。
まとめ
家具業界には価格帯の二極化や住宅業界の動向による影響といった課題が存在し、同業種・異業種のM&Aが活発化しています。
家具業界のM&Aを実施したい方は、自社の立場におけるメリットを把握し、M&Aアドバイザーなどのサポートを受けることも検討しましょう。
株式会社レコフは豊富なM&A実績があり、お客様へのM&A提案から完了までを一貫してサポートするM&A助言会社です。家具業界のM&Aで悩みや不安がある方は、株式会社レコフにご相談ください。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00