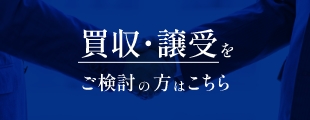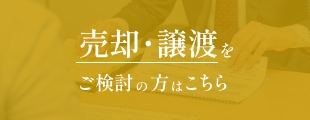平日9:00〜18:00

放送業界のM&A動向
業界別M&A
テレビやラジオといった従来型のメディアに加え、動画配信サービスやSNSの台頭によって、放送業界のビジネス環境は大きく変化しています。視聴者のメディア接触時間や広告の在り方が多様化する中で、放送局や制作会社によるM&Aも活発化しています。
今回は、放送業界の概要や市場動向を踏まえた上で、M&Aの動向や立場ごとのメリット・デメリット、さらに成功に向けたポイントを詳しく解説します。放送業界でのM&Aを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
-
放送業界とは?
-
放送業界の市場規模と課題
-
放送業界のM&A動向
-
放送業界のM&Aによるメリット&デメリット
-
放送業界の主なM&A事例
-
放送業界のM&Aを成功させるためにおさえておくべきポイント
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
放送業界とは?

放送業界とは、電波や通信設備を用いて情報や娯楽などの多様な情報を不特定多数の視聴者に広く発信する産業・事業者の総称です。放送には総務省の「放送法」に基づいた放送免許が必要であり、業界全体は国による厳格なルールのもとで運営されています。
放送業界は大きく、「テレビ業界」と「ラジオ業界」の2つに分類され、それぞれ異なるメディア特性をもちながら社会に重要な情報を提供しています。
●テレビ業界
テレビを通して映像と音声、文字情報を組み合わせながら、報道番組や娯楽番組、ドラマなどの幅広いコンテンツを提供する分野です。視聴者の日常生活に密着した存在であり、情報伝達とエンターテインメントの両面で大きな役割を担っています。
●ラジオ業界
ラジオ業界は、音声を中心に情報を発信する分野で、音楽やトーク番組などが主なコンテンツです。近年ではスマートフォンアプリやPC経由での視聴が広がっており、場所や時間にとらわれず利用できる利便性から、再評価が進んでいます。
放送業界の特色は、「公共性の高さ」と「規制の厳しさ」です。公共の電波を利用しているため、表現内容には倫理性・公平性が求められ、広告の量や時間帯などにも制約があります。また、事業を営むには放送免許を取得する必要があり、新規参入のハードルが高いのも特徴です。
なお、近年ではAbemaTVやNetflixといったインターネットを介した動画配信サービスが台頭していますが、これらは「放送免許」を必要としないため、厳密には放送業界には含まれません。こうしたサービスは「OTT(Over The Top)サービス」や「配信(ストリーミング)業界」と呼ばれ、放送業界とは異なる産業構造を持っています。
放送業界の市場規模と課題

総務省が公表した「令和6年版 情報通信白書」によると、2022年度における日本の放送産業の市場規模(売上高ベース)は3兆6,845億円でした。 。
【放送業界の市場規模の推移(2018年~2022年)】
| 2018年 | 3兆9,418億円 |
|---|---|
| 2019年 | 3兆8,643億円 |
| 2020年 | 3兆5,522億円 |
| 2021年 | 3兆7,157億円 |
| 2022年 | 3兆6,845億円 |
【2022年における放送業界の売上高の内訳・前年比】
| 事業者分類 | 売上高集計 | 前年比 |
|---|---|---|
| 地上系基幹放送事業者 | 2兆1,623億円 | -0.36% |
| 衛星系放送事業者 | 3,370億円 | -1.40% |
| ケーブルテレビ事業者 | 4,880億円 | -2.20% |
(出典:総務省「令和6年版 情報通信白書|放送市場の規模」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd213110.html )
内訳を見ると、地上系基幹放送事業が2兆1,623億円、衛星系放送事業が3,370億円、ケーブルテレビ事業が約4,880億円となっており、いずれも前年から微減しています。長期的に見ると放送業界全体の市場は緩やかな縮小傾向にあり、従来型の放送ビジネスは明らかに転換期を迎えている状況です。
市場の変化をもたらしている背景には、複数の構造的な要因が挙げられます。
●スマートフォンやタブレットの普及に伴う若年層のテレビ・ラジオ離れ
かつて家庭の中心にあったテレビですが、近年では若年層を中心に視聴時間が減少しています。代わってYouTubeをはじめとした動画配信サービスなどのネットメディア利用が拡大しており、若い世代のメディア接触は大きく様変わりしています。
●広告主の出稿先の変化
メディアの利用形態の変化に伴い、企業の広告戦略も変わってきています。近年ではインターネット広告費がテレビ広告費を上回るようになり、放送業界の広告収入は年々縮小しています。特にローカル局にとっては大きな打撃となっており、経営基盤の維持が難しくなるケースも増えています。
●SNSや配信サービスの台頭による視聴者ニーズの細分化・多様化
SNSや個人向け配信サービスの普及により、視聴者の関心は従来の「マス向け番組」から離れ、より個人の嗜好に寄り添うコンテンツへと移っています。これにより、従来の番組編成やコンテンツ提供の手法では対応しきれないケースが増えており、柔軟なサービス設計が求められるようになっています。
一方で、高齢者層のテレビ視聴時間は依然として多く、特定の層には根強いニーズが存在しています。しかし、それだけでは広告収入の減少を補いきれず、業界全体としては厳しい経営環境が続いています。
放送業界のM&A動向

かつての放送業界では、M&Aはほとんど行われていませんでした。
その背景には、放送局が厳格な許認可制度のもとで守られていたことに加え、巨額の資金が必要となる買収には現実的なハードルが多かったことなどが挙げられます。安定した広告収入に支えられた経営が成り立っていたため、外部資本を受け入れる必要性も乏しかったと言えるでしょう。
しかし近年では、広告収入の減少や視聴者ニーズの多様化といった課題を受け、放送局各社はネット事業への参入やコンテンツとデジタル技術を連携させた新規ビジネスの開発に積極的に取り組むようになっています。その中で、M&Aによる事業の多角化や経営資源の再編が現実的な選択肢として注目されています。
放送業界のM&Aが社会的に注目された最初の転機は、2005年の「ライブドア騒動」でした。この事件をきっかけに、許認可制度のあり方や、放送局の経営体制の問題点が広く議論されるようになり、M&Aへの意識も徐々に変化していきました。
現在では、例えば大手放送局が自社のコンテンツ力を強化するために制作会社を買収したり、配信事業に進出する目的でIT企業との提携や買収を行ったりと、M&Aが経営戦略の一環として活発化しています。また、広告会社やネット企業が放送局のブランド力を活用し、広告・配信分野を拡大する動きも見られます。
放送業界のこうした状況を踏まえると、今後はビジネスモデルの見直しや他業種との連携、そしてM&Aを通じた構造改革がますます重要になっていくと言えるでしょう。
放送業界のM&Aによるメリット&デメリット
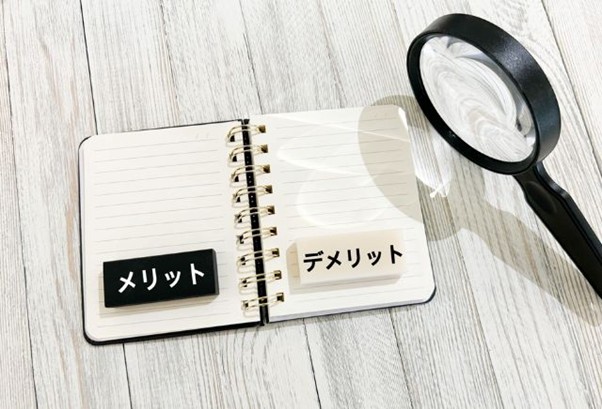
放送業界におけるM&A(企業の合併・買収)は、近年になってその動きが徐々に活発化しています。その背景には、広告収入の減少や視聴者の行動変容といった「従来のビジネスモデルの限界」が挙げられます。
各社が新たな事業展開を模索している中で注目されているのが、M&Aを通じた事業基盤の強化や新規事業の創出です。しかし放送業界のM&Aは、規制上の課題や文化の違いによる摩擦などのデメリットも少なくありません。
そこで次に、放送業界におけるM&Aの主なメリットとデメリットを紹介します。
メリット(1)事業基盤の強化と経営の効率化を図れる
M&Aによって、異なる放送局や関連企業が持つ技術・人材・拠点などのリソースを統合すれば、事業基盤の強化につながります。例えば、番組制作機能や送出設備を一本化することで、重複するコストの削減が可能となり、より効率的な経営体制を構築できます。
また、制作部門の連携により、企画や取材、編集などの工程も共有できるため、番組制作全体のスピードアップや品質向上にも寄与します。さらに、統合によって得た余剰リソースを新規事業の立ち上げに活用することで、将来的な収益拡大を目指す土台づくりにもつながります。
メリット(2)市場の拡大や新たなビジネスモデルの確立につながる
M&Aは、市場拡大や新たなビジネスモデルの構築にも貢献します。たとえば、放送局とネット系企業・広告会社が手を組むことで、アーカイブされた番組コンテンツや編成ノウハウを、デジタル配信技術やデータマーケティングと融合させることが可能になります。
ノウハウとマーケティングの融合によって、地上波やBS・CS放送だけでなく、動画配信サービスやSNS、ポッドキャストといった多様なチャネルでのコンテンツ展開が実現し、視聴者層の拡大やブランド価値の向上につながると考えられます。
こうした柔軟なビジネスモデルへの転換は、今後の成長戦略において大きな意味をもつでしょう。
メリット(3)広告・マーケティング面でのシナジー効果が期待できる
デジタル広告市場が拡大を続ける中、放送業界でも広告・マーケティングの刷新が求められています。M&Aによって、放送局の営業部門とネット企業の広告テクノロジーやデータ分析力を組み合わせれば、新たな広告商品を生み出すことが可能です。
例えば、番組とSNS広告を連動させたクロスメディア施策や、視聴者の行動データに基づいたパーソナライズ広告など、付加価値の高い提案ができるようになります。こうした取り組みは、広告主の期待に応えつつ、広告収益の最大化にも貢献すると言えるでしょう。
メリット(4)ハッピーリタイアを実現できる
経営者視点で見た場合、M&Aによる会社売却は「ハッピーリタイア」の手段としても注目されています。株式の売却によって大きな資金を得られるだけでなく、個人保証や担保責任から解放され、安心して次の人生を歩むことができます。
また、売却後も顧問や役員として企業運営に関わることが可能なケースもあり、培った知見を次世代に引き継ぐことも可能です。特に地方のローカル局やコンテンツ制作会社にとって、後継者問題の解決策としてのM&Aはより現実的な選択肢となっています。
デメリット(1)厳格な規制や手続きのハードルがある
放送業界には他業種にはない独自の規制が存在しており、M&Aを進めるうえでの障壁となる場合があります。例えば、放送業界には「マスメディア集中排除原則」といって、特定の企業が放送局を支配することを厳しく制限するルールがあります。そのため、M&A実施時には持株比率や系列関係に注意しておかなければなりません。
また、外資規制も厳格で、外国資本が一定割合以上の株式を保有することは法律で禁止されています。さらに、地上波放送局などの場合、総務省の認可が必要となるケースも多く、手続きや審査に時間とコストがかかる点も無視できません。特に、異業種からの参入においては規制の理解と対応がより重要となります。
デメリット(2)企業文化や制作方針の違いによる統合リスクがある
放送業界のM&Aでは、各社が長年にわたって築いてきた企業文化や制作方針の違いが、統合後の大きな課題となるケースもあります。
特に、系列を超えた統合や異業種とのM&Aにおいては、こうした違いによる影響が表面化しやすく、現場レベルでの摩擦や不満につながるリスクもあります。
これらをうまくコントロールできなければ期待されていたシナジーが発揮されず、業績が悪化する可能性があることに注意が必要です。
放送業界の主なM&A事例
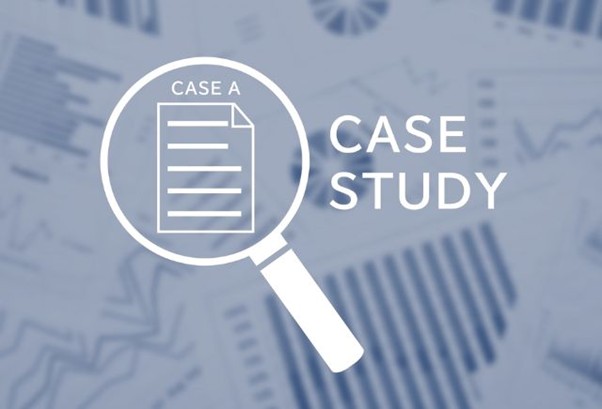
放送業界におけるM&Aは、メディア環境の変化やコンテンツの多角的展開を見据えた戦略的な動きとして注目されています。成功事例を把握することは、今後のM&Aを進めるうえで有効な参考となるでしょう。
ここからは、放送業界における代表的な3つのM&A事例を詳しく紹介します。
TBSホールディングス株式会社×株式会社ケイコンテンツ
2025年5月、TBSホールディングス株式会社は株式会社ケイコンテンツの株式を取得し、連結子会社化しました。 M&Aの詳細は、下記の通りです。
| 譲渡(売り手)側 | TBSホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社ケイコンテンツ |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
TBSホールディングス株式会社は、日本の大手放送持株会社で、テレビ放送や動画配信を中心に幅広くメディア事業を展開しています。 株式会社ケイコンテンツは、YouTubeを中心に、人気アニメIPの企画・制作・管理を展開する企業です。 当M&Aにより、TBSホールディングス株式会社はケイコンテンツのIP資産を活用しながらアニメや関連メディアの多角的展開を進め、IPの価値最大化と収益強化を図る方針です。
HJホールディングス株式会社×Hulu,LLCほか
HJホールディングス株式会社は、Hulu,LCC(米国Hulu社)とLINEヤフー株式会社(旧ヤフー株式会社)、東宝株式会社、讀賣テレビ放送株式会社、中京テレビ放送株式会社を引受先とする第三者割当増資を2017年7月に実施しました。
M&Aの詳細は、下記の通りです。
| 出資を受けた側 (実施主体) |
HJホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 出資した側 (引受先) |
|
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 資本提携(第三者割当増資) |
HJホールディングス株式会社は、日本テレビ放送網株式会社の連結子会社であり、動画配信サービス「Hulu」を日本国内で運営する企業です。 今回の資本提携では、米国Hulu社(Hulu, LLC)をはじめ、放送業界における国内大手5社が出資者として名を連ねています。いずれも映像やインターネットコンテンツ領域で実績を誇る企業であり、今後の協業体制を見据えた戦略的パートナーと言えます。 この資本提携により、HJホールディングスは、コンテンツのさらなる拡充や動画配信インフラの強化を図るとともに、各パートナー企業との連携を深めることで、Huluブランドの競争力を一層高めていく方針です。
日本BS放送株式会社×株式会社国土社・株式会社理論社
日本BS放送株式会社は2018年1月、株式会社国土社および株式会社理論社の全株式を取得し、連結子会社化しました。 M&Aの詳細は、下記の通りです。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社国土社 株式会社理論社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 日本BS放送株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式取得 |
日本BS放送株式会社は、BS11(日本BS放送)を運営する企業で、幅広い視聴者層に向けた番組編成を手がけています。 株式会社国土社は建築・土木分野、株式会社理論社は科学・技術分野の専門出版に強みをもつ出版社です。 本M&Aにより、各社の優良コンテンツと媒体価値を高めるとともに、出版事業の成長とグループ全体の収益多角化を目指しています。
放送業界のM&Aを成功させるためにおさえておくべきポイント

放送業界におけるM&Aでは、単に経営権の移転を行うだけでは成功とは言えません。事業の継続性や価値向上を見据えたうえで、慎重かつ戦略的に進める必要があります。
最後に、放送業界でM&Aを成功に導くために重要な3つのポイントをご紹介します。
優秀な人材の雇用を維持する
放送業界においては、番組制作やコンテンツ開発に関わる人材が企業の競争力そのものであり、事業価値の源泉です。 M&Aによって経営体制が変わると、従業員が不安を感じてしまい、優秀なスタッフが離職するリスクも高まります。優秀な人材の維持は、M&A後の統合プロセスにおいて極めて重要な要素となります。
そのため、M&Aを進める段階で社員に対して雇用条件の継続や今後のビジョンを丁寧に共有し、不安の払拭に努めることが不可欠です。従業員にとっても将来が見える状態であれば、安心して働き続けることができ、M&Aの成功確率も高まります。
シナジーを創出できる相手を見つける
放送業界のM&Aでは、シナジー(相乗効果)を生み出せる相手を選ぶことが成否を左右すると言っても過言ではありません。 技術力やコンテンツ制作力を補完し合える関係や、放送と出版・配信との連携が期待できるケースなど、明確なシナジーのある相手を見極めることが重要です。
特に売り手側にとっては、自社の魅力を高めておくことが、理想的な買い手を引き寄せるカギとなります。例えば、若手の優秀な人材を多く確保していることや放送倫理や内部統制といったガバナンス面が整備されていることは、買い手にとって安心材料となり、交渉を有利に進めやすくなります。
また、コンプライアンス体制の整備や健全な財務管理も、企業としての信頼性を高める要素です。M&A成功のためには、買い手に「この会社となら連携したい」と思わせるような総合的な魅力づくりが欠かせません。
M&Aの専門家へ相談する
放送業界でM&Aを成功させるには、企業の魅力を磨き上げる努力を重ねながら、外部の専門家の力も借りて着実に進めていくことが重要です。
M&Aは、法務・財務・税務といった様々な専門知識が求められる複雑なプロセスです。特に放送業界は、電波利用やコンテンツに関する特有の規制や契約が存在するため、専門家のサポートが不可欠です。 M&Aについて相談できる専門家には、 M&Aに精通した弁護士や公認会計士、税理士のほか、業界知見のあるM&Aアドバイザーが挙げられます。M&Aアドバイザーは、適切な相手先の紹介から交渉支援、手続きのフォローまで一貫して対応してくれるため、スムーズなM&Aを実現しやすくなります。
まとめ
放送業界では、視聴スタイルの多様化やデジタルコンテンツの拡大を背景に、M&Aを活用した事業再編や成長戦略が加速しています。
放送業界のM&Aを円滑に進めるため、そして成功に導くためには、優秀な人材の確保や、企業としての総合的な魅力の強化が重要です。加えて、業界に精通し豊富な実績を有する専門家への相談も欠かせません。
株式会社レコフでは、戦略立案からマッチング、成約までを一貫してサポートしております。M&Aを通じた成長や課題解決をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00