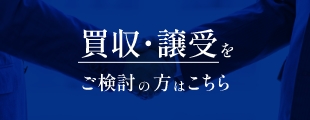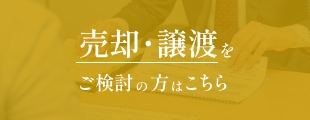平日9:00〜18:00

金属加工業界のM&A動向
業界別M&A
昨今の金属加工業界は、技術革新やグローバル化の進展に伴い、様々な課題に直面しています。特に、経営者の高齢化や後継者不足といった問題が深刻化する中、M&Aは重要な解決策として注目されている戦略の1つです。
また、M&Aは事業の継続や成長を目指すだけでなく、技術力の強化や経営基盤の強化にも寄与するでしょう。当記事では、金属加工業界におけるM&Aの最新動向や譲渡側・譲受側双方のメリット、近年の参考事例などを解説します。
-
金属加工業界(金属製品製造業界)とは?
-
金属加工業界の市場規模
-
金属加工業界を取り巻く現状と課題
-
金属加工業界におけるM&A最新動向
-
【金属加工業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット
-
【金属加工業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット
-
金属加工業界における主なM&A事例3選
-
金属加工業界のM&Aに関する主な相談先4選
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
金属加工業界(金属製品製造業界)とは?

金属加工業界(金属製品製造業界)とは、金属材料を使用目的に合わせて所定の形状や寸法を持つ製品に加工する業界です。 例として、板や棒などの半製品を加工して日用品や各種機械・装置を製造する企業が該当します。総務省の日本標準産業分類では「中分類24-金属製品製造業」です。ブリキ缶・めっき板・刃物・手道具類・建設用金属製品などが対象となります。
この業界の特徴は、特定の製品ラインアップに特化した中小零細企業が多く存在し、その大半が優れた技術力を持っている点です。基本的に受注生産型のビジネスモデルを採用しており、自動車や建設業界などの大規模なユーザー企業のニーズに対応する製品を作ります。ユーザー企業の細かな要望に応じるため、ほかの製造業に比べて国内生産に依存する傾向が強い業界です。
金属加工業界と混同されやすい業界に鉄鋼業界がありますが、その役割は異なります。鉄鋼業は鉱石や鉄くずから鉄や鋼を製造する産業であり、金属加工業で用いる金属材料そのものを提供する業界です。金属加工業界では、この鉄鋼材料を使用して最終製品や部品を作り上げます。
金属加工業界は、日本の「ものづくり産業」を支える重要な立ち位置です。しかし、技術の継承や海外進出など、業界が直面する課題も少なくありません。
金属加工業界の市場規模

金属加工業界を含む金属製品製造業の市場規模は、国内経済に強く影響される傾向があります。
経済産業省が発表した2022年度のデータによると、金属製品製造業の製品出荷額は約16兆9,199億円に達しました。業界全体の事業所数は3万589事業所、従業員数は60万7,992人です。これにより、金属製品製造業は国内製造業の中で重要な位置を占めることが伺えます。
(出典:経済産業省「2023 年経済構造実態調査二次集計結果<製造業事業所調査>結果の概要」https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kkj/pdf/seizo_gaikyo2023.pdf )
また、財務省の「法人企業統計調査」によれば、2022年度の金属製品製造業の売上高は約19兆4,657億円で、前年度から約5.8%増加しました。
(出典:経済産業省「2023 年経済構造実態調査二次集計結果<製造業事業所調査>結果の概要」https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kkj/pdf/seizo_gaikyo2023.pdf )
この増加の背景にあるのは、アフターコロナの影響で、住宅向け金属製品や建設資材の需要が高まったことです。特に、製缶や金属プレス製品などの需要が拡大し、業界全体の売上を押し上げたとされています。
しかし、金属製品製造業の市場規模が今後もこの水準を維持するかどうかは不透明です。例えば、素材が金属から樹脂に置き換えられる動きや、3Dプリンターの普及などが業界に影響をおよぼす可能性があります。ウクライナ問題などの国際情勢による材料費の高騰も、業界の課題です。このような状況下で、業界各社は未来に向けた技術革新と経営力の強化が求められています。
金属加工業界を取り巻く現状と課題

近年の金属加工業界では、市場規模の拡大が見られる一方、様々な課題が顕在化しています。業界全体の持続的な成長を阻む要因として特に代表的なのが、IT化の遅れや海外進出の加速、技術力の継承などです。
ここからは、金属加工業界の主な課題3つを解説します。
IT化への対応
金属加工業界では、IT化による生産性向上が急務です。海外企業との競争が激化する中、国内企業は技術面やコスト面での優位性を失いつつあります。このため、設備投資を含むIT化によって生産効率を高める動きが強まってきました。
例えば、1社で金型製作から金属プレス加工までを一貫して行う場合です。3次元の形状を短時間で測定する機械や、プレス機の稼働状況をリアルタイムで把握するシステムを導入し、業務効率を約3倍にまで向上させた企業もあります。IT化への取り組みは、今後の業界全体の競争力を大きく左右する要素となるでしょう。
海外進出の活発化
金属加工業界の主要な取引先である自動車や電機業界で加速しているのが、海外進出です。この流れに伴い、現地での材料調達や生産活動も増加しており、国内金属加工企業にとっては、取引の打ち切りや取引量の減少などのリスクが高まっています。
こうした状況に対応するには、各企業が海外展開を視野に入れた戦略を構築しなければなりません。例えば、短納期での納品や多品種小ロット生産など、取引先のニーズに応える柔軟な対応力が必要<?です。また、独自の技術やノウハウを活用した高付加価値の製品も、競争力の維持につながります。
技術力の継承
金属加工業界において、技術力の継承は喫緊の課題です。特に、高度な技術を持つ職人の定年退職に伴い、次世代への技術継承が難しいケースが増えています。金属加工には、個々の職人の経験や勘が必要とされる作業が少なくありません。これらの技術が失われると、企業の競争力に大きな影響を与えます。
この課題の解決には、若手技術者の育成や技術の標準化が有効です。また、IT化による技術のデジタル化や、教育システムの構築も求められています。これにより、技術力の継承とともに、さらなる生産性の向上が期待できるでしょう。
金属加工業界におけるM&A最新動向

近年の金属加工業界では、M&Aが活発化しています。金属加工業界におけるM&Aでは、同業種による買収だけでなく、他業種による買収も多く見られるのが特徴です。
●金属加工業界同士のM&A
金属加工業界内でのM&Aの目的は、主に技術力の強化や事業の拡大です。プレス加工や切削加工など、金属加工には多岐にわたる技術が存在し、各企業がそれぞれの専門技術を持っています。
このような企業が、異なる技術を持つ同業者の買収によって技術力を獲得し、自社の製品ラインアップを拡充するケースが増加中です。新たな技術の獲得により、未開拓の市場に参入するチャンスが生まれるため、成長戦略としてM&Aが積極的に活用されています。
また、経営者の高齢化や後継者不足が進む中、廃業回避にM&Aが選択されるケースも少なくありません。
●他業種による金属加工業界のM&A
金属加工業界は、他業種からのM&Aのターゲットとしても注目されています。特に商社や自動車関連企業など、川上・川下の企業が金属加工会社を買収する事例が増えてきました。
中でも、サプライチェーンの強化やシナジー効果の創出を目的とした垂直統合型のM&Aは特に多く見られます。例えば、商社が金属加工会社を買収することで、製販一体の事業展開を実現し、コスト削減や販路拡大を狙うケースが典型的です。
また、自動車業界のような製品の質や生産スピードが競争力の源泉となる業界では、独自の技術を持つ金属加工会社の買収により、製品の競争力強化が期待されています。
【金属加工業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット

金属加工業界において、M&Aは事業を継続・発展させるための有力な手段となります。譲渡側の得られるメリットとして代表的なのが、後継者問題の解消と創業者利益の確保、個人の財務リスクからの解放です。
ここからは、M&Aによる譲渡側の主なメリットを3つ解説します。
後継者問題を解決させられる
金属加工企業では、経営者が高齢化しているにもかかわらず、後継者が見つからないケースが少なくありません。M&Aを活用すれば、後継者がいなくても技術やノウハウが継承でき、廃業も回避できます。
また、M&Aは従業員の雇用を守れる点も大きなメリットです。廃業すれば従業員は解雇するしかありません。しかし、M&Aによって買い手企業が事業を引き継げば、従業員の雇用継続も期待できます。経営者は従業員の行く末を心配することなく、安心して引退できるでしょう。
創業者利益(譲渡益)を獲得できる
M&Aによって経営者が保有する株式を譲渡すれば、譲渡益を得られます。金属加工業界の多くの企業は非上場であり、株式を現金化する機会は限られているケースが大半です。しかし、M&Aを通じて株式を売却すれば、まとまった資金を得られます。
譲渡益は、経営者が新たな事業への投資やセカンドライフの資金として活用できるため、経済的メリットは非常に大きいものとなるでしょう。また、株式譲渡によって現金化された資金は、相続税の資金として活用が可能です。これも、経営者にとって重要な財務的利点に挙げられます。
個人保証・担保を解除できる
中小企業では、金融機関からの融資に際して個人保証や担保を提供している経営者が多く見られます。M&Aを通じた事業譲渡の際、買い手企業が個人保証事態を引き継いだり融資を肩代わりしたりすれば、経営者は保証や担保の解除が可能です。
個人保証や担保は、経営者にとって大きな精神的・経済的負担となるため、事業承継の妨げになるケースが少なくありません。特に、親族内での事業承継が難しい場合や、経営者が引退後のリスクを最小限に抑えたいと考えている場合、M&Aは有効な手段となるでしょう。
【金属加工業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット

金属加工業界において、M&Aは譲渡側だけでなく譲受側にも多くのメリットをもたらします。代表的なのが、経営資源を迅速に獲得できる点や事業拡大・発展の可能性、経営リスク分散と財務力強化などです。
次に、M&Aによる譲受側の主なメリットを3つ解説します。
経営資源をまとめて獲得できる
M&Aを通じて、買い手企業は売り手企業技術力・ノウハウ・設備・顧客基盤・ブランド力・優秀な人材といった経営資源を一度に獲得できます。金属加工業界では特に技術力が競争力の鍵となるものの、新しい技術を一から習得するには多大な時間とコストが必要です。
しかし、M&Aによって売り手企業が持つ技術力をそのまま取り込めば、即座に競争力や事業基盤を強化できます。また、優秀な人材の雇用により、技術のさらなる発展や事業の継続的成長も期待できるでしょう。
シナジー効果による事業の拡大・発展が期待できる
M&Aの大きな目的の1つが、シナジー効果の発揮です。金属加工業界においても、買い手企業と売り手企業の強みを組み合わせることで、シナジー効果が期待できます。
例えば、買い手企業の販売チャネルを活用し売り手企業の製品を広範囲に展開すれば、売上シナジーが生まれるでしょう。また、両社の設備や技術の統合で、仕入れコストや製造コストを削減するコストシナジーも発生します。
さらに、ノウハウの融合により、新たな製品開発や市場開拓も可能となり、事業のさらなる拡大と発展が期待できます。
経営リスクを分散させつつ財務力を強化できる
M&Aを通じた他業種の買収により、事業の多角化と経営リスクの分散が可能です。金属加工業界は、経済状況や需要の変動に左右されやすい業界です。しかし、異なる業種に進出すれば、経営を特定の市場に依存する必要がありません。
これにより、外部環境の急変による影響を最小限に抑えられます。また、複数の事業を持てば、キャッシュフローの安定性確保や財務基盤の強化も可能です。さらに、多角化による新たな収益源の確保は、企業全体の成長を促進し長期的な競争力の維持・強化にも寄与するでしょう。
金属加工業界における主なM&A事例3選

譲渡・譲受のいずれの場合でも、金属加工業界におけるM&Aを成功させるためには、事例を参考にするのが有効です。
ここからは、近年実施された金属加工業界における代表的な3つのM&A事例を紹介します。M&Aを検討している方は、今後の戦略を立てる際の参考にしてください。
日鉄物産株式会社×電機資材株式会社
日鉄物産株式会社は、2024年に電機資材株式会社の株式を追加取得し、同社を子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 電機資材株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 日鉄物産株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡(部分譲渡) |
日鉄物産株式会社は、鉄鋼や産業機器などの商材を扱う大手商社で、国内外で幅広い事業を展開しています。一方、電機資材株式会社は、電磁鋼板や非鉄金属の販売を専門とする商社です。 このM&Aの目的は、日鉄物産が電磁鋼板事業における営業基盤のさらなる強化と、サプライチェーン全体の効率向上です。株式の追加取得によって日鉄物産は電機資材を完全子会社化し、市場シェアの拡大と事業の競争力強化を図りました。
三菱マテリアルグループ×H.C.Starck Holding
三菱マテリアルグループは、2024年にH.C.Starck Holdingの全株式を取得し、同社を完全子会社としました。
| 譲渡(売り手)側 | H.C.Starck Holding |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 三菱マテリアルグループ |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡(全部譲渡) |
三菱マテリアルグループは、非鉄金属や超硬工具など多岐にわたる事業を展開する大手企業です。H.C.Starck Holdingは、タングステン製品の製造・販売およびリサイクルにおいて世界有数の企業で、欧州・北米・中国などで強固な市場基盤を持っています。 このM&Aの目的は、三菱マテリアルがグローバルなタングステン事業の強化を図ることです。リサイクル技術・能力の活用によりシナジー効果を発揮し、世界的な競争力を一層高める狙いもあります。
岡谷鋼機株式会社×旭精機工業株式会社
岡谷鋼機株式会社は、2021年に旭精機工業株式会社との資本業務提携契約を締結し、第三者割当増資を引き受けました。
| 譲渡(売り手)側 | 旭精機工業株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 岡谷鋼機株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 第三者割当増資(部分譲渡) |
岡谷鋼機株式会社は、世界23カ国で鉄鋼や産業資材などを取り扱う大手商社です。旭精機工業株式会社は、自動車や情報通信、家電向けの精密金属加工品を製造・販売しています。 このM&Aは、両社が持つ経営資源やノウハウを有効活用し、事業活動の効率化と販売拡大を図るのが目的です。資本業務提携により、両社はさらなる連携と協力関係を強化し、ともに成長を目指しています。
金属加工業界のM&Aに関する主な相談先4選

金属加工業界のM&Aに関する相談先には、以下のような選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、自社に最適な相談先を選ぶことが重要です。
●公的機関
商工会議所や事業承継・引継ぎ支援センターといった公的機関では、中小企業へのM&Aや事業承継を支援しています。初めてM&Aを検討する企業には安心して相談できる場所ではあるものの、専門的な実務サポートには限界があります。複雑な案件には別途専門家の助言が必要です。
●士業
弁護士・税理士・公認会計士などの士業からは、M&Aや事業承継に関する法務や税務のアドバイスが受けられます。特に会計・税務の観点での専門性が高く、法務や税務に関するサポートでは頼りになる相談先です。ただし、M&Aに関する知識や経験が豊富な士業を選ぶ必要があります。
●マッチングプラットフォーム
マッチングプラットフォームは、M&Aの相手企業をインターネット上で探せるものです。売り手と買い手の直接交渉が可能で、特にコストを抑えたい中小企業には魅力的な選択肢です。ただし、専門的な助言やサポートにはあまり期待できません。
●M&Aアドバイザー
M&Aアドバイザーは、売手と買手の間に立ち、取引全体をサポートします。幅広いネットワークと豊富な経験を生かして最適なM&A相手を見つけるだけでなく、デューデリジェンスや契約交渉などの実務も支援します。包括的かつ専門的なサポートを受けたいのであれば、M&Aアドバイザーが最もおすすめです。
まとめ
金属加工業界におけるM&Aは、事業の継続や成長、技術力の強化を目指す上で重要な手段です。譲渡側には後継者問題の解決や創業者利益の獲得といったメリットがあり、譲受側には経営資源の獲得やシナジー効果が期待できます。
どのようなM&Aをすべきか迷ったときは、同業種による事例を参考にすると、より効果的な戦略を立てられるでしょう。M&Aを真剣に検討するのであれば、適切な相談先を選び専門的なサポートを受けることが成功への鍵となります。金属加工業界のM&Aを検討している方は、ぜひ一度「株式会社レコフ」にお問い合わせください。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00