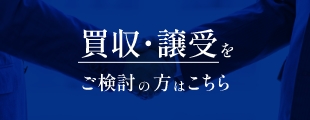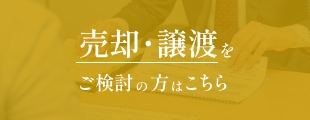平日9:00〜18:00

自動車整備業のM&A動向
業界別M&A
自動車整備業界では、後継者問題や新技術への対応が急務となっており、M&A(企業の合併・買収)が有力な選択肢として注目されています。特に、整備士不足や設備投資の課題を抱える企業にとって、M&Aは事業継続や成長の鍵を握る重要な手段となり得るでしょう。
当記事では、自動車整備業界におけるM&Aの動向や具体的なメリット、成功事例に加え、円滑に進めるためのポイントを解説します。M&Aを検討している事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
-
自動車整備業とは?
-
自動車整備業の市場規模
-
自動車整備業のM&A動向|活発化する理由は?
-
【自動車整備業】M&Aによる立場ごとのメリット
-
自動車整備業における主なM&A事例3選
-
自動車整備業のM&Aを成功させるためのポイント
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
自動車整備業とは?

自動車整備業とは、自動車の安全な運行を維持するために、自動車のメンテナンスや修理、車検などを行う業種です。主な業務には、車検整備や定期点検整備、事故後の修理、およびカーナビやETC機器の取りつけなどがあります。
自動車整備工場は、一般的に「認証工場」と「指定工場」の2つに大別されます。それぞれの役割・機能の主な差は、以下の通りです。
●認証工場
認証工場とは、地方運輸局の認可を受けて、自動車の分解整備を行う工場のことです。認証工場では車検のための整備作業は可能なものの、車検検査そのものはできません。そのため、車検を受ける際には陸運局へ自動車を持ち込んで、最終的な検査を行う必要があります。小規模な整備工場や地域密着型の事業者に多い工場の形態です。
●指定工場
指定工場とは、自社内で車検の検査を実施できる工場のことです。民間車検場とも呼ばれます。指定工場として認可を受けるためには、まず認証工場としての認可が必要であり、さらに厳しい基準を満たさなければなりません。検査ラインが工場内にあるため、整備から車検までを一貫して行えます。指定工場は大手のディーラーやチェーン店に多く見られ、短時間での車検対応ができるのが強みです。
自動車整備業の特色
自動車整備業の大きな特徴は、その業態が「専業」「兼業」「ディーラー」「自家」の4つに分類される点です。それぞれの業態に応じて、提供するサービスや事業モデルが異なります。
●専業
全売上の50%以上が整備業務によって成り立っている事業者です。整備業務に特化した工場が多く、主に車検整備や定期点検など、専門的なメンテナンスを行います。
●兼業
整備業の売上が総売上高の50%未満であり、自動車販売や保険など、ほかの事業と併せて整備業を行う事業者です。ガソリンスタンドやカー用品店などがこの業態に該当します。
●ディーラー
自動車メーカーと特約販売契約を結んでいるディーラーが運営する整備工場です。新車の販売に併せて、定期点検や修理サービスも提供します。指定工場が多く、メーカーの基準に基づいた高度なサービスが特徴です。
●自家
タクシー会社や運送会社、バス会社などが自社で保有する車両のメンテナンスを行うために設置された工場です。外部の顧客を受け入れることは少なく、自社の車両維持のみを目的としています。
自動車整備業の市場規模

令和6年度の「自動車特定整備業実態調査結果」によると、2024年の自動車整備業界の総売上高は6兆2,561億円に達しました。前年度と比べて約5.9%の増加で、3年連続の成長を示した数字です。市場は自動車の車検や定期点検整備に支えられており、整備需要が安定しているのが背景にあります。
業態別の売上高をみると、ディーラーが2兆9,743億円と全体の約48%を占め、続いて専業が2兆2,483億円、兼業が7,716億円、自家が2,619億円です。ディーラーの優位性は、メーカーとの直接的な取引による技術力や設備の優位性にあるとされています。また、2024年の時点での事業者数は92,384社と報告されました。
(出典:一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会「令和6年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について」https://www.jaspa.or.jp/Portals/0/resources/jaspahp/member/data/pdf/R06jittaityousa.pdf )
しかし、日本は人口減少や高齢化、若者の車離れが進んでおり、将来的な車検需要の減少が予想されている状況です。特に、少子高齢化による運転免許返納の増加や自動車保有台数の減少は、市場全体に大きな影響を与えるでしょう。さらに、電動化や技術革新の影響も無視できません。競争が激化する中で安定した成長を続けるには、さらなる変革が求められます。
自動車整備業の動向
自動車整備を担う事業者の市場撤退が加速しており、2024年度(2024年4月〜2025年3月)に発生した「自動車整備」事業者の休廃業・解散(廃業)は382件となり、過去最多を更新しています。前年度(334件)から約15%増加したほか、倒産(負債1000万円以上、法的整理)に至った63件を含めると、過去最多となる445件が自動車整備の現場から消滅しました。
自動車整備業界では近年、パーツ仕入価格や人件費の高騰、少子高齢化による自動車ユーザー減少、整備士不足による受注制限など、厳しい経営環境に直面する事例が増加している。2024年度の損益状況では、26.2%が赤字となり、「減益」を含めた「業績悪化」企業の割合は52.9%と半数を超えました。特に、整備士不足が業績に深刻な影響を与えており、若年層の整備士志望者減少と高齢化が進んだことで人手不足が慢性化し、納期遅延や受注台数の制限を余儀なくされるケースが目立ちました。
足元では、大手自動車メーカーが整備士教育で連携を始めたほか、全国の自動車車体整備事業者で構成される日車協連と大手損保の東京海上日動火災保険が整備代金の単価引き上げに合意するなど、整備事業者の経営環境改善に向けた取り組みに注力しています。ただ、整備士の不足や新車の販売不振などで顧客基盤が先細りするリスクが残るほか、整備ニーズの質的変化にも対応が必要となるなど課題も多く、こうしたニーズに対応できない自動車整備業者で淘汰がさらに進む可能性もあります。
(出典:株式会社帝国データバンク「「⾃動⾞整備事業者」の倒産、休廃業・解散動向」https://www.tdb.co.jp/resource/files/assets/d4b8e8ee91d1489c9a2abd23a4bb5219/5c2507901ce545a1964b8713bb87d134/20250504_%E3%80%8C%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%95%B4%E5%82%99%E3%80%8D%E5%80%92%E7%94%A3%E3%83%BB%E4%BC%91%E5%BB%83%E6%A5%AD%E8%A7%A3%E6%95%A3%E5%8B%95%E5%90%91%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%882024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%89.pdf )
自動車整備業のM&A動向|活発化する理由は?

自動車整備業界では、近年M&Aが活発化している状況です。自動車整備業同士のM&Aが特に目立ちますが、隣接業種や異業種による参入も増えつつあります。これにより、地域に根ざした中小企業が、大手企業の傘下に入るケースも増えてきました。
自動車整備業のM&Aが活発化している背景には、以下のような要因があります。
新規参入の難しさ
自動車整備業への新規参入は、そもそも容易ではありません。自動車の整備を行うには、工場設備の確保もさることながら、国家資格である整備士の確保が必須であり、これが新規参入の大きな壁となっています。さらに、整備士を育成する専門学校への進学者数も減少傾向にあり、資格を持つ整備士の絶対数が少ない状況です。
そのため、新たに事業を立ち上げるよりも、既存の整備工場をM&Aで獲得するほうが効率的だと考えられています。運輸局からの認可や、整備工場の設備を一度に取得できる点も、M&Aを選ぶ理由の1つです。
経営者の高齢化などによる後継者の不在
自動車整備業界では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっています。経営者の平均年齢は60歳を超えており、多くの事業者が引退を考える時期に差しかかっています。しかし、若者の自動車離れや少子化の影響で、後継者が見つからないケースが少なくありません。
帝国データバンクの「自動車整備事業者の倒産、休廃業・解散動向」によると、2023年における自動車整備業の後継者不在率は59.7%と、半数を大きく上回りました。このような状況から、事業の存続をM&Aによる第三者承継で解決する動きが広がっています。
(出典:株式会社帝国データバンク「「⾃動⾞整備事業者」の倒産、休廃業・解散動向」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p240806.pdf )
電気自動車の進歩に伴う新たな設備投資の必要性
自動車整備業界においては、電気自動車(EV)やハイブリッド車の普及が進んでおり、これに対応するための設備投資が不可欠です。従来の内燃機関車両と異なり、EVはバッテリーや電子制御システムが重要な部分を占めているため、整備に必要な技術や機器も大きく変化しました。
そのため、最新の設備を導入する資金力のない中小整備工場は、新たな設備投資が負担となり、事業継続が難しくなるケースが増えています。こうした背景から、大手企業が中小企業をM&Aで吸収し、設備投資を効率化する動きが見られるようになりました。
企業の生き残りをかけた多角化・整備内製化の必要性
近年は、労働人口の減少や若者の車離れにより、自動車整備の需要も低下しつつあります。そのため、従来の設備のまま単一の整備業務に依存するだけでは、今後の長期生存は難しいと言えるでしょう。
多くの企業が新たな収益源を確保するために、自動車や自動車部品の販売、保険代理業務、カーシェアリングなど、事業の多角化を進めています。また、外部に依頼していた自動車整備を自社で行う「整備内製化」によって、コスト削減や効率化を図る動きも増えてきました。
こうした多角化や整備内製化を目的とした、隣接業種・異業種によるM&Aも活発化しています。
【自動車整備業】M&Aによる立場ごとのメリット

自動車整備業におけるM&Aは、譲渡側(売り手)と譲受側(買い手)の双方に多くのメリットをもたらします。譲渡側にとっては、後継者問題や事業の継続に関する課題を解決できる点、譲受側にとっては、貴重な人材や設備を迅速に獲得できる点が代表的です。
ここからは、M&Aの実施による具体的なメリットを、立場ごとに紹介します。
「譲渡(売り手)側」のメリット
M&Aで自動車整備工場を売却する譲渡側には、主に以下のようなメリットがあります。
- 後継者問題の解決
- 従業員の雇用維持
- 事業の継続と地域貢献
- 資金の確保
- 経営者の負債からの解放
譲渡側の最大のメリットは、後継者不在という深刻な問題を解決できる点です。特に経営者が高齢化している場合、M&Aによって後継者を外部から確保することで、事業の継続が可能となります。廃業を避けられれば従業員の雇用を守れるだけでなく、取引先との関係も維持されるでしょう。
また、売却益を得ることで、引退後の生活資金や新たな事業展開に資金を充てることも可能です。特に大手企業に買収される場合は資金力やブランド力の活用もでき、地域への貢献や事業のさらなる発展が見込まれます。
さらに、買い手が負債を引き継ぐ株式譲渡による事業承継を行えば、経営者の個人保証や担保の差し入れが解消されるのもメリットです。これは経営者にとって大きな負担軽減となり得ます。
「譲受(買い手)側」のメリット
M&Aで自動車整備工場を買収する譲受側には、次のようなメリットがあります。
- 整備士など貴重な人材の確保
- 設備と認可を一度に取得
- 事業規模の拡大とエリアの拡張
- 低コストでの新規参入
- 収益基盤の強化
買い手にとっての大きなメリットは、整備士のような必須資格保有者を一度に確保できる点です。自動車整備業界では整備士不足が深刻化しており、資格を持つ人材のスムーズな確保は事業運営において重要な要素となっています。
さらに、運輸局から認可を受けた設備や工場もまとめて取得できるため、初期投資を抑えつつ迅速な整備事業の開始が可能です。
同業者が買収する場合は、事業規模を拡大したり新たなエリアに進出したりする動きが容易になります。異業種からの買収であれば、M&Aを通じて低コストで整備業界への新規参入が実現するでしょう。
これにより、整備業務の内製化が進み、外部委託コストの削減や収益基盤の強化が図られます。結果的に、買い手側の企業は迅速に競争力を強化でき、長期的な成長を目指しやすくなるのがメリットです。
自動車整備業における主なM&A事例3選
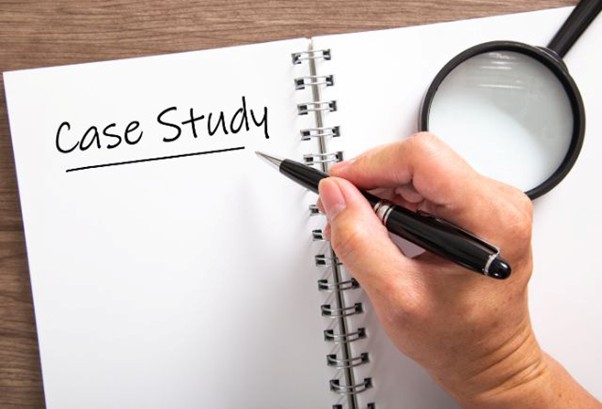
自動車整備業におけるM&Aは、特に後継者不足に悩む事業者や競争激化へ迅速に対応したい事業者に効果的な解決策となるでしょう。自動車整備業界におけるM&Aを成功させるには、事例を参考にするのも有効です。
次に、業界でも注目された3つのM&A事例を紹介します。
株式会社オートバックスセブン×近藤自動車工業株式会社
オートバックスセブンは2024年5月、近藤自動車工業株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 近藤自動車工業株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社オートバックスセブン |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡(完全子会社化) |
オートバックスセブンは、カー用品の販売や車検・整備などを行う企業として知られています。近藤自動車工業は、車両整備や販売、リース事業を展開しており、地域に根ざした事業基盤を持つ企業です。
このM&Aの目的は、オートバックスグループが掲げる「次世代技術に対応する整備ネットワーク」の強化にあります。新たな整備事業者との提携により、顧客接点を増やし、収益基盤の拡大を目指しました。
SPK株式会社×株式会社デルオート
2021年12月、SPK株式会社は、株式会社デルオートの全株式を取得し、完全子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社デルオート |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | SPK株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
SPKは自動車部品の企画・販売を行う企業で、デルオートはトランスミッションの修理やリビルト事業、自動車整備を手掛ける企業です。 このM&Aの主な目的は、両社が保有する自動車関連事業の連携によるシナジー効果を追求し、補修アフターマーケットでの事業拡大を図ることです。
株式譲渡により、 SPKはデルオートをグループに取り込み、新たなモビリティ事業の立ち上げを目指しています。整備士の技術力と部品供給の強化などが期待されます。
D&Dホールディングス×室蘭ダイヤモータース株式会社
2021年12月、D&Dホールディングスは室蘭ダイヤモータース株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 室蘭ダイヤモータース株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | D&Dホールディングス |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡(完全子会社化) |
D&Dホールディングスは、三菱自動車のディーラーとして自動車販売や整備事業を展開しています。室蘭ダイヤモータースは、三菱車の販売および整備を行う企業です。 このM&Aの目的は、D&Dホールディングスが持つ既存の札幌・旭川エリアの事業と室蘭ダイヤモータースのビジネスを掛け合わせることです。特にレンタカー需要が高い北海道の特性に対応したビジネス展開が重視されており、北海道全域でのさらなる事業拡大が期待されます。
自動車整備業のM&Aを成功させるためのポイント

自動車整備業のM&Aを成功させるためには、売り手と買い手それぞれの立場で戦略的な計画と準備が必要です。以下は、双方の立場で成功を収めるための具体的なポイントです。
【「譲渡(売り手)側」のポイント】
- 事前の準備と計画を入念に行う
- 自社の強みや整備士数を資料として整理する
- 契約成立まで情報を外部に漏らさない
- 専門家に相談する
M&Aを成功させるためには、まず自社の現状を把握した上で計画を練ることが重要です。特に、整備士の人数や設備状況など、自社の強みを整理して相手にアピールする力が求められます。
また、従業員や取引先に対して情報をどのタイミングで伝えるかも慎重に考えなければなりません。契約成立前に情報が漏れると、従業員の不安を煽ったり、取引先との関係が悪化したりする可能性があります。情報管理には十分な注意が必要です。
【「譲渡(買い手)側」のポイント】
- 有資格者(整備士)の確保状況を確認する
- 売却側の財務状況を詳細に調査する
- 将来の収益性を見極める
- 地域特性や顧客基盤を考慮する
買い手側の最大のポイントは、有資格者である整備士の人数や年齢構成を把握することです。特に若手整備士が多く在籍している企業は、将来の成長を見込める優れた投資対象となります。
また、財務状況の確認も重要です。借入金や負債の多さが事業運営にどのような影響を与えるかを慎重に検討しなければなりません。適正な買収価額を決めるために、デューデリジェンスを徹底的に行いましょう。 さらに、事業エリアの特性や顧客基盤が自社にとってどのような付加価値を生むかを考慮し、成長の可能性を見極めることが大切です。
売り手側と買い手側の双方が、M&Aの目的を明確にし、譲れない条件をしっかり設定することが成功のカギを握ります。事業承継や事業拡大を目的とする場合でも、相手のニーズや条件に対して柔軟に対応する姿勢が大切です。
M&Aは複雑な手続きが絡むため、専門的な知識を持つ仲介会社への相談をおすすめします。専門家のサポートを受けることで、最適な相手とマッチングしやすくなり、複雑な手続きも円滑に進むでしょう。
まとめ
自動車整備業のM&Aは、後継者不足や電気自動車の普及による技術革新、新規参入の難しさなどの背景から、近年ますます活発化しています。売り手側は後継者問題の解消や事業の継続、買い手側は人材や設備の獲得、新規事業の拡大を実現しやすいのが大きなメリットです。
M&Aを成功させるには、譲渡や譲受の目的を明確にした上で、双方がしっかりと準備を整えなければなりません。専門的な知識を持つ仲介会社に相談しながら進めることで、M&Aの成功確率を高められるでしょう。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00