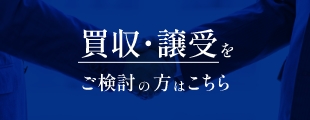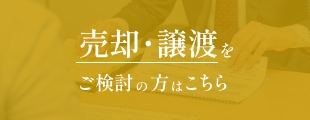平日9:00〜18:00

銀行業界のM&A動向
業界別M&A
銀行業界は、資金の流通や企業活動を支える基盤として経済の安定や成長に直結するだけでなく、企業の発展や産業再編においても欠かせない存在です。
近年は産業構造や社会の変化を背景に、さまざまな業界でM&Aが活発化しています。銀行業界は企業同士のM&Aをサポートする役割を果たしつつ、自らも経営統合や提携を通して業界再編を進めてきました。
そこで今回は、銀行業界の変遷や直面する課題、M&Aの代表的なスキームと主な事例、さらに成功のポイントについて詳しく解説します。
-
銀行業界とは?
-
銀行はM&Aの相談先の1つ|相談先としての主な役割
-
バブル崩壊から現在までの銀行業界の変遷
-
銀行業界のM&Aにおける代表的なスキーム
-
【立場別】銀行業界のM&Aによるメリット
-
銀行業界の主なM&A事例3選
-
銀行業界のM&Aを成功させるポイント
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
銀行業界とは?

銀行業界とは、預金や融資、為替取引といった金融サービスを通して、資金の流通を支える役割をもつ産業です。金融業界の一種であり、個人・法人の双方にとって身近で欠かせない存在となっています。
銀行業界の業態としては、全国規模で展開する都市銀行や地域に密着した地方銀行、資産運用に強みをもつ信託銀行のほか、実店舗をもたないネット銀行やデジタルバンクも台頭しています。
また、地域や組合員を対象とする信用金庫・信用組合・労働金庫も銀行業界に含まれ、幅広い形態で社会の金融ニーズに応えています。このように、銀行業界は経済や人々の生活に関係するさまざまな金融機関によって構成されているのが特徴です。
銀行はM&Aの相談先の1つ|相談先としての主な役割

銀行は、主に個人や法人に対して預金・融資・投資信託など幅広い金融商品を提供し、資金面のサポートを行っています。加えて、企業の成長戦略や事業承継の手段として活用されるM&Aに関しても重要な役割を担っています。
M&Aの実行には、資金調達や企業価値の評価、条件交渉といった専門的なプロセスが必要であり、これらを適切に進めるためには相談先の存在が欠かせません。
銀行は日常的に取引先企業の財務状況を把握していることから、M&Aの相談先として信頼性が高く、経営者にとっても身近で心強い存在と言えるでしょう。
ここでは、企業のM&Aにおいて銀行が果たす代表的な役割を2つ紹介します。
資金融資
M&Aを進める際には、買収資金や統合後の運転資金など多額の資金が必要です。銀行は融資やローンといった形で資金を供給し、買い手企業のM&A実行を支援します。
特に、銀行は取引先企業の財務内容や業績を把握しているため、リスク評価に基づいた柔軟な融資判断を行える点が強みです。
また、信用力の高い銀行からの融資は売り手にとっても安心材料となり、交渉をスムーズに進める効果があります。さらに、M&A後の設備投資や人材採用にかかる追加資金の調達も支援できるため、銀行は単なる資金提供者にとどまらず、取引全体を支える存在と言っても過言ではありません。
M&Aアドバイザリー
銀行は融資だけでなく、M&Aの企画から実行までをサポートするアドバイザリー業務も担っています。具体的には、買収候補企業の選定、企業価値の算定、条件交渉のサポートなど、多岐にわたる業務を行います。
銀行は幅広い顧客ネットワークを有しており、これを活かして売り手・買い手双方のマッチングを行える点も大きな強みです。また、税務や会計の専門家とも連携し、取引スキームの最適化やリスク軽減の提案も可能です。
特に、地方銀行などは地域に密着したネットワークをもっており、中小企業の事業承継や地域産業の再編におけるM&Aではより大きな役割を果たします。
バブル崩壊から現在までの銀行業界の変遷

銀行業界の現在の市場動向や直面する課題を理解するためには、まず業界の歴史的背景を振り返る必要があります。
日本経済は1990年代初頭のバブル崩壊によって大きな転換点を迎えました。地価や株価の下落に伴い不良債権が膨らみ、銀行は経営危機に直面しました。その後、政府主導での金融システム改革、いわゆる「金融ビッグバン」が進められ、規制緩和によって業界再編が加速しました。
1997年には独占禁止法が改正され、銀行持株会社の設立が可能となったことで、都市銀行や地方銀行の合併・グループ再編が一気に進展しました。
これにより、かつて十数行あった都市銀行は再編を繰り返し、現在ではメガバンク3グループ(「三菱UFJフィナンシャル・グループ」「三井住友フィナンシャルグループ」「みずほフィナンシャルグループ」)へと集約されています。
さらに2000年代以降は、インターネットの普及を背景に、実店舗を持たないネット銀行やデジタルバンクの登場、証券会社や通信会社など異業種からの参入も相次ぎました。銀行業界は伝統的な枠組みにとどまらず、多様な金融サービスを提供するプレーヤーが混在する構造へと変化しています。
| 【2024年9月末の業態別金融機関数】 | |
|---|---|
| 業態 | 金融機関数 |
| 都市銀行 | 5 |
| 地方銀行 | 62 |
| 第二地方銀行 | 37 |
| 信託銀行 | 3 |
| その他銀行 | 15 |
(出典:株式会社日本金融通信社「最新の業態別金融機関数」https://www.nikkin.co.jp/link/number.html )
銀行業界を取り巻く最新の市場動向
銀行業界は現在、人口減少や高齢化といった社会構造の変化によって大きな影響を受けています。特に地方経済の縮小に伴い、地方銀行の貸出需要は減少傾向にあり、収益基盤の維持が難しくなっています。
加えて、日銀による長期的な低金利政策は銀行の資金利益を圧迫しています。国債の利回り低下や貸出金利の下落により、利ザヤが確保しづらい環境が続いており、従来の「貸出で稼ぐ」ビジネスモデルは限界を迎えつつあります。
さらに、フィンテックやデジタルサービスの普及によって、クラウドファンディングやオンライン融資といった資金調達手段が多様化しました。これにより、銀行の存在意義そのものが揺らぎつつあります。
都市銀行は海外進出や高度な金融商品提供といった戦略に活路を求めていますが、地域銀行については明確な成長戦略を描けず、厳しい状況に直面しています。
銀行業界が直面する主な課題
市場環境を踏まえると、銀行業界が直面する最大の課題は「持続的な収益基盤の確立」です。特に地方銀行は、人口減少や地域経済の縮小による貸出需要の減退に対応するため、再編や経営統合の必要性が高まっています。
経営資源を強化するための手段には、合併・経営統合・資本提携・業務提携など複数の選択肢があります。規模を拡大することでシステム投資や人材活用を効率化できる一方で、統合に伴う文化の違いやガバナンス上のリスクも存在します。そのため、単なる規模拡大にとどまらず、独自の強みを活かした戦略をいかに確立できるかが競争力を左右します。
特に地方銀行は、地域密着型の強みを活かしつつ、新しいビジネスモデルを構築することが急務です。デジタル技術を活用したサービス提供や、地域企業との連携による新事業の創出など、独自戦略をいかに築けるかが今後の成否を分けるポイントとなるでしょう。
銀行業界のM&Aにおける代表的なスキーム

銀行業界は、金融庁による規制・監督の下で事業運営が行われているほか、地域密着性や市場シェアに関する制約もあることから、一般企業のM&Aとは異なる特徴をもちます。
特に銀行同士の再編や統合においては、金融システムの安定性や顧客利便性の確保といった観点が重視されるため、スキームの選択や進め方にも独自の傾向が見られます。
ここからは、銀行業界において代表的に用いられる3つのスキームを解説します。
合併
合併とは、2つ以上の銀行が1つの法人に統合されるスキームで、既存の銀行が存続して相手を取り込む「吸収合併」と、新たに法人を設立して統合する「新設合併」があります。銀行のM&Aでは主に都市銀行による吸収合併が多く見られ、規模の拡大を通じてシナジー効果を追求するケースが一般的です。
合併のメリットは、経営資源の統合によるコスト削減、競争力の強化、そして顧客基盤の拡大です。特にITシステムや店舗網を一元化することで、大幅な効率化を実現できる可能性があります。
しかし一方で、銀行は組織文化やシステムが複雑であるため、統合時に文化の不一致や大規模なシステム障害といったリスクが発生しやすい点も否めません。実際に過去には、大手銀行の合併に伴い大規模障害が発生した事例もあり、統合プロセスの難しさが浮き彫りとなっています。
持株会社方式による経営統合
持株会社方式による経営統合とは、複数の銀行が共同で銀行持株会社を設立し、それぞれの銀行がその傘下に入る形で段階的に統合を進めるスキームです。近年では特に地方銀行の間で多く採用されており、地域経済の縮小に対応する再編の一環として用いられています。
持株会社方式による経営統合の特徴は、各行の独自性を一定程度残しながら統合を進められる点です。例えばブランド名や営業スタイルを維持したまま、持株会社のもとで資本や経営資源を共有できるため、急激な変化を避けながら協力体制を築くことが可能です。
その一方で、システム統合や業務プロセスの一本化には時間がかかりやすく、経営効率化のスピード感や即効性に欠ける側面もあります。また、経営の意思決定においてガバナンスが複雑化しやすく、統合効果を最大限に発揮できないリスクも指摘されています。
資本提携・業務提携
資本提携や業務提携も、銀行業界のM&Aで多く見られるスキームです。
資本提携は、出資比率を通じて資本関係を構築するもので、広義にはM&Aに含まれることもありますが、経営権の移動を伴わないため狭義のM&A(企業の買収・合併)とは区別されます。そして業務提携は、資本の移動を伴わずに特定分野で協力関係を築くものであり、厳密にはM&Aには該当しません。
資本提携と業務提携は地方銀行同士で活用されるケースが多く、完全統合には至らないものの、相互補完によるメリットを享受できます。例えば投資信託や保険商品の共同開発、システム基盤の共同利用、人材育成における協力などが代表的です。
資本提携・業務提携のメリットは、フルスケールの統合に比べて柔軟性が高く、リスクを抑えながら協力できる点にあります。ただし、緩やかな連携にとどまるため、抜本的な競争力強化や収益改善には限界があることにも注意が必要です。
【立場別】銀行業界のM&Aによるメリット

銀行業界のM&Aでは、譲渡(売り手)側と譲受(買い手)側の双方にそれぞれメリットがあります。
主に、売り手は自社の強みや資産を活かしながら経営基盤の安定化や成長機会の拡大が期待でき、買い手は規模拡大や事業領域の強化を通じて競争力や収益性を高めることが可能です。
ここからは、銀行業界のM&Aによる売り手側・買い手側それぞれのメリットを具体的に整理します。
譲渡(売り手)側のメリット
売り手側にとってM&Aは、経営基盤を強化しながら将来の成長機会を広げる手段となります。具体的なメリットは、下記の通りです。
- 顧客ネットワークの価値向上
- 経営の安定化とリスクの分散
- サービスの充実と質向上
- 協働による成長
統合先の銀行との連携によって顧客基盤が拡大すると、既存顧客へのサービス提供価値が高まります。また、経営資源を統合することで、単独経営では負担となるリスクやコストを分散できます。加えて、共同での資金運用や金融商品の開発により、顧客向けサービスの幅と質が向上するほか、新たな事業機会の創出にもつながるでしょう。
譲受(買い手)側のメリット
買い手側にとってM&Aは、規模拡大や事業領域の強化を通じて、競争力や収益性を高める手段となります。具体的なメリットは、下記の通りです。
- 運営コストの削減
- 人材の強化
- サービス領域の拡大
- ノウハウの共有
- 財務力の向上
統合によってシステムや人員の効率化が進み、運営コストを削減できます。また、相手銀行の専門人材を取り込むことで組織力や専門性を高めることが可能です。さらに、サービス提供の範囲拡大や、業務プロセス・ノウハウの共有などで運営力全体が向上し、資本基盤の強化により将来的な投資や事業拡大の余地も広がるでしょう。
銀行業界の主なM&A事例3選

銀行業界のM&Aを成功させるためには、まず銀行業界における過去のM&A事例をチェックするのが有効です。他社が実際にどのような取り組みを行ったかを参考にすることで、自社に適したM&Aの目的や手法をイメージしやすくなるでしょう。
ここからは、銀行業界における主なM&A事例を3つ紹介します。
株式会社青森銀行×株式会社みちのく銀行
株式会社青森銀行は、2025年1月1日に株式会社みちのく銀行を吸収合併し、新たに「青森みちのく銀行」としてスタートしました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社みちのく銀行 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社青森銀行 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 吸収合併 |
青森銀行は、青森県を中心に展開する地方銀行で、地域密着型の金融サービスを提供しています。みちのく銀行は、青森県内で広範なネットワークを有する地方銀行で、地域経済の発展に寄与してきました。
両行は当M&Aで、リソースの統合による地域経済の活性化とサービスの質向上を目指しています。
三井住友信託銀行株式会社×東京証券代行株式会社・日本証券代行株式会社
三井住友信託銀行株式会社は、2025年1月1日に東京証券代行株式会社と日本証券代行株式会社を吸収合併しました。
| 譲渡(売り手)側 |
|
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 吸収合併 |
三井住友信託銀行は、信託業務を中心に幅広い金融サービスを提供する大手信託銀行です。銀行事業のほか、資産運用・管理事業や不動産事業も手がけています。東京証券代行株式会社と日本証券代行株式会社は証券代行業務を専門とする企業で、株主名簿管理や議決権行使等の業務を行っています。
当M&Aでは、3社の経営資源を結集させることで証券代行業務の効率化を図るとともに、各種サービスの質向上やデジタル化の推進も目指しています。
株式会社りそなホールディングス×株式会社関西みらいフィナンシャルグループ
株式会社りそなホールディングスは、2024年4月1日に株式会社関西みらいフィナンシャルグループを吸収合併しました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社りそなホールディングス |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 吸収合併 |
りそなホールディングスは、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行を傘下に持つメガバンクです。関西みらいフィナンシャルグループは、銀行持株会社としてグループの経営管理等を行っている企業です。
当M&Aは、グループガバナンスの強化と最適な組織体制の構築を図ることを目的に実施されました。
銀行業界のM&Aを成功させるポイント

最後に、銀行業界のM&Aを成功させるためにおさえておくべきポイントを紹介します。
●事前準備とリスク分析を徹底する
銀行の統合にはシステム統合や法令遵守、文化の違いなど、特有のリスクが多く存在します。円滑な統合を実現するためには、合併や持株会社方式による経営統合など選択するスキームに応じてリスクを事前に分析し、適切な対応策を準備しておくことが重要です。
●必要に応じて外部専門家からのサポートを受ける
銀行はM&Aに関するノウハウを豊富に有していますが、特定の案件や法務・会計・税務など専門性の高い分野においては、外部のM&Aアドバイザーやコンサルタントと連携することで、成功確度をより高めることが可能です。M&Aをスムーズに進めるためにも、アドバイザーといった外部の専門家からのサポートを受けることをおすすめします。
まとめ
銀行業界は、預金や融資、為替取引などの金融サービスを通じて資金の流通を支える産業で、企業や地域経済の基盤としての重要な役割を担っています。
経営統合や提携を目的としたM&Aが活発化する近年、M&Aのサポートを行う銀行自身でもM&Aが多く実施されています。銀行M&Aの主なスキームとしては合併や持株会社方式による経営統合、資本提携・業務提携などがあり、それぞれの目的や特徴に応じた統合が行われています。
銀行M&Aを効率的かつ安全に進めるには、事前のリスク分析や外部専門家との連携が不可欠です。M&A助言会社である株式会社レコフは、M&Aの計画から実行まで幅広くサポートしております。戦略的な統合を検討する際の相談先をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00