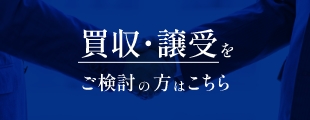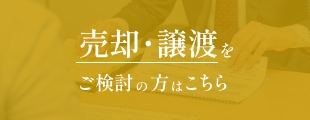平日9:00〜18:00

証券業界のM&A動向
業界別M&A
証券業界は、企業や個人の資産運用を支える重要な役割を担っており、経済活動の活性化において不可欠な存在です。株式・債券の売買仲介だけでなく、近年ではコンサルティング業務やデジタル証券の取り扱いなど、提供するサービスも多様化しています。
証券業界では、こうした経営環境の変化や競争激化に対応するため、M&Aによる再編や成長戦略が注目を集めています。特に、デジタル化やフィンテックとの連携を軸とした動きが加速しています。
そこで今回は、証券業界の基本的な構造や現状・課題から、具体的なM&Aの動向や事例、成功のポイントまでを分かりやすく解説します。
-
証券業界とは?
-
証券業界の市場動向
-
証券業界が抱える構造的課題
-
証券業界のM&A動向
-
証券業界のM&Aによるメリット&デメリット
-
証券業界の主なM&A事例3選
-
証券業界のM&Aを成功させるポイント
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
証券業界とは?

証券業界とは、企業や個人に対して株式・債券・投資信託などの金融商品を提供し、資産形成や資金調達を支援する業界です。
企業にとっては、証券会社を通じて資金を市場から調達できる手段を得られ、個人にとっては長期的な資産形成や投資運用の機会を得る場となります。金融商品取引法においては「第一種金融商品取引業」に分類されており、経済全体の資金循環を支える重要な役割を果たしています。
証券業界に属する企業の中心は、証券会社です。証券会社は、株式や債券の売買仲介をはじめ、自己勘定での取引(ディーリング)、資金調達支援(引受業務)、投資銀行業務、資産運用アドバイスなど、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
証券会社の主な種類
証券会社とひとくちに言っても、その規模・資本力・サービス内容・所属母体などによって、いくつかの分類が存在します。ここでは、日本国内で見られる証券会社の主な5つの種類について紹介します。
●大手独立系
資本系列に属さず、他社と資本関係を結ばずに独自の戦略で総合的な証券サービスを展開する証券会社です。国内外の企業を顧客にもち、M&AやIPO、引受業務にも強みをもっています。
●銀行系
メガバンクなどのフィナンシャルグループに属し、銀行との連携によって幅広い顧客基盤と信用力を有する証券会社です。個人向け資産運用サービスや企業向けソリューションにも強みをもっています。
●準大手・中堅系
地域密着型のサービスや特定分野に特化したビジネスで差別化を図る証券会社です。大手独立系や銀行系に次いで規模が大きく、地場企業や中小企業とのつながりを強みにしています。
●外資系
外国法人が一定以上の割合で出資する、海外の大手金融グループに属した証券会社です。グローバルな金融ネットワークと豊富な国際業務経験を背景に、高度な金融技術や商品を提供しています。
●ネット系
対面式の営業店は設置せず、オンライン取引に特化した証券会社です。スマートフォンやPCを通じた取引サービスが主力となります。低コスト・利便性の高さが特徴で、若年層や初心者の投資家に人気を集めています。
証券業界の市場動向

近年の証券業界では、テクノロジーの進展やフィンテック企業の台頭によって投資環境にも変化が生じています。これにより証券業界のビジネスモデルやサービスの在り方も変わりつつあり、各社はそれぞれの強みを活かしながら市場での競争力を高めています。
日本証券業協会の「FACT BOOK 2024」によると、全国261社の証券会社の2023年度決算における営業収益は約5.4兆円と、前期比で29.4%増加しました。好調な背景としては、「新NISA制度の導入」や「株式市場の好調さに伴う投資需要の拡大」があります。
ただし、海外経済の不透明感は依然として強く、今後も業界の変化に対する柔軟な経営が求められています。
(出典:日本証券業協会「FACT BOOK 2024」https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/factbook/files/FactBook2024_J.pdf )
証券業界が抱える構造的課題
証券業界では、社会構造の変化やテクノロジーの進化により、従来のビジネスモデルの見直しが迫られていることが実情です。顧客離れや収益力の低下に直結するおそれもあるため、各社には柔軟かつ迅速な対応が求められています。
ここでは、証券業界が直面する主な3つの構造的課題について詳しく紹介します。
競争激化に伴うビジネスモデルの見直し
証券業界では、ネット証券や外資系証券など多様な事業者の参入によって、競争が一段と激化しています。特に、低コストで利便性の高いネット証券の成長は、従来の対面型営業スタイルに依存してきた証券会社にとって大きな脅威です。 業界全体で株式売買手数料による収入が減少傾向にある中、従来型のビジネスモデルからの脱却は急務とされており、多くの企業が株式取引中心の収益構造から預かり資産の残高に応じた運用支援型ビジネスへの転換を模索しています。
今後は単なる取引の仲介だけでなく、コンサルティング的価値の提供も重要となるでしょう。
少子高齢化による顧客層と需要の変化への理解・対応
日本の証券業界では、少子高齢化の進行によって顧客層とそのニーズに大きな変化が生じています。 高齢の顧客は安定志向が強く、リスクを避けた運用を求める傾向があり、従来の株式中心のサービスでは対応が難しくなっています。一方で、若年層は投資への関心は高まっているものの、実際の投資行動に結びつかないケースも多く、アプローチが課題です。
顧客層と需要の変化に対応するためには、ライフステージに応じた柔軟な商品設計や、新たな投資スタイルに応えるサービスの開発が欠かせません。特に、少額から始められる投資信託やロボアドバイザーなど、新規顧客の獲得に向けた「初心者でも利用しやすい仕組みの整備」は重要です。
また、デジタル世代向けの教育や情報提供の工夫も、将来的な顧客基盤の形成において大切な要素となるでしょう。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の迅速な対応
近年の証券業界では、オンライン取引の普及やフィンテック企業の台頭により、業界全体に大きな変革が求められています。従来型の対面営業だけでは競争力を維持することが難しくなりつつあり、デジタル技術を活用したサービスや業務の効率化が不可欠となっています。
特に若年層を中心に非対面取引へのニーズが高まっており、迅速なDX推進が急務です。システムの刷新やデータ活用による顧客対応力の強化などは、企業の将来を左右する重要な経営課題となっています。
DX対応が遅滞すると、顧客の流出や競合他社との差別化に失敗するリスクが高まるため、今後の成長に向けた戦略的投資が求められます。
証券業界のM&A動向

証券業界では、事業強化や競争力維持を目的としたM&Aが活発化しています。特に、大手証券会社を中心に新規事業領域の開拓や既存ビジネスの拡張を図る動きが顕著であり、業界全体が再編・成長の局面にあると言えるでしょう。
ここからは、証券業界の主なM&Aの動向について詳しく紹介します。
大手証券会社による事業強化を目的としたM&A
大手証券会社では、M&Aを通じて新規事業の開拓や収益構造の強化を図る戦略が広がっています。
特に海外案件への対応力や資本力を活かした大規模な買収・出資が進んでおり、マネジメント・バイアウト(MBO)の支援やファンド運用の強化など、付加価値の高い取引が増加傾向にあります。
また、メガバンクグループがグループ内再編や証券会社の統合を通じて、銀行・証券一体の総合金融サービス体制を構築するケースも増えており、M&Aは中核的な成長戦略の一環となっています。
地域証券会社による統合・再編を目的としたM&A
地方証券会社では、人口減少や営業基盤の縮小に対応するための業界再編や統合が進められています。 収益力や人材確保に課題を抱える中小規模の証券会社にとって、M&Aは経営の持続可能性を高める手段となっており、同業他社との合併や大手による買収が相次いでいます。
地域証券会社による業界内統合は、営業エリアの拡大や業務効率化だけでなく、デジタル対応や新サービスへの対応力強化にもつながっています。
フィンテック企業との連携強化を目的とした隣接業種間のM&A
近年、証券業界ではフィンテック企業との提携や買収を通じた業務改革も進んでいます。
AIやビッグデータを活用した投資助言、ロボアドバイザーの導入など、デジタル技術との融合が競争力を左右する要素となっており、非金融業界との連携も含めたM&Aが活発化しています。
また、不動産・保険・IT分野など異業種企業の証券業界参入も進んでおり、サービスの垣根が曖昧になる中で、金融プラットフォームとしての進化を遂げる企業も登場しています。
証券業界のM&Aによるメリット&デメリット

証券業界におけるM&Aは、経営資源の補完や競争力強化、新たなサービス創出などを目的に多くの企業が取り組んでいます。しかし、多くのメリットが期待できる一方で、いくつかのデメリットやリスクがあることも理解しておかなければなりません。
そこで次に、証券業界のM&Aにおける主なメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。
メリット
証券業界におけるM&Aは、各社がもつ経営資源を掛け合わせることで、企業価値の向上や競争優位性の確保を目指す動きとして注目されています。特に環境変化の激しい金融市場においては、M&Aは戦略的な成長手段として活用されています。
- 経営基盤・資本力の強化による財務安定性の向上
- 企業規模の拡大による収益力・競争力の向上
- フィンテック分野などの新規事業や新サービスの獲得
- 顧客基盤の拡充や取引先の多様化による市場シェア拡大
- 業界再編による業務効率の向上とコスト削減
- 優秀な人材やノウハウの獲得による組織力強化
M&Aは短期的な収益改善だけでなく、長期的な成長の布石ともなります。特に異なる得意分野をもつ企業同士が統合することで、互いの弱みを補完し合える点が強みです。経営リソースの相乗効果が発揮されれば、単独では実現し得ない新たなビジネスチャンスの獲得も可能となるでしょう。
デメリット
証券業界のM&Aには、様々なリスクや課題も存在します。統合を進める過程で想定外の問題が発生すれば、期待される成果を得られないどころか、むしろ経営の足かせとなるおそれもあることに注意が必要です。
- 企業文化や経営方針の違いによる組織内の混乱
- M&Aによる不安感から既存顧客が離脱するリスク
- 組織再編に伴う従業員の離職やモチベーションの低下
- システム統合や再編にかかる高コスト・工数の増加
- 金融庁・公正取引委員会との調整による手続き負担
これらのデメリットを軽視すると、M&A後の統合がスムーズに進まず、予定していたシナジー効果を十分に発揮できないおそれがあります。特に、企業文化の違いや従業員への配慮を怠ると、内部からの崩壊リスクも高まりかねません。
M&Aを成功させるには、統合後の組織マネジメントやリスク対応策も含めた計画が不可欠です。
証券業界の主なM&A事例3選
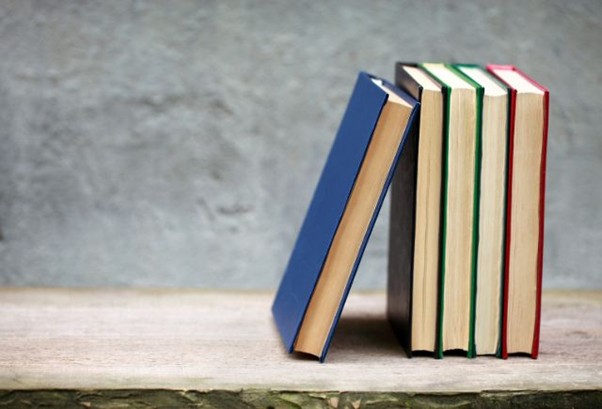
証券業界におけるM&Aを成功させるには、過去に行われた実際のM&A事例を参考にするのが有効です。事例から取り組みの内容を具体的に把握することで、自社が実施すべきM&Aの適切な方向性をイメージできるようになるでしょう。
ここからは、証券業界で実際に行われたM&Aの最新事例を2つ紹介します。
日産証券ファイナンス株式会社×NSトレーディング株式会社
日産証券ファイナンス株式会社は、同じく日産証券グループの連結子会社であるNSトレーディング株式会社を2025年7月1日付で吸収合併しました。
| 譲渡(売り手)側 | NSトレーディング株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 日産証券ファイナンス株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 吸収合併 |
日産証券ファイナンス株式会社は主に貸金業を中心に事業を展開しており、金融市場で重要な役割を担う企業です。
NSトレーディング株式会社は日産証券グループの100%子会社として2022年3月に設立された企業であり、主に自己売買事業(ディーリング業務/自己資金運用)を行っていました。
この吸収合併により、日産証券ファイナンスはNSトレーディングのリソースやノウハウを取り込み、より多角的な金融サービス提供を目指します。グループ全体の競争力強化と経営資源の効率的活用を図ることが期待されています。
コインチェック株式会社×エキサイトホールディングス株式会社
2024年3月、コインチェック株式会社は自社が展開するバーチャル株主総会運営支援サービスの「Sharely(シェアリー)」事業を会社分割により新設会社へ移管し、その新設会社の全株式をエキサイトホールディングス株式会社へ譲渡しました。
| 譲渡(売り手)側 | コインチェック株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | エキサイトホールディングス株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 会社分割(新設分割)+株式譲渡 |
コインチェック株式会社は、暗号資産交換業を中心としたクリプトアセット事業を展開するフィンテック企業です。
エキサイトホールディングス株式会社は、通信・インターネットサービスを主軸にもつ総合IT企業で、近年はSaaS・DX事業への注力とM&Aによる事業ポートフォリオ強化を進めています。
本M&Aにより、エキサイトホールディングスはバーチャル株主総会支援サービスという成長市場に本格参入し、DX事業の中核プロダクト拡充を図る狙いがあります。
東海東京証券株式会社×髙木証券株式会社
2019年9月、東海東京フィナンシャル・ホールディングスの完全子会社である東海東京証券株式会社は、同じくグループ傘下の髙木証券株式会社を吸収合併しました。
| 譲渡(売り手)側 | 髙木証券株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 東海東京証券株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 吸収合併 |
東海東京証券株式会社は、東海東京フィナンシャル・ホールディングスの完全子会社で、証券業を中心に幅広い金融サービスを展開しています。
髙木証券株式会社は、関西圏を中心に地域密着型の証券営業基盤をもつ証券会社で、主にIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)事業を展開していました。
本M&Aにより、東海東京証券株式会社は髙木証券の営業基盤を取り込み、 店舗や業務の統合を進めることでサービスの向上を目指すとともに、IFA事業の再編・拡充を通じて新たな成長分野への展開を図りました。
証券業界のM&Aを成功させるポイント

証券業界でM&Aを成功させるには、「事前準備」「買い手選定」「従業員対応」の3つの視点が特に重要です。
まず、スムーズなM&Aを実現するには事前の準備が不可欠です。具体的には、財務状況を整理し、収益性の改善やコスト削減などに取り組むことで、企業価値の向上を図る必要があります。 次に、買い手候補の選定も成否を分ける要素です。ただ高値で買ってくれる相手を探すのではなく、事業内容や組織文化においてシナジーが見込める企業を慎重に選ぶことが重要です。 そして、M&Aに伴う従業員の不安を軽減する取り組みも忘れてはなりません。社内への誠実な情報共有や将来のビジョンを丁寧に伝えることで、離職やモチベーション低下といったリスクを抑えることができます。
これらのポイントをしっかり押さえるには、M&A仲介会社など専門家のサポートを活用するのも有効な手段です。
まとめ
証券業界では、規制強化やデジタル化など経営環境の変化を背景に、事業再編や経営基盤の強化を目的としたM&Aが活発化しています。その一方で、M&Aの実施にはリスクも伴うため、的確な判断と専門的な支援が成功のカギを握ります。
証券業界でのM&Aをご検討中の方は、豊富な実績と専門知識をもつM&A助言会社・株式会社レコフにぜひご相談ください。初めてのM&Aでも安心して進められるよう、プロの視点でしっかりとサポートいたします。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00